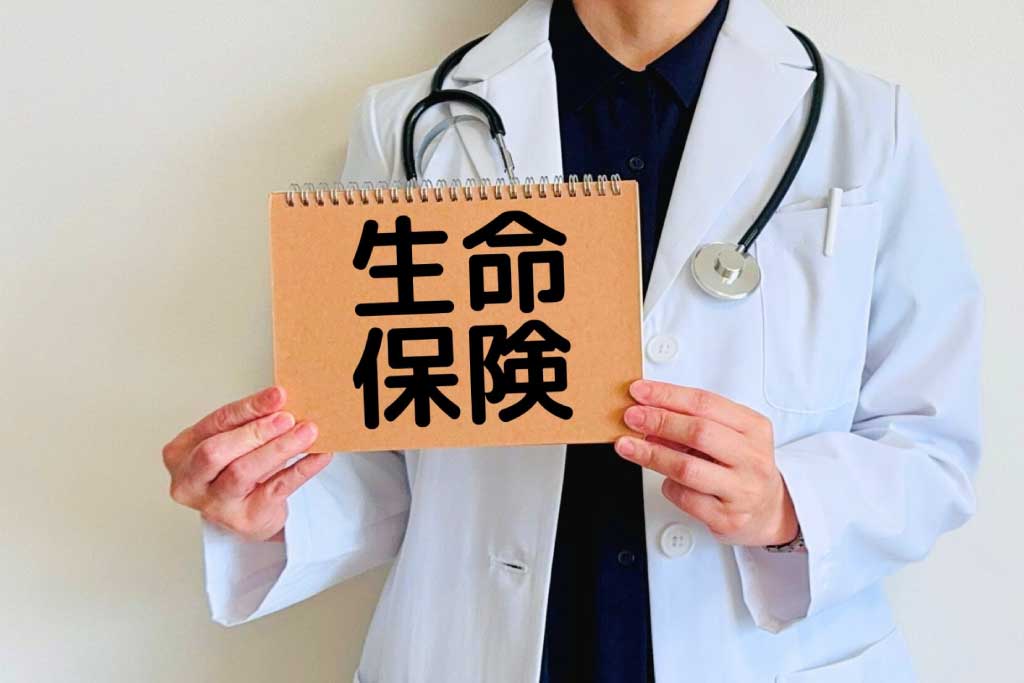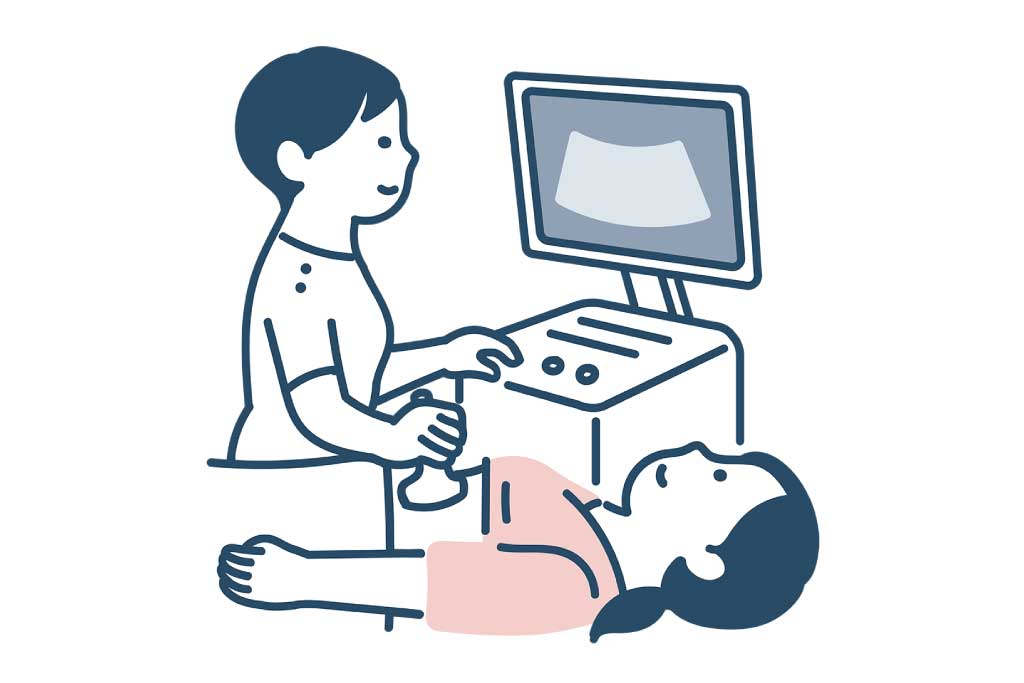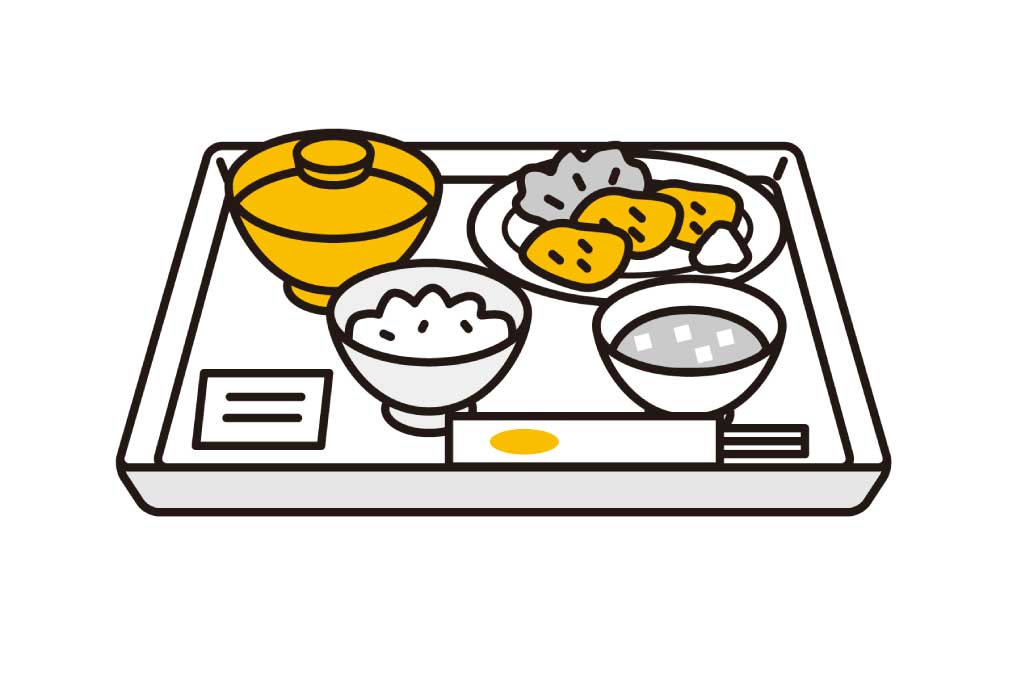医療法人が知りたい適正な節税対策9選|税務上の注意点も重点的に解説


個人開業の医院・クリニックでも、医療法人でも、節税対策をしながら適切に納税することはとても大切です。
特に医療法人の場合は、適正に節税対策を行うかどうかで、手元に残るキャッシュが大きく変わります。
しかし、間違った節税対策を行うと、税務調査で追徴課税を課される可能性があります。
最悪、悪質な所得隠しを指摘されてしまうことになれば、社会的な信用を失うことになりかねません。
そこで本記事では、医療法人が取り組むべき代表的な節税対策について、税務上の注意点と併せてお伝えします。
特にこれから医療法人化を検討している先生や、医療法人を設立したばかりの先生は最後までご覧ください。
【対策①】役員報酬の最適化で手取りを最大化する

医療法人の節税対策で重要になってくるのが、役員報酬の設定です。
役員報酬の場合でも給与所得控除を適用できることも念頭に置いて、医療法人と個人の手元に残るキャッシュを最大化することを目指します。
役員報酬では給与所得控除が適用される
個人開業医院の院長先生の場合、個人事業主には給与という概念がないので、給与所得控除は適用されません。
そのため、クリニックの利益のほぼすべてが事業所得となり、院長個人の所得税・住民税の課税対象となります。
一方、医療法人では、理事長は法人から給与(役員報酬)を受け取る形になります。
役員報酬であっても、給与であることには変わりないので、以下のように最大195万円の給与所得控除が適用されます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
※国税庁「No.1410 給与所得控除 」より抜粋
給与所得控除があると、所得を圧縮できるため、個人開業医時代と同じ所得額であっても、税負担を軽減できます。
なお、2025年度税制改正によって、2025年分以降は給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に引き上げられ、対象となる給与が190万円まで拡大されます。
【改正前】
給与収入≦1,625,000円⇒給与所得控除額:550,000円
1,625,001円≦給与収入≦1,800,000円まで⇒給与所得控除額:収入金額×40%-100,000円
【改正後】
給与収入≦1,900,000円⇒給与所得控除額:650,000円
役員報酬を損金算入する際のルールに気を付ける
役員報酬はいつでも自由に金額を変更できるわけではなく、医療法人の損金として認められるために、ルールを守らないといけません。
そのなかの1つが、定期同額給与です。
⇒⇒⇒国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) 」
定期同額給与は、毎月の支給額が一定であることを求めるもので、事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額を、原則として年度中は変更できません。
期中の利益状況に応じて安易に報酬額を変動させると、損金算入できず、法人税の追徴課税を受けるリスクがあります。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
医療法人・個人の最適バランスを考える
役員報酬を高く設定すれば、医療法人の利益が圧縮されて法人税は下がりますが、理事長先生の所得税・住民税、そして社会保険料の負担が増加します。
逆に低く設定すれば、個人の税負担は減りますが、医療法人の利益が残り、法人税が高くなります。
つまり、「法人税」と「個人の所得税・住民税・社会保険料」のバランスを考えて、役員報酬を最適化することがポイントになります。
具体的な役員報酬のシミュレーションについては、以下の記事を参考にしてください。
【対策②】家族に給与を支払って世帯の税負担を軽減する

理事長先生だけではなく、クリニックに従事されているご家族にも給与(役員報酬)を支払うことで、世帯全体での税負担を軽減できることがあります。
所得分散と言われるもので、家族経営の医療法人でよく利用されますが、勤務実態があり、報酬額が妥当であることが前提となります。
所得分散により所得税の軽減効果がある
日本の所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる累進課税の仕組みです。
例えば、理事長お一人が3,000万円の役員報酬を得る場合と、理事長、配偶者で1,500万円ずつ受け取る場合を比較してみます。
世帯収入は同じ3,000万円ですが、前者の所得税率が40%であるのに対し、後者は33%となり、世帯全体での税負担が軽減されます。
さらに、ご家族も給与所得控除を利用できるため、課税対象額を二重に圧縮できます。
結果として、世帯全体で納税する所得税・住民税の合計額を引き下げることが可能になります。
節税対策という税務面以外にも、家族経営には運営面でのメリット・デメリットがあります。
医療法人の経営の観点では、家族経営のメリット・デメリットを考慮することが大切です。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
勤務実態がなければ税務調査で否認される
家族の所得分散は有効な節税対策ですが、税務調査では厳しくチェックされるポイントの1つです。
具体的には、ご家族への給与を損金算入して法人税を軽減するには、次の2つの条件を満たさなければいけません。
| 勤務実態があること | 家族が出勤して医療法人の業務に従事していること |
| 給与が妥当であること | 担当する業務内容や勤務時間に照らして社会通念上、妥当な給与であること |
2点を満たさずに支払われた給与は、税務調査で否認され、法人税の追徴課税に繋がるので注意してください。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
【対策③】生命保険を活用して将来の退職金を準備する

生命保険による税制上のメリットを享受しながら、将来の退職金を準備するのも良いでしょう。
医療法人にとっても、退職金を受け取る個人にとっても節税効果があります。
保険料の一部を医療法人の損金にできる
生命保険で退職金を積み立てる場合は、医療法人を契約者、理事長を被保険者として生命保険に加入するので、医療法人が保険料を支払います。
保険の種類や契約内容によって異なりますが、支払った保険料の一部を医療法人の損金として計上できるため、法人税を圧縮する効果があります。
そして、理事長が退職するタイミングなどで保険契約を解約すると、医療法人は解約返戻金を受け取ることができます。
生命保険には様々なタイプがあり、損金算入のルールも複雑なため、顧問税理士や専門知識のあるFPに相談の上、慎重に検討しましょう。
医療法人の生命保険については、以下の記事をご覧ください。
退職所得控除が適用されて所得税が軽減される
退職金にかかる課税額は、次のように計算されます。
退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
【退職所得控除】
| 勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (A - 20年) |
※国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) 」を元に作成
このように、退職金の課税対象額は、退職所得控除後の金額の半分になるので、大幅な所得税の軽減に繋がります。
【対策④】死亡退職金と弔慰金の非課税枠を最大限活用して相続税に備える

医療法人の先のことを考えると、相続・承継対策は切実な問題です。
理事長先生が万が一お亡くなりになった際、医療法人からご遺族へ支払われる死亡退職金と弔慰金には、それぞれ相続税の大きな非課税枠が設けられています。
死亡退職金と弔慰金は併用することができます。
例えば死亡退職金で1,500万円、弔慰金で1,200万円の非課税枠があれば、合計で2,700万円が非課税枠となり、大きな相続税対策になります。
もちろん、医療法人としては損金計上できるので、法人税の圧縮にも繋がります。
なお、相続税対策については、以下の記事も参考にしてください。
死亡退職金による非課税枠
理事長先生が亡くなると、ご遺族が受け取る死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。
(1)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
しかし、次の計算式による非課税枠が設定されています。
死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者とお子様2人の合計3名の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。
弔慰金による非課税枠
死亡退職金とは別に、医療法人は福利厚生の一環として、ご遺族に対しお悔やみの気持ちを示す弔慰金を支払うことができます。
この弔慰金にも、次の計算式による相続税の非課税枠が設けられています。
・業務上の死亡の場合:死亡時の月額報酬 × 36ヶ月分
・業務外の死亡の場合:死亡時の月額報酬 × 6ヶ月分
※国税庁「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い 」を元に作成
例えば、理事長先生の最終的な月額報酬が200万円で、業務外で亡くなられた場合、200万円×6ヶ月= 1,200万円までが弔慰金として非課税でご遺族に支払えます。
弔慰金を非課税で支払うには、役員退職慰労金規程や慶弔見舞金規程などで支給の根拠を定めておくことが重要です。
【対策⑤】適正な役員退職金を算出する
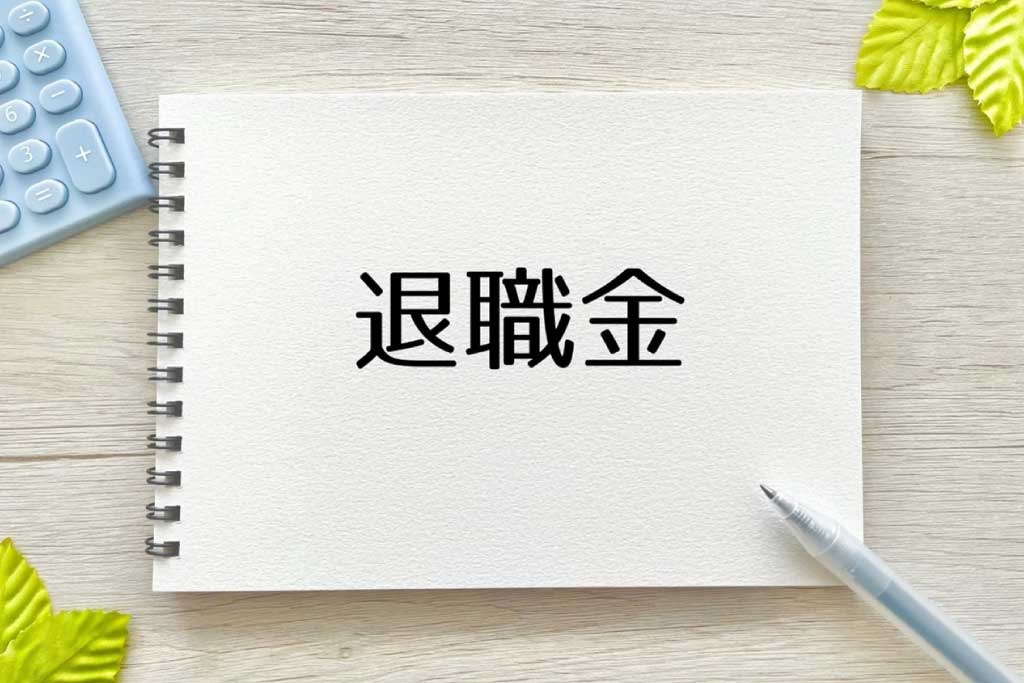
役員退職金は、医療法人にとっては多額の損金計上となり、個人には退職所得控除が適用されるため、税金対策のインパクトが高くなります。
しかし、医療法人の経費として認められるためには、その金額が不相当に高額でないこと、つまり社会通念上、適正な金額であることが前提です。
適正額を超えた部分は損金として認められず、役員賞与とみなされる可能性があります。
功績倍率法で役員退職金を算出する
適正な役員退職金を、客観的に算出するために、実務上、広く用いられているのが功績倍率法です。
功績倍率法は、以下の計算式で役員退職金の適正額を計算します。
役員退職金の適正額=最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率
功績倍率とは、役員の役職や、法人への貢献度を反映させるための係数で、法律上の目安はありませんが、次のような目安があります。
| 役職 | 功績倍率の目安 |
| 理事長 | 2.5~3倍 |
| 理事 | 2~2.5倍 |
| 監事 | 1.5~2倍 |
役員退職慰労金規程を整備しないと損金算入できない可能性がある
役員退職金について、税務調査で否認されないようにするには、役員退職慰労金規程を整備しておきましょう。
そのなかで、功績倍率法で算出することと、功績倍率の数値について明確にしておきます。
また、実際に退職金を支給する際には、社員総会や理事会で決議して、議事録を適切に保管しておくようにしましょう。
【対策⑥】出張旅費規程を整備して日当を非課税で受け取る

学会の参加など出張する機会が多い場合は、出張旅費規程の整備をするのも1つの手です。
出張旅費規程を設けることで、医療法人・個人双方に節税メリットがあるのはもちろん、事務負担の軽減にも繋がるからです。
日当が非課税になり社会保険料の算定対象にもならない
出張旅費規程を定めておけば、出張中の食事代や細かな諸雑費に充てるための「日当」を法人から支給できます。
この日当は、医療法人は全額損金計上できるのはもちろん、個人では給与扱いにならないため、所得税・住民税がかかりません。
また、社会保険料の算定対象にもならないので、出張に行ったスタッフ個人の手取りを増やすことができます。
妥当な出張旅費規程でなければ税務調査で否認される
出張旅費規程は、適正な規程の整備と運用が前提であり、税務調査でチェックされやすい項目である点は認識しておく必要があります。
税務調査で否認されないようにするには、次の点を守って出張旅費規程を整備しましょう。
・対象者は全スタッフとする
・社員総会などで出張旅費規程の承認を得る
・妥当な支給金額を設定する
・出張旅費精算書を作成して、業務記録を残しておく
出張旅費規程の詳細は、以下の記事をご覧ください。
【対策⑦】医療用機器等の特別償却制度を利用して税負担を圧縮する

高額な医療機器への設備投資は、クリニックを成長させるうえで不可欠な戦略の1つですが、多額の資金負担を伴います。
しかし、医療法人だからこそ活用できる税制優遇措置である「医療用機器等の特別償却制度」を用いることで、法人税負担を圧縮できます。
特別償却とは通常の減価償却費とは別枠で経費計上できる優遇制度
特別償却とは、設備投資を行った場合に、通常の減価償却費とは別枠で取得価額の一定割合を追加で損金計上できる制度です。
例えば、1,000万円の医療機器を導入し、12%の特別償却が認められた場合、通常の減価償却費とは別に1,000万円×12%=120万円を上乗せして経費計上できます。
特別償却によって、投資初年度の課税所得が大幅に圧縮され、納税額が減ることで手元のキャッシュフローが改善します。
税金が免除されるというわけではなく、課税の繰り延べになりますが、設備投資初期の税負担を軽減することができます。
3つの医療機器の特別償却制度
一般的な中小企業向けの特別償却制度のある中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制は、医療機器の購入などは対象外とされています。
医療機器の購入で活用できるのは、次の3つの特別償却制度があり、令和7年度の税制改正で2年延長が決まっています。
| 対象 | 特別償却割合 | |
| 医師等の働き方改革のための特例 | 勤務時間短縮に資する器具及び備品、ソフトウェア(30万円以上のもの)など | 15% |
| 高額な医療機器の導入に関する特例 | 高度な医療の提供に貢献する、比較的新しい高額な医療機器(取得価額500万円以上) | 12% |
| 地域医療構想の実現のための特例 | 病床の再編などにより取得する建物やその附属設備など、地域の医療提供体制の再編に協力する場合 | 8% |
※厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係) 」より抜粋
いずれの特例償却についても、都道府県等へ計画書を提出し、事前の手続きが必要となります。
なお、医療機器の減価償却については、次の記事をご覧ください。
【対策⑧】4年落ち中古車を購入して減価償却で大きな経費を作る
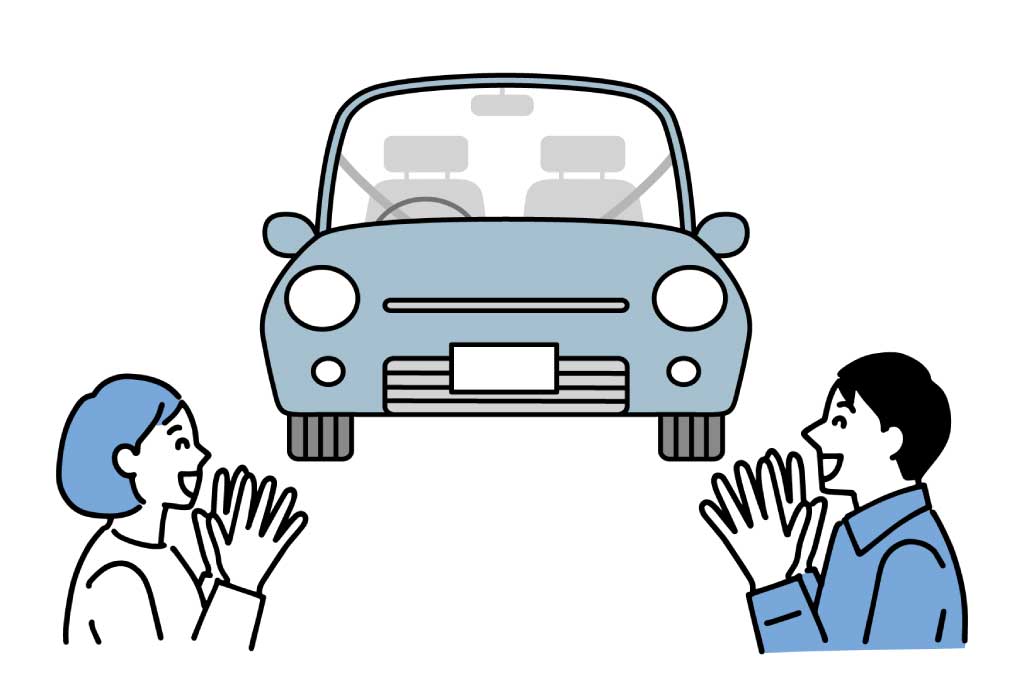
医療法人に限らず、減価償却資産による法人税の圧縮でよく利用されるのが、中古車の購入です。
有名なのが、「4年落ちの中古車」による節税です。
4年落ち中古車の節税効果が高い仕組み
自動車や医療機器などの高額資産は、購入した年に全額を経費にはしません。
耐用年数で分割して経費計上する減価償却が原則となります。
新車の普通自動車の耐用年数は6年ですが、中古車の場合は特別な計算式で耐用年数を算出します。
その結果、4年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。
未償却残高に一定の償却率を掛けて減価償却費を計算する定率法では、耐用年数2年の償却率は100%です。
つまり、4年落ち中古車を購入した場合、初年度にそのほぼ全額を経費計上することが可能になります。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
4年落ち中古車の税務調査での注意点
4年落ち中古車の購入は、税務調査ではチェックされやすい項目の1つです。
税務調査で否認されないようにするには、医業のために使用されているということが大前提になります。
例えば、理事長先生の通勤や往診、学会参加などです。
運転日報などを作成して、「誰が、いつ、どこへ、何のために何km走行したか」を記録しておく必要があります。
もし、私的に利用していれば、給与とみなされて、先生に多額の所得税を課されるリスクがあるので、十分使用状況を管理しましょう。
【対策⑨】福利厚生費でスタッフ満足度と節税を両立する
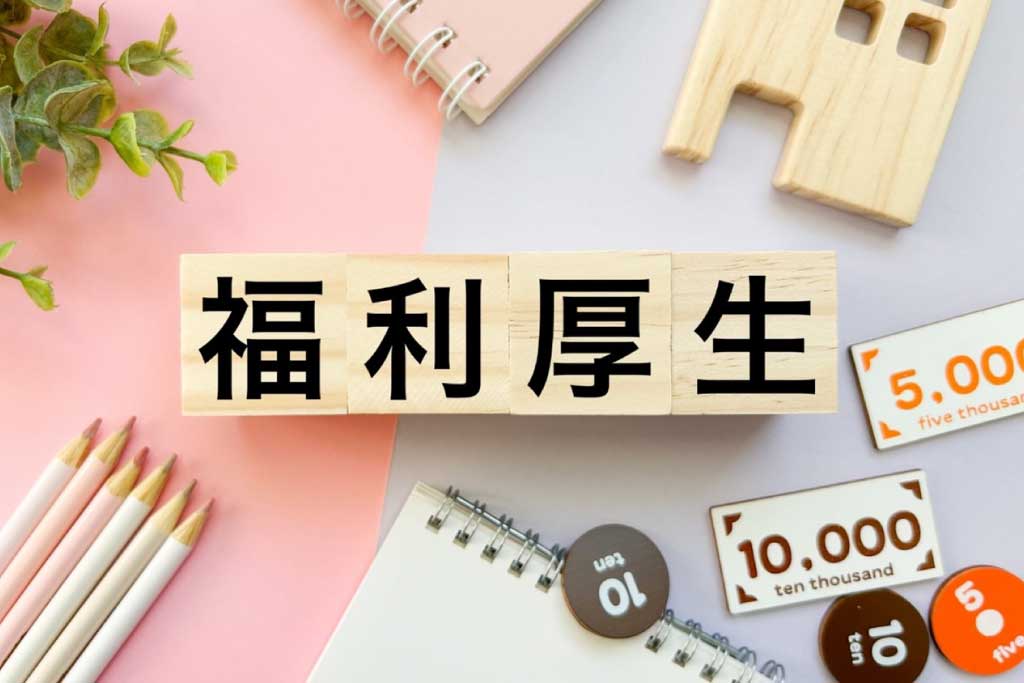
クリニックの安定経営には、優秀なスタッフの確保と定着が不可欠ですが、そのための有効な施策の一つが、福利厚生の充実です。
スタッフの働く意欲や満足度を高める福利厚生費は、医療法人にとっては全額を損金計上できるため、節税とスタッフ満足度を両立することが可能です。
福利厚生費の要件を満たさないと税務調査で否認される
福利厚生の内容によって、医療法人の損金計上できる項目は変わりますが、共通することは、以下の要件は必ず満たす必要があります。
| すべての役員・従業員が対象であること | 理事長先生など特定のスタッフだけを対象とした支出は福利厚生費とは認められず、役員報酬や給与として課税対象になる。 |
| 社会通念上、妥当な金額であること | 常識の範囲を逸脱した、あまりに高額・豪華な支出は福利厚生とはならない。 |
医療法人が使用できる福利厚生の例
上記を踏まえて、医療法人が活用しやすい具体的な福利厚生費の一例を示すと次の通りです。
・人間ドック・健康診断費用の補助
・食事補助
・社員旅行や忘年会などのレクリエーション費用
・慶弔見舞金
・自己啓発、スキルアップ関連費用 etc
いずれも、福利厚生費として計上するには、いずれも全スタッフが対象で社会通念上、妥当な金額であることが大前提となります。
食事補助や社員旅行の福利厚生費については、以下の記事を参考にしてください。
【まとめ】医療法人の節税対策で適切にキャッシュを残す
医療法人の代表的な節税対策についてお伝えしました。
医療法人によって、適切な節税対策は変わってきますし、税制改正にも常に対応しておく必要があります。
正しく節税対策をするには、医療法人の税務に強い税理士に相談するようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。
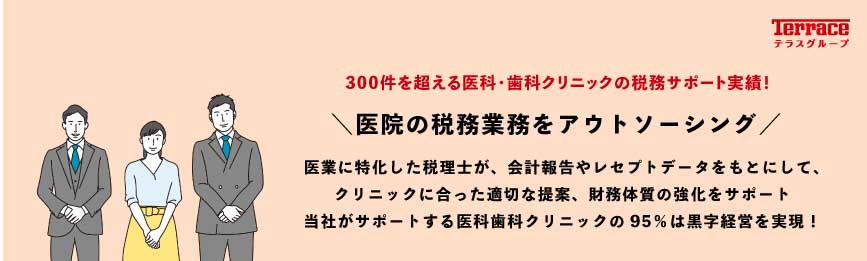
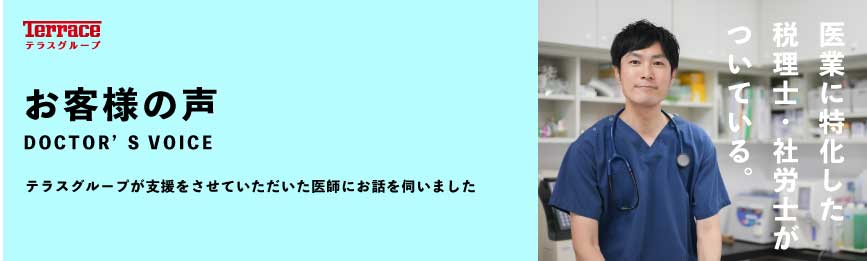


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。