医療機器の耐用年数とは?減価償却費の計算方法や新品と中古の違いなどを重点解説
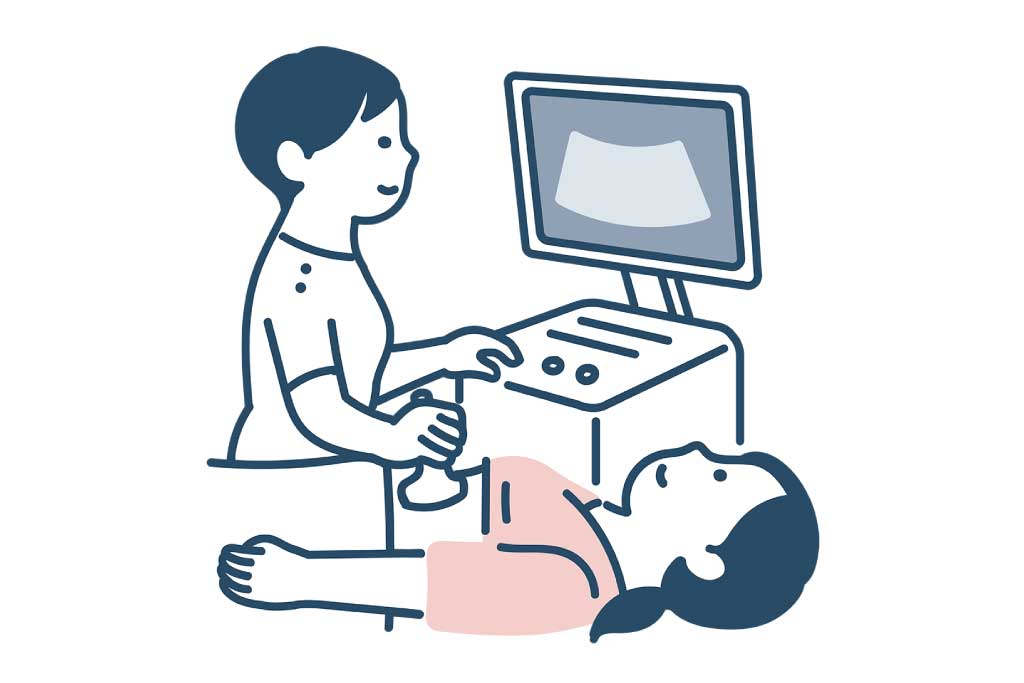
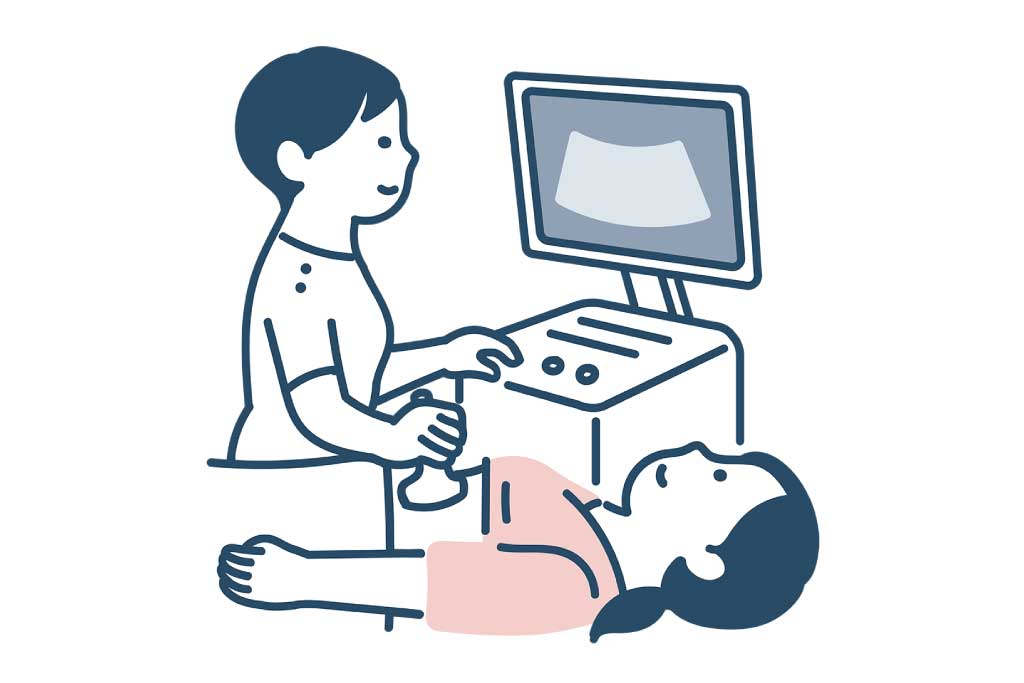
医院・クリニックを開業すると、診療科目や治療方針によって大きな違いはありますが、様々な医療機器が必要です。
医療機器は、経費のなかでもかなりのウェイトを占めるので、税務上、次の点には十分注意しておく必要があります。
・医療機器の法定耐用年数はどれくらいか?
・医療機器の会計処理はどうすれば良いのか?
・中古の医療機器を導入したらどうなるのか?
・耐用年数と耐用期間、耐用寿命は何が違うのか?
・医療機器の買い替えのタイミングは?
そこで、今回は医療機器の耐用年数や減価償却費の計算方法など、税務上のポイントについて解説します。
医療機器の法定耐用年数と減価償却費の計算方法

医療機器の「耐用年数」と聞くと、機器そのものの寿命を思い浮かべがちですが、それは「耐用寿命」という別の言葉があります。
耐用年数とは、あくまで「税務上、減価償却を行うために定められた、固定資産を使用できるとされている期間」のことです。
医療機器などの減価償却資産は、年月が経過するほど資産価値が減っていき、最終的に0円となるという考え方があります(厳密には1円まで)。
つまり、耐用年数は資産価値が0円になるまでの期間であり、購入費用を耐用年数で分割して経費計上する会計処理が減価償却です。
この点を踏まえて、医療機器の法定耐用年数と減価償却費の計算方法を解説します。
国税庁が定める医療機器の法定耐用年数
医療機器の法定耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 」で、次のように定められています。
| 細目 | 耐用年数 |
| 消毒殺菌用機器 | 4年 |
| 手術機器 | 5年 |
| 血液透析又は血しょう交換用機器 | 7年 |
| ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6年 |
| 調剤機器 | 6年 |
| 歯科診療用ユニット | 7年 |
| 光学検査機器①ファイバースコープ | 6年 |
| 光学検査機器②その他のもの | 8年 |
| レントゲンその他の電子装置を使用する機器①移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4年 |
| レントゲンその他の電子装置を使用する機器②その他のもの | 6年 |
| その他のもの①陶磁器製又はガラス製のもの | 3年 |
| その他のもの②主として金属製のもの | 10年 |
| その他のもの③その他のもの | 5年 |
医療機器の減価償却費の計算方法
先ほどお伝えしたように、減価償却資産は、購入費を一度に経費計上するのではなく、耐用年数で分割して、少しずつ経費として計上します。
減価償却の計算方法には、一般的には定額法と定率法があります。
| 定額法 | 定率法 | |
| 特徴 | 毎年同額の費用を計上する | 初年度が最も多く年々費用が減少 |
| 計算式 | 取得価額×定額法償却率 | (取得価額−減価償却累計額)×定率法償却率 ※ただし、償却保証額を下回った年度以降は定額で償却する |
| メリット | ・帳簿の扱いがシンプルになる ・初期利益が多くなる | ・導入初期の節税効果が高い ・早い段階で購入費用を回収できる |
| デメリット | ・導入初期の節税効果が低い ・利益の増減にかかわらず償却費が一定である | ・帳簿の扱いが複雑になる ・後年になるほど節税効果が低い |
例えば、耐用年数6年の医療機器を1,200万円で導入したとします。
この場合、定額法では6年間にわたって200万円ずつ経費計上することになります。
ただし、最終年度は、1円の備忘価額を差し引くので、厳密には199万9,999円の償却額になります。
一方、定率法の場合は、耐用年数6年の定率法償却率は0.333なので、1~3年目までの減価償却費は次のようになります。
| 1年目 | 399万6,000円 |
| 2年目 | 266万5,332円 |
| 3年目 | 177万7,778円 |
ところが、4年目以降から計算方法が変わります。
というのも、定率法の場合は、償却保証額(=取得価額×保証率)」を下回った年度からは、残りの年数で均等に償却するからです。
定率法の法定耐用年数6年の保証率は0.09911なので、償却保証額は118万9,320円になります。
1~3年目と同じ方法で、減価償却費を計算していくと、4年目は118万5,776円と、償却保証額を下回ります。
そのため、4年目以降は改定償却率(耐用年数6年の場合は0.334)を乗じて、毎年同額を償却します。
この結果から、4~6年目の減価償却額は以下のようになります(定額法と同じく、最終年度は1年の備忘価額を差し引きます)。
| 4年目 | 118万9,337円 |
| 5年目 | 118万9,337円 |
| 6年目 | 118万2,215円 |
このように、医療機器などの減価償却資産の経費計上は、定額法や定率法で変わってきます。
どちらを選んだ方が自院にとって有利になるかは、最寄りの税理士に相談するようにしてください。
⇒参考:国税庁「No.2106?定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) 」
中古の医療機器の耐用年数
資金を抑えるため、中古の医療機器を導入する医院・クリニックも少なくありません。
実際、新品でなくても、少し古いスペックの中古品でも治療にはまったく支障がない場合もあります。
もちろん、後述する耐用期間や耐用寿命には気を付ける必要があり、使用できる期間は新品より短くはなりますが、検討の余地は十分にあります。
また、中古の医療機器は、新品に比べて短い期間で減価償却できるため、早期に経費計上できるという税務上のメリットがあります。
中古の医療機器の場合、上記の法定耐用年数をもとにして、国税庁が示す簡便法を用いて耐用年数を算出します。
簡便法については、法定耐用年数を経過していない中古資産と、経過した中古資産で分けて考えます。
①法定耐用年数を経過していない中古資産
まだ法定耐用年数が残っている中古資産の場合は、以下の計算式で算出します。
計算式:中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
例えば、法定耐用年数8年の内視鏡を、製造から3年経過した中古品として購入した場合の耐用年数は、次のように求められます。
(8年−3年)+(3年×20%)=5.6年
小数点以下の端数は切り捨てるため、この場合の耐用年数は5年となります。
②法定耐用年数を経過した中古資産
すでに法定耐用年数を過ぎている中古資産の場合は、計算がよりシンプルになります。
計算式:中古資産の耐用年数=法定耐用年数×20%
例えば、法定耐用年数8年の内視鏡を、製造から10年経過した中古品として購入した場合の耐用年数は、8年×20%=1.6年となります。
この場合も小数点以下の端数は切り捨てますが、計算結果が2年未満になった場合は、耐用年数は2年となります。
⇒参考:国税庁「No.5404?中古資産の耐用年数 」
【比較】耐用年数と似た用語との違い

先ほどお伝えした通り、耐用年数は会計処理に必要な数字で、年数を経過したからといって、医療機器が使えなくなるわけではありません。
また、逆に耐用年数期間中は「故障しない」ということでもありません。
「医療機器がいつまで使えるのか」を示す言葉は他にもあります。
耐用年数と似た言葉なので、混同しないように注意してください。
耐用期間
耐用期間とは、医療機器メーカーが「医療機器を安全に使用できる標準的な期間」として設定した目安のことです。
適切な使用環境や保守点検・メンテナンスを前提とした期間となっており、医療の安全を確保する目的で定められています。
耐用期間を超えた医療機器を使用すると、故障リスクが高まり、医療事故のきっかけになりかねません。
法定耐用年数とは異なり、法的拘束力はありませんが、機器の更新を検討するうえでは重要な判断材料となります。
耐用寿命
耐用寿命とは、部品の摩耗や経年劣化などの物理的理由や、医療技術的な理由で、医療機器が使用できなくなるまでの期間を指します。
製品寿命というとわかりやすく、純粋に技術的な限界を示す言葉です。
医療機器メーカーが定める耐用期間は、この耐用寿命よりも安全を見て短く設定することが一般的です。
使用期限
使用期限とは、未開封で適切に使用されている医薬品などの品質が保持される期限のことです。
食品や化粧品に表示されている賞味期限、消費期限に近いものをイメージするとわかりやすく、医薬品などの消耗品に設定されています。
保証期間
保証期間とは、医療機器の購入後、メーカーが「通常の使用範囲内で発生した故障について、無償で修理・交換を行います」と約束する期間です。
家電製品の保証期間と、ほぼ同じ意味を持ち、多くの場合、購入日から1年間とされるのが一般的です。
保証期間を過ぎてからの修理は、原則として有償となります。
医療機器の買い替えのタイミングを見極める5つの基準

最後に、医療機器の買い替えのタイミングを見極める基準について解説します。
医療機器への投資は莫大なものになるので、次の点を考慮して判断するようにしてください。
耐用年数が過ぎるタイミング
耐用年数が過ぎると、減価償却費として計上することができなくなるので、税負担が増えてしまいます。
そのため、耐用年数が経過する時期が、医療機器買い替えのタイミングの1つとなります。
しかし、無理な設備投資は税金対策になっても資金繰りを圧迫することになる点は注意しましょう。
耐用期間が過ぎるタイミング
医療機器の耐用期間は、医療の安全性の観点から重要です。
特にメーカーの保守サポートが終了している医療機器は、万が一の故障時に迅速な対応ができず、診療に支障が出る可能性があります。
決算期のタイミング
予想以上に利益が出た年度の決算月近くに設備投資を行えば、減価償却費で利益を圧縮して、納税額をコントロールすることができます。
また、医療機器によっては、特別償却などの税制優遇措置が受けられることがあります。
特別償却とは、一定の要件を満たす設備に対して、通常の減価償却とは別枠で費用計上できる優遇制度です。
医療機器の場合は、500万円以上の特別償却制度や、中小企業投資促進税制などが該当します。
導入予定の医療機器が、特別償却などの税制優遇措置が適用されないか、最寄りの税理士に確認するようにしてください。
年間の修理・メンテナンス費用が高くなってきたタイミング
古い医療機器は、予期せぬ故障による高額な修理費や、部品交換の費用が嵩むことになります。
自動車の維持費が、古くなるほど高くなることと同じです。
年間の修理・メンテナンスのコストと、新しい医療機器を導入した場合のコストを比較して、どちらが経済的かを判断しましょう。
法改正が行われたタイミング
新しい医療の安全基準や診療報酬改定など、既存の医療機器が法改正などに対応できているかは重要なチェックポイントです。
古い医療機器のままでは、新しい基準を満たすことができず、診療ができなくなる可能性があります。
【まとめ】医療機器の減価償却を理解して適切な税金対策を
医療機器の減価償却の耐用年数や、減価償却費の計算方法について解説しました。
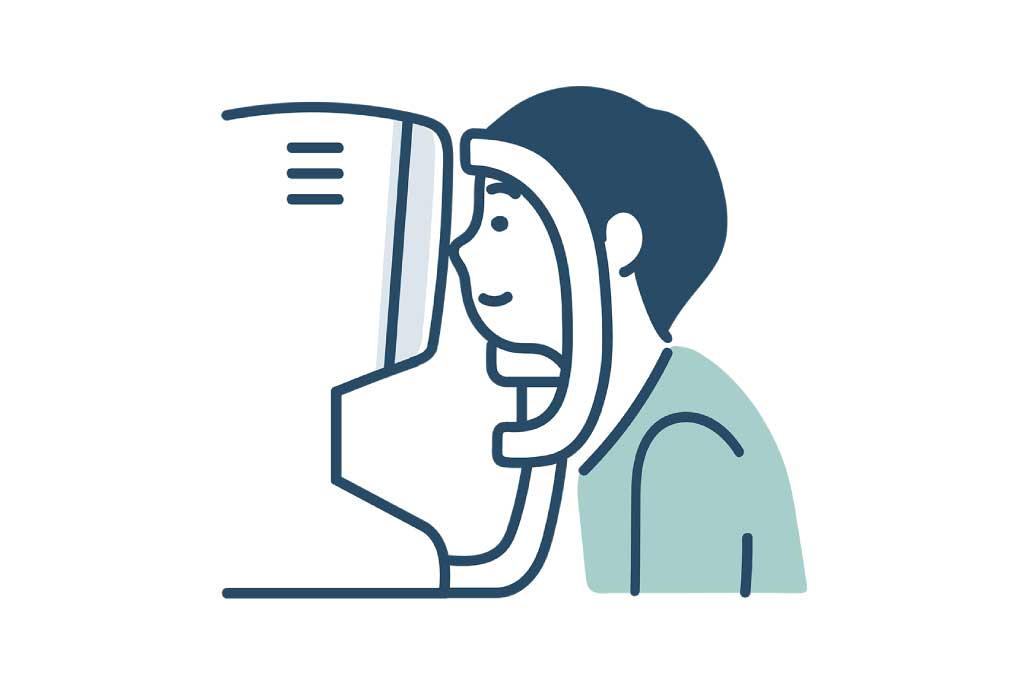
医療機器に限った話ではありませんが、減価償却は正しく理解することで適正な税金対策を行うことができます。
高額な医療機器への設備投資は、医院・クリニックの資金繰りに大きな影響を与えます。
詳細は最寄りの税理士や医療機器の専門家に相談して、長期的な視点で計画を立てて、医療機器を導入していきましょう。
これから開業する先生で、開業資金が気になる先生は、以下の記事も参考にしてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
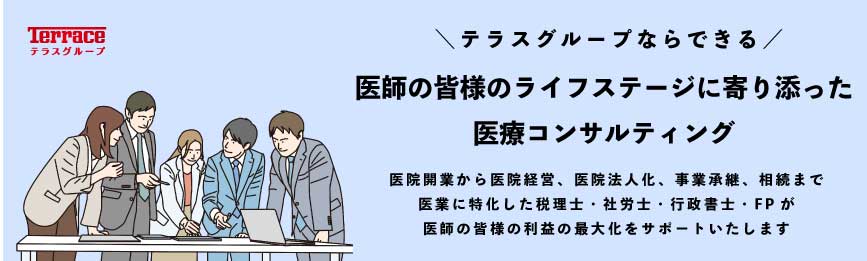
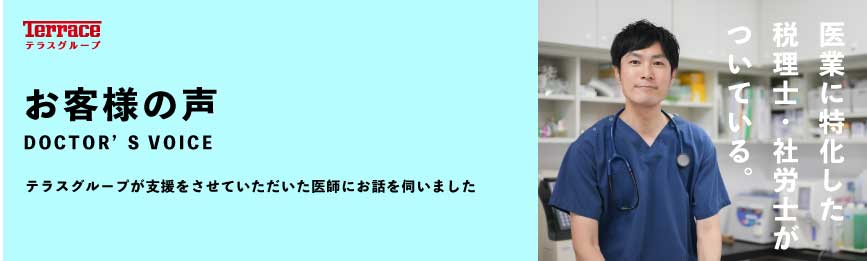
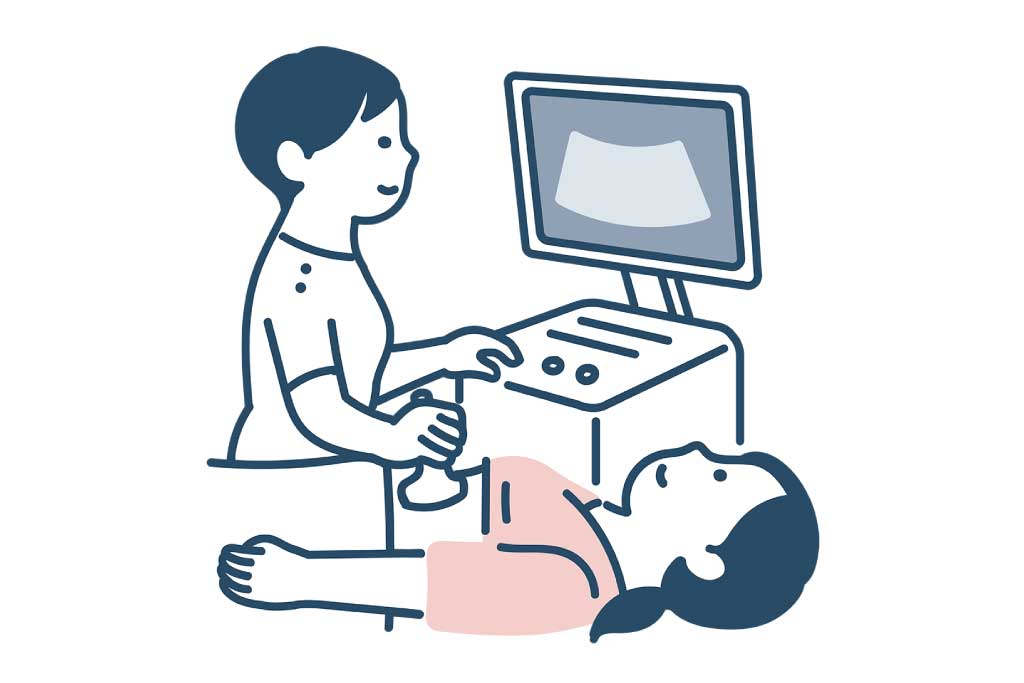

監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。













