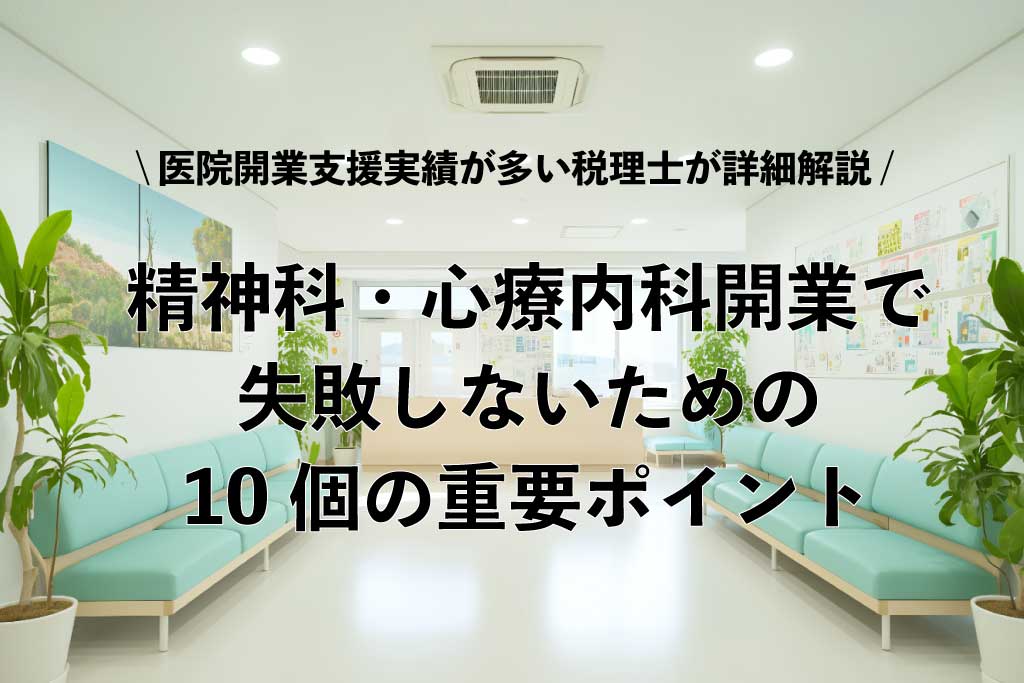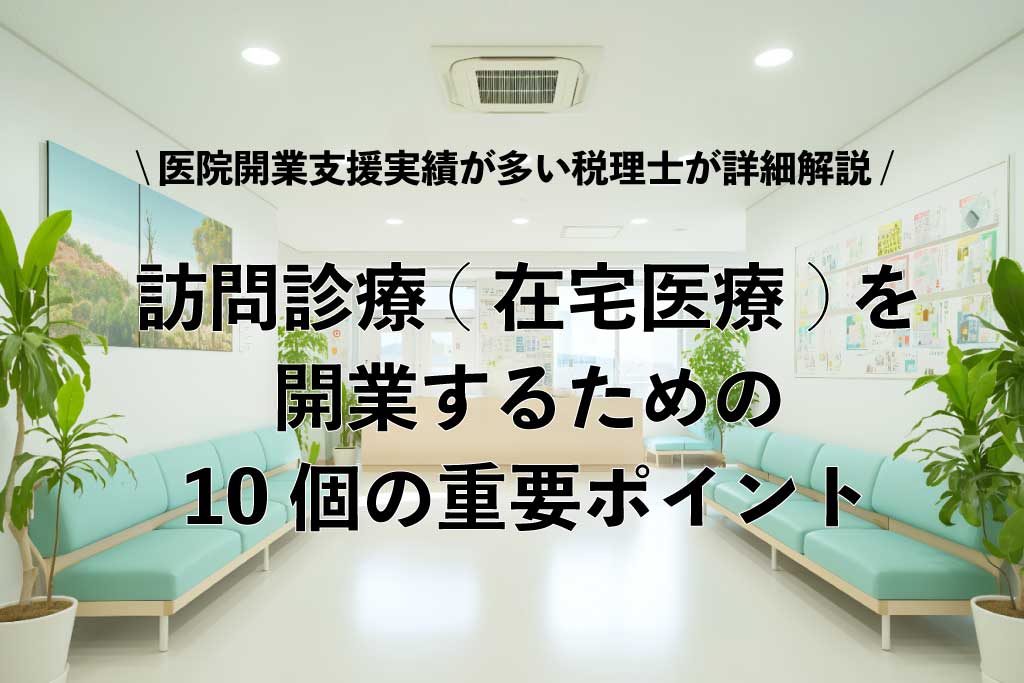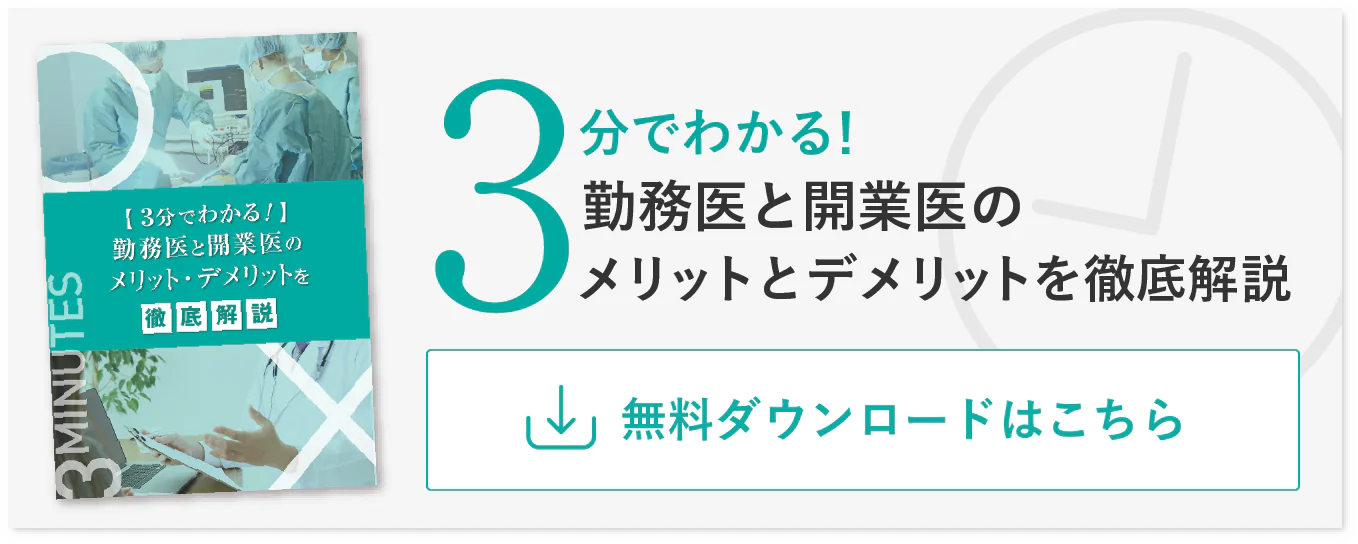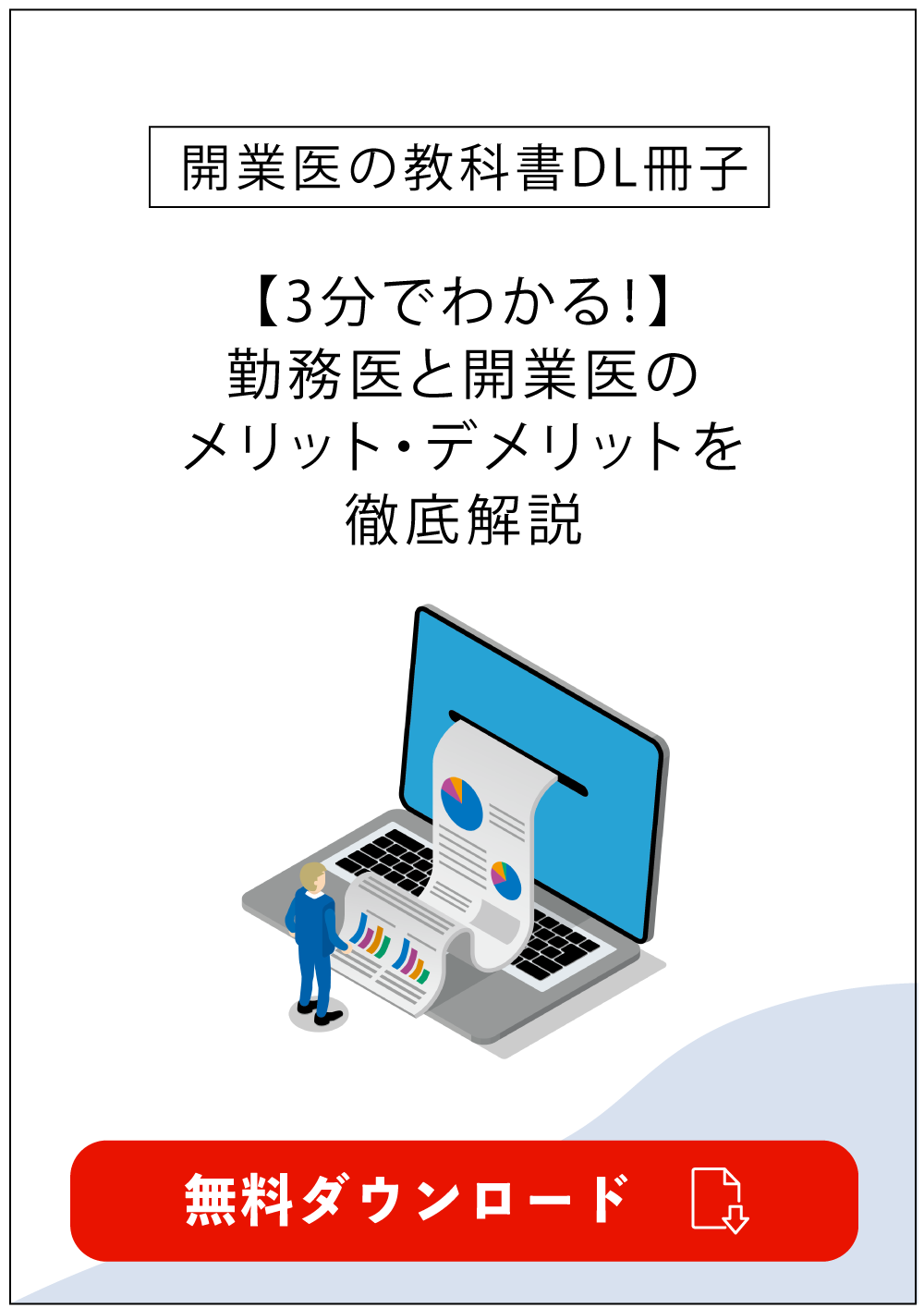ミニマム開業の特徴は?成功するための重要ポイントと向いている医院・クリニックを詳細解説


ここ数年、医院・クリニックでも少額の開業資金と、最低限のスタッフで開業する「ミニマム開業」という言葉を耳にするようになりました。
診療科目にもよりますが、医院・クリニックの開業資金は最低でも8,000万~1億円程度になることも珍しくありません。
開業資金をかければ、それだけリスクが多くなり、開業後に軌道に乗らなければ資金繰りに苦労することになります。
ミニマム開業は、開業資金や開業後の運転資金を抑えつつ、失敗するリスクを極限まで抑える方法と言えるでしょう。
そこで、ミニマム開業の概要やメリット・デメリット、開業時の重要ポイント、向いている医院・クリニックなどをお伝えします。
資金を抑えて開業したいと考えている先生は、ぜひ最後までご覧ください。
医院・クリニックのミニマム開業と通常の新規開業の違い

医院・クリニックのミニマム開業について、具体的に定義が定められているわけではありません。
ただ、一般的に開業資金をできるだけ抑えて、最低限の広さの物件、スタッフ数、医療機器で医院開業することを指します。
具体的には、通常の新規開業と比べると次の比較表の通りになります。
| ミニマム開業 | 通常の新規開業 | |
| 開業資金 | 低い(5,000万円以下) | 高い(8,000万~1億円) |
| 物件 | 小規模(15~25坪目安) | 中規模(40~50坪目安) |
| スタッフ | 医師+1~2人程度 | 医師+4~5人程度 |
| 医療機器 | 必要最低限(中古やリースもあり) | 充実(最新機器も積極的に導入) |
| 来院患者数 | 少ない | 多い |
| 医業収入 | 少ない | 多い |
| 損益分岐点 | 低い | 高い |
| 資金的なリスク | 低い | 高い |
| 方針転換 | しやすい | しにくい |
ミニマム開業と通常の新規開業の明確な違いは定義されていませんが、目安としては上記の通りです。
ミニマム開業は、スタッフ数や医療機器、院内の面積を最小限にするので、開業資金、そして開業後の運転資金も抑えることができます。
一方で、通常の新規開業ほど患者数を見込むことができず、医業収入は低くなる傾向にあります。
つまり、ミニマム開業は損益分岐点が低く設定されており、少ない患者さんで黒字化を目指していきます。
どちらの開業がおすすめということではないですが、先生の診療科目や開業コンセプトによって選択肢は変わってきます。
なお、開業資金を抑える方法には、他にも既存のクリニックを引き継ぐ承継開業や、内装や医療機器のみ引き継ぐ居抜き開業があります。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
ミニマム開業5つのメリット
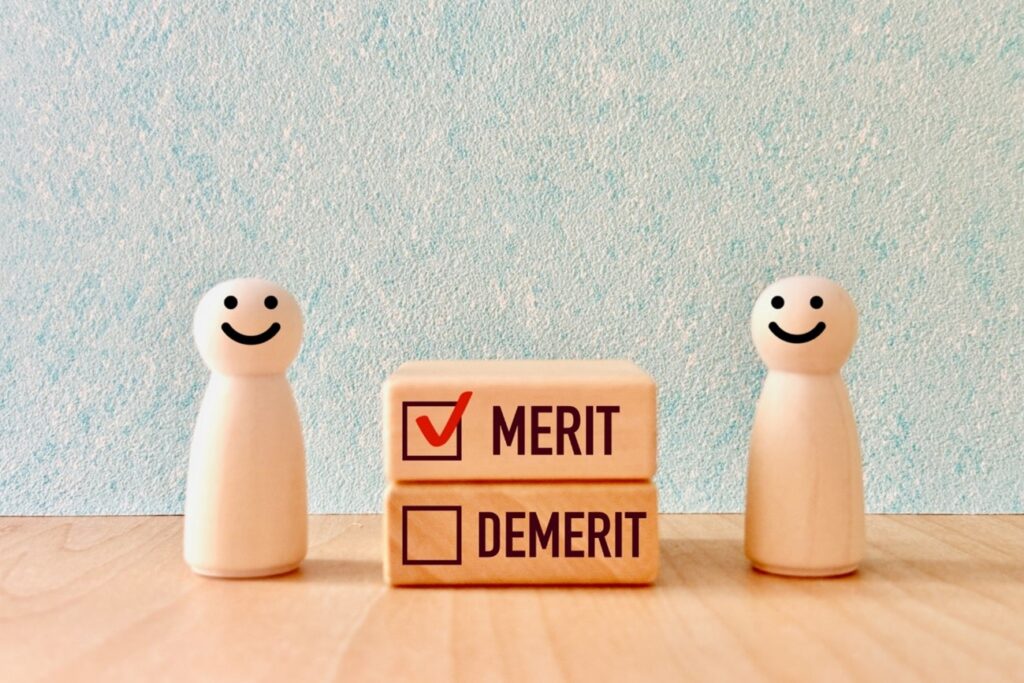
医院・クリニックのミニマム開業の5つのメリットについてお伝えします。
資金面のリスク軽減だけでなく、手取りの収入を増やしやすい、スタッフマネジメントの負担を軽減できるなどのメリットもあります。
開業資金や運転資金を抑えられるから失敗のリスクが低い
ミニマム開業の一番のメリットは、資金を極力抑えることによって、失敗のリスクを低くできる点です。
ミニマム開業では、内装工事費や医療機器の導入費用などを必要最低限に絞り込むので、場合によっては開業資金を2,000~3,000万円に抑えることができます。
その分、借入金を少なくして、月々の返済額を低く抑えることができますし、自己資金を抑えて手元に現金を残すことも可能です。
開業したら、家賃や人件費といった運転資金も低く抑えることができるので、集患が少なくても黒字化が可能です。
資金繰りに余裕があり、「失敗したらどうしよう」という精神的な不安も軽減される点は、ミニマム開業の大きなメリットと言えるでしょう。
概算経費の特例活用で手取りを増やすことができる
ミニマム開業は、人件費や家賃などの固定費を抑えていますから、経費は少なくなります。
実際の経費(実額経費)が少なくなることは出費を抑えられる一方で、利益を圧縮できないので税負担が増えることになります。
しかし医師の場合は、次の場合に、実額経費の代わりに、収入に応じた一定の割合を必要経費として計上できる「概算経費」を選択できます(租税特別措置法第26条)。
・社会保険診療報酬が年間5,000万円以下
・総収入額が7,000万円以下
概算経費率については、租税特別措置法で定められており、次の速算表の通りです。
| 社会保険診療報酬 | 概算経費率の速算表 |
| 2,500万円以下 | ×72% |
| 2,500万円を超え3,000万円以下 | ×70%+50万円 |
| 3,000万円を超え4,000万円以下 | ×62%+290万円 |
| 4,000万円を超え5,000万円以下 | ×57%+490万円 |
例えば、社会保険診療報酬が4,200万円で、実額経費が2,000万円かかったとします。
この場合、概算経費は4,200万円×62%+290万円=2,864万円です。
つまり、概算経費を選択すると、実額経費より664万円多く経費として計算できるので、そのぶん税負担を軽減できることになります。
ミニマム開業の場合は、資金をかけていない分、医業収入も少なめになります。 しかし、社会保険診療報酬の概算経費を選択することにより、手取りの収入を増やすことが可能になります。
柔軟に経営方針を変更しやすい
ミニマム開業は、運転資金が少なく、組織がシンプルであるため、経営方針を柔軟に変更しやすくなります。
大規模なクリニックになると、毎月の固定費がかかることや、多くのスタッフを抱えていることが足かせになることがあります。
「新しい自由診療を導入したい」「診療時間を変更したい」と思っても、なかなか融通が利かないことも少なくありません。
その点、ミニマム開業であれば、小さな組織になっているだけあって、スピーディーな意思決定が可能です。
・患者さんのニーズに合わせて、新しい診療メニューを試験的に導入する
・オンライン診療を導入してみる
・院長先生のライフステージの変化に合わせて診療日時を調整しやすい
外部環境や院長先生自身の状況の変化に素早く対応できる身軽さは、変化の激しい時代では有利になることも考えられます。
スタッフマネジメントの悩みや労力負担を軽減できる
開業医の先生は、医業収入や資金繰りといったお金の悩みだけでなく、スタッフ採用や教育、労務など人の悩みも抱えています。
ミニマム開業では、スタッフを医師以外に1〜2名程度に絞り込むため、マネジメントの悩みや労力負担を大幅に軽減できます。
少数精鋭の組織は、院長先生の理念や治療方針が浸透しやすく、一体感のあるチームを作りやすい利点があります。
スタッフ一人ひとりと密なコミュニケーションを取れる点も、質の高い医療を提供するうえではメリットと言えるでしょう。
しかし、少人数の組織にすることで、院長先生やスタッフの雑務の負担が増えたり、急患対応などが難しくなったりする可能性には注意が必要です。
ワークライフバランスを実現しやすい
ミニマム開業は、損益分岐点が低いので、少ない患者数でも経営が成り立つので、必ずしもフルタイムで働く必要がありません。
そのため、「子育てと介護と両立したい」「趣味の時間を大切にしたい」など、比較的ワークライフバランスを実現しやすくなります。
ミニマム開業は、経済的な安定とプライベートの充実を両立したい院長先生のニーズに合った働き方と言えるでしょう。
しかし、患者さんも少なければ、スタッフも最小限です。
場合によっては業務負担が院長先生に集中してしまう可能性がある点は注意が必要でしょう。
ミニマム開業5つのデメリット
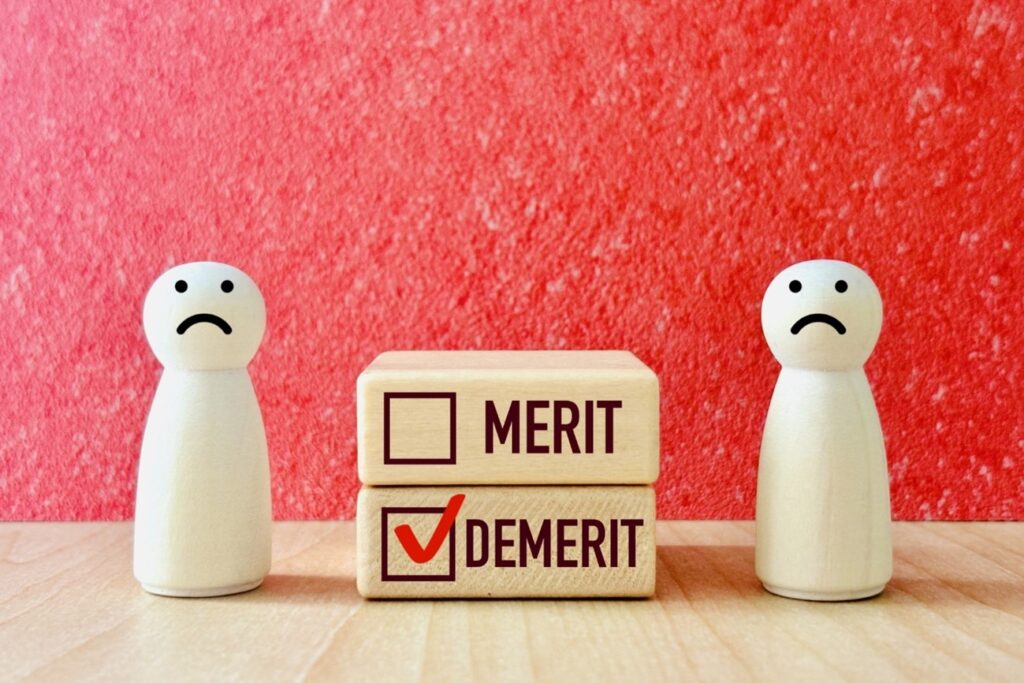
次にミニマム開業のデメリットをお伝えします。
医業収入の上限が低く、設備投資や人件費の追加投資が難しい点は、ミニマム開業の代表的なデメリットです。
また、スタッフ、医療機器、院内スペースがすべて限られており、診療範囲が限定され、機会損失が発生する可能性があります。
医業収入が伸び悩み医療機器や人件費への投資が難しい
ミニマム開業は資金を抑えられる反面、規模が小さくなり医業収入が伸び悩む傾向にあります。
院内スペースやスタッフ数が限られているため、1日に診察できる患者さんの数には物理的な上限があります。
そのため、すぐに医業収入が頭打ちすることになり、医療機器やスタッフの増員への投資が難しくなることが多いです。
低リスクでスタートできる代わりに、事業拡大への選択肢が狭まる可能性がある点は、デメリットとして理解しておく必要があるでしょう。
認知されにくく集患が難しい
院内スペースが狭く、看板なども小規模になりがちなミニマム開業の場合、地域住民への認知度が上がりにくい傾向があります。
ミニマム開業では家賃を抑えるために、小規模なスペースに加えて、少し奥まった場所や空中階(ビルの2階以上)などを選ぶケースも少なくありません。
また、資金力も十分でないので、広告宣伝費にも限界があります。 限られた広告宣伝費の中で、ホームページやSNSなどの情報発信に注力したり、他の医療機関と連携したりするなどして、地道に認知度を高める必要があります。
診療範囲が限定されて機会損失が発生する可能性がある
ミニマム開業は、医療機器を必要最低限に絞り込むことになるので、対応できる疾患や検査の範囲が限定的になりがちです。
例えば、ある症状を訴える患者さんが来院しても、医療機器がないために検査ができず、機会損失が発生することになります。
他の病院と連携していれば紹介することもできますが、そうでなければ地域の患者さんもどこで診てもらえばいいのか困ってしまいます。
このような状態が続くと、患者満足度の低下に繋がり、他のクリニックに患者さんが流れることになりかねません。
どの医療機器を導入して、どこまでを自院で対応するのか、という線引きは地域間連携や診療圏調査を踏まえて慎重に検討する必要があります。
限られたスペースなので動線づくりや院長室やスタッフルームの設置が難しい
ミニマム開業は、どうしてもスペースが限られる傾向があり、レイアウトなど内装の設計には制約が伴います。
患者さんが受付から待合室、診察室、処置室、そして会計へとスムーズに移動できる動線を確保しようとすると、どうしてもスペースに余裕がなくなります。
待合室が窮屈な印象を与えてしまったり、患者さんのプライバシーの確保が難しかったりすることもあり得ます。
また、院長室やスタッフルームが作れない可能性があります。
快適な労働環境を整備できず、スタッフにストレスを与えることになるかもしれません。
15~25坪程度の狭いスペースの場合は、本当に診療に支障が出ないか、医院開業に詳しい業者と相談するようにしましょう。
急なトラブルに対応できる人員的余裕がない
スタッフ数を最小限に絞ることは、人件費を抑えることができますし、人間関係の悩みも少なくなる傾向にあります。
しかし、同時に人員的な余裕がなくなるという懸念もあります。
例えば、スタッフの急な欠勤があった場合、院長先生や残りのスタッフですべて業務をカバーしなければいけません。
患者さんの待ち時間が長くなる可能性がありますし、場合によっては、休診とせざるを得ないこともあり得ます。 また、想定外に患者さんが集中した場合や、急患対応が必要な場合も、最小限のスタッフでは対応しきれない可能性があります。
ミニマム開業で成功するための3つの重要ポイント

これまでのことを踏まえて、ミニマム開業で成功するための重要ポイントについてお伝えします。
いかに、資金を抑えつつ、ミニマム開業によるデメリットを克服していくかが、成功のカギとなります。
インターネットを中心とした集患対策を実施する
ミニマム開業の場合、クリニックが小さく、しかも目立たない場所に開業するケースがあり、看板などで認知を広げるには不利なところがあります。
そのため、ホームページを制作して、インターネット上で集患する戦略が欠かせません。
インターネットであれば、クリニックの規模に関係なく、院長先生のクリニックを認知させることが可能です。
広告宣伝費の予算には気を付けつつ、SEO対策やMEO対策、リスティング広告などでホームページを露出させる対策が必要です。
医院・クリニックのホームページ制作については、以下の記事をご覧ください。
また、SEO対策やMEO対策については、以下の記事をご覧ください。
また、FacebookやInstagramなどSNSアカウントを開設して情報発信するのも良いでしょう。
SNSの集患対策であれば、資金はほとんどかかりませんし、スタッフ採用でも有効です。
インターネットの集患に限らず、広告宣伝費に余裕があれば、チラシを配布したり、内覧会を開催したりするのもおすすめです。 ミニマム開業の場合、看板などの視認性で不利になっている分、他の集患方法を試すようにしましょう。
DX化による生産性向上を図る
ミニマム開業の場合、スタッフの数が必要最低限で、物理的なスペースにも限りがあり、リソースの面で不利になりがちです。
しかし、医療DXを積極的に導入することによって、生産性向上を図ることで解決できることもいくつかあるでしょう。
少数精鋭のスタッフで質の高い医療を提供し続けるためには、予約受付や会計、問診といった業務を可能な限り効率化することを目指します。
例えば、次のようなものを開業時から積極的に導入します。
| オンライン予約システム | 24時間自動で予約を受け付けることで、スタッフの電話対応の負担を大幅に削減する |
| Web問診システム | 来院前に患者さんに問診を入力してもらうことで、受付での記入の手間を省き、待ち時間を短縮する |
| 自動精算機 | 会計業務をスムーズにして、限られたスペースの混雑緩和に繋げる |
DX化により、少数精鋭でもスタッフが患者さんへの対応に集中できる環境を整えることができます。
医療DXについては、以下の記事も参考にしてください。要件を満たせば医療DX推進体制整備加算が可能になります。
地域の病院・クリニックとのスムーズな連携体制を築く
ミニマム開業のクリニックは、地域の病院・クリニックとの連携が重要になってきます。
ミニマム開業のクリニックは、大規模な病院・クリニックのように自院ですべての医療を完結させることはできません。
医療機器やスタッフ数が限られているので、後述するように特定の領域に特化した専門外来を目指すケースが多いです。
そのため、自院で対応できない検査や治療が必要になった場合、患者さんをスムーズに紹介できる体制をあらかじめ構築しておくと良いでしょう。
地域の病院・クリニックと連携をすれば、自院でできないことでも、患者さんに対して切れ目のない医療を提供できます。
結果的に、「あそこに行けば、とりあえず大丈夫」という、地域の患者さんからの信頼獲得に結びつくでしょう。
ミニマム開業に向いている医院・クリニック5つの特徴

最後に、ミニマム開業に向いている医院・クリニックの特徴についてお伝えします。
次のコンセプトの医院・クリニックであれば、ミニマム開業の余地は十分あるでしょう。
高額・大型の医療機器や処置室が不要である
高額で大型の医療機器や処置室が不要な医院・クリニックは、ミニマム開業に向いています。
CTやMRIなど、数千万円単位の設備投資が必要な場合は、どうしても億単位の開業資金が必要となります。
医療機器や診療スペースを最小限に留めても診療に支障が出ないことが、ミニマム開業の前提となります。
具体的には、精神科、心療内科、皮膚科などが該当するケースが多いです。
診察やカウンセリングが中心である
先に述べた大型の医療機器不要にも繋がってくるのですが、診察やカウンセリングが中心のクリニックは、ミニマム開業に向いています。
具体的には、精神科や心療内科、禁煙外来などが該当します。
精神科や心療内科の開業については、以下の記事を参考にしてください。
自由診療を組み合わせやすい
ミニマム開業は来院患者数に上限があるので、少ない患者さんでも収益性を高める工夫が必要になります。
具体的には、自由診療メニューで患者さんに価値を提供できる医院・クリニックは、ミニマム開業でも医業収入の限界を突破しやすいでしょう。
ただし、自由診療には、最新の高額な医療機器が必要となることもあるので、慎重に検討が必要です。
訪問診療やオンライン診療と相性がいい
訪問診療やオンライン診療は、院内スペースの制約と関係ないので、ミニマム開業に向いています。
極論を言えば、クリニックをあくまで事務作業などを行う拠点と割り切り、診療の主軸を院外に置くことができれば、院内スペースを極限まで抑えられます。
訪問診療やオンライン診療については、以下の記事を参考にしてください。
特定の疾患や患者さんに特化した専門外来
リソースが限られたミニマム開業は、自院内で様々な疾患を扱うよりも、特定の疾患や患者さんに特化した専門外来の方が向いています。
敢えて診療領域を絞り込むことで、必要な医療機器やスペースは限定されますし、競合医院との差別化を図ることも可能です。
慎重に物件を選定する必要はありますが、地域住民にニーズがある場所であれば、ミニマム開業でも安定した集患が見込めます。
【まとめ】コンセプトが合えばミニマム開業を検討する余地はある
ミニマム開業について、メリット・デメリットや重要ポイント、向いている医院・クリニックについてお伝えしました。
ミニマム開業は、リソースがかなり絞られるものの、資金的なリスクが少ない、失敗しにくい開業方法の1つです。
リソースが限られることによる、デメリットもありますが、開業コンセプトが合えば十分検討の余地があるでしょう。
また、ミニマム開業まではいかなくても、無駄に開業資金をかける医院開業は避けるべきでしょう。
通常の医院・クリニックの開業資金や、資金を抑える方法などについては以下の記事を参考にしてください。
税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。
医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。
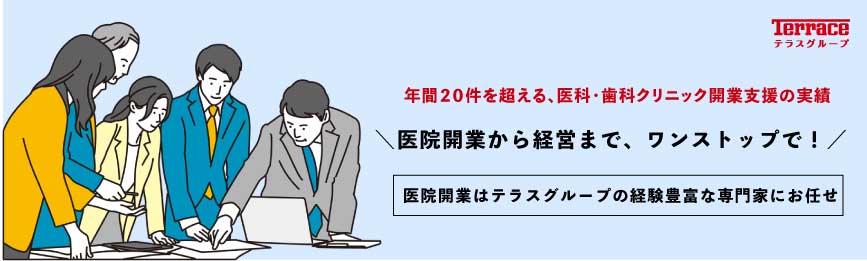
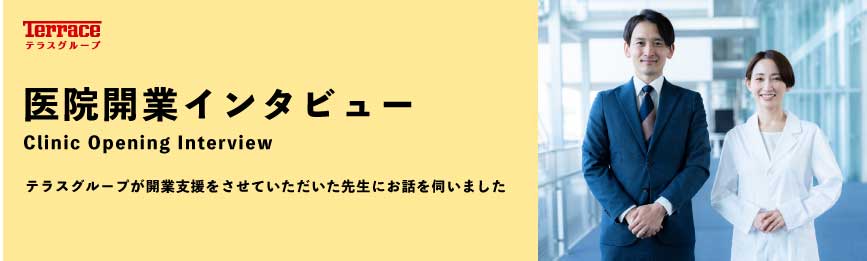


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。