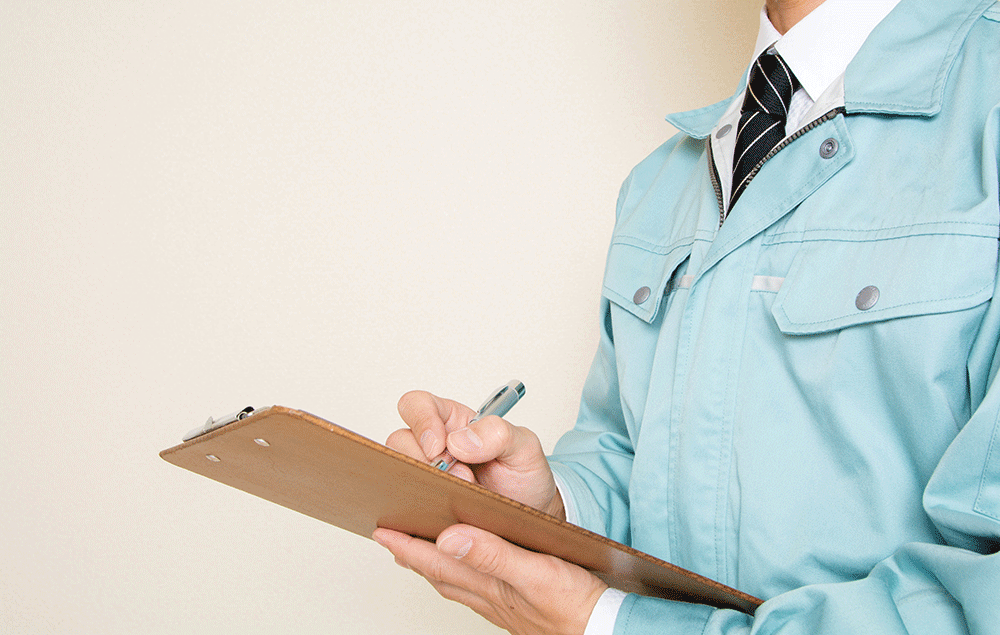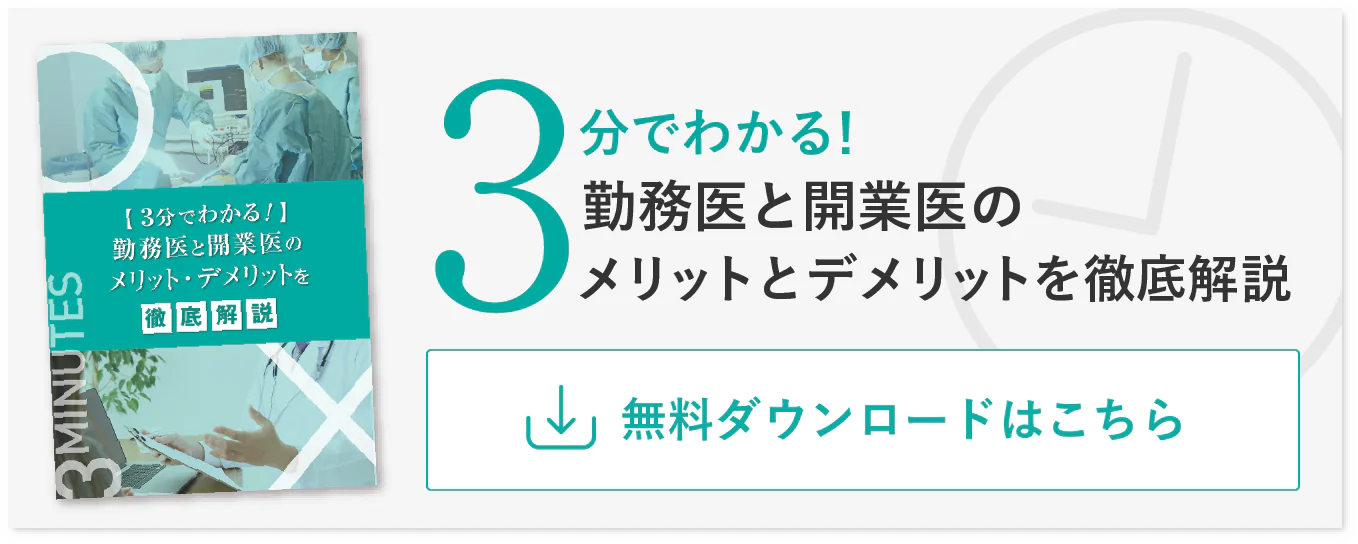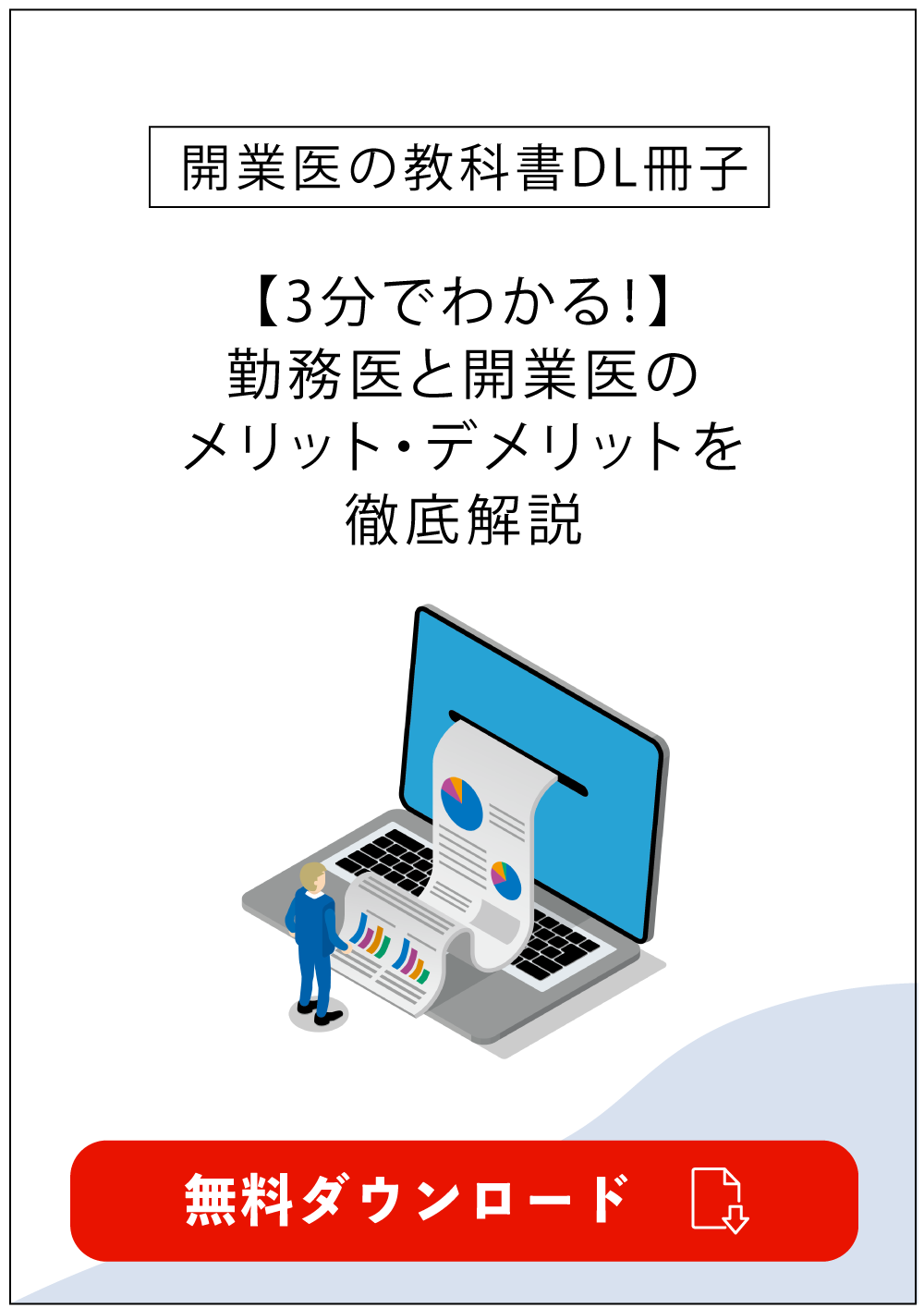クリニックを居抜き物件で開業する際の重要ポイントは?承継開業との違いやメリット・デメリットも詳細解説


クリニックを新規開業しようと考えている先生のなかには、居抜き物件を探している方も少なくありません。
たしかに、内装や医療機器が残ったままの居抜き物件は、すべて一から揃えないといけない通常の新規物件に比べて開業資金を抑えることが可能です。
ただ、居抜き開業は、承継開業と同様に、先生が開業するクリニックとマッチするかどうかがとても大切なポイントになります。
また、居抜き開業が、通常の新規開業や承継開業とどう違うのかを知っておくことも大切です。
そこで今回は、居抜き物件でのクリニック開業と他の開業方法の違い、居抜き開業のメリット・デメリットや重要ポイントをお伝えします。
居抜き開業を検討中の先生は最後までご覧ください。
居抜き開業、通常の新規開業、承継開業の違いは?

居抜き物件とは、前のクリニックが使用していた内装や医療機器を残したまま、売買もしくは賃貸借することです。
一方、通常の新規開業は、内装、医療機器、備品類がすべて撤去されたスケルトンの状態で契約した物件でクリニックを作り上げます。
スケルトン物件と違い居抜き物件の場合は残された内装や医療機器を使用できるので、開業資金を抑えることができます。
その点では、居抜き開業は承継開業(M&A)と似ていますが、クリニックを事業承継するわけではありません。
つまり、居抜き開業は、スタッフや患者さんのカルテ情報などを引き継ぐわけではなく、あくまで物理的な資産だけを引き継ぎます。
居抜き開業と、通常の新規開業、承継開業の違いをまとめると、次のようになります。
| 特徴 | 通常の新規開業 | 居抜き開業 | 承継開業 |
| 内装・医療機器 | なし | あり | |
| 患者さん引き継ぎ | なし | あり | |
| スタッフ引き継ぎ | なし | あり | |
| 営業権(のれん代) | なし | あり | |
| 融資 | 事業計画次第 | 有利(実績あり) | |
| 初期費用 | 高 | 中 | 低~中 |
| 開業準備期間 | 1年程度 | 3~6ヶ月程度 | |
| 開業準備で行うこと | 物件選定、資金調達、内外装や医療機器の選定、スタッフ採用、広告・集患対策、開業の行政手続き等 | M&A交渉、資金調達、承継元の引き継ぎ等 | |
| 設計自由度 | 高 | 中 | 低 |
| 集患難易度 | 高 | 中 | 低 |
| 行政手続きの手間 | 高 | 低 | |
| 開業時のリスク | 高額な開業資金、長期の準備期間、集患難易度、スタッフ採用難易度等 | 設備の老朽化、前院の悪評、医療機器やレイアウトの制約、スタッフ採用難易度等 | 設備の老朽化、前院の悪評やトラブル、医療機器やレイアウトの制約、既存スタッフとの不和、診療方針の制約、簿外債務等 |
このように、居抜き開業の特徴は、通常の新規開業と承継開業の中間にあるイメージです。
各々の開業方法の特徴について押さえておくようにしましょう。
なお、承継開業についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
居抜き物件でクリニックを開業する4つのメリット

上記のことを踏まえて、居抜き物件でクリニックを開業する主なメリットは次の通りです。
何と言っても、開業資金を大幅に削減できる点と、開業準備期間を押さえることができる点は大きいと言えます。
開業資金を大幅に削減できる
居抜き開業が魅力的な大きな理由が、開業資金を大幅に削減できることです。
クリニックの開業資金は、診療科目や規模によって変わりますが、5,000万円から1億円ほどかかります。
その中で、内装工事費や医療機器の導入費用は大きな割合を占めますが、居抜きの場合はそれがありません。
しかし、居抜き物件の場合は、後述するように造作譲渡料が発生することがある点は注意してください。
造作譲渡料を支払った方が良い場合と、そうでない場合があります。
開業までの期間を短縮できる
新規開業する先生にとって、開業期間を短縮できるのも、居抜き開業の大きなメリットです。
通常のスケルトン物件での新規開業では、開業準備に1年程度かかることがあります。
しかし、居抜き物件では内装工事や医療機器の導入にかかる期間を大幅に短縮できます。
居抜き物件の場合、開業準備期間は3~6ヶ月程度が目安になりますが、物件によっては、もっと短くなることがあります。
そのため、開業準備期間中の空家賃などの経費を削減し、早期に収益化が可能になります。
立地の優位性があり集患しやすい
居抜き開業は、もともとクリニックのあった場所に開業することになるので、もともと立地優位性が高く集患しやすい傾向があります。
もともと、クリニックに適した好立地物件は競争が激しく、確保が難しい実情があります。
一方、居抜き物件は、もともと同じ場所にクリニックがあったということですので、地域住民には「あそこはクリニックの場所だ」と認知されています。
また、もともとクリニックのあった場所に再び新規のクリニックができることで、転院した患者さんが戻ることも考えられます。
そのため、開業時の集患で有利に働き、経営が軌道に乗りやすくなることがあります。
ただし、前院の評判が悪かった場合は、逆に集患に不利に働くリスクがあるので注意しましょう。
スムーズに行政手続きを進めやすい
保健所にクリニックの開設届を提出した後、保健所職員による立入検査が行われます。
通常の新規開業の場合、何らかの細かい問題が見つかって職員から指摘を受け、開業までに対応しなければいけないことがあります。
しかし、居抜き物件は、過去に立入検査をクリアしているため、レイアウトに大きな変更がない限り、立入検査をスムーズにパスできる傾向があります。
このように、開業前からクリニックとして運営していた実績があると、行政手続きがスムーズになることがあります。
なお、保健所の立入検査については、以下の記事をご覧ください。
居抜き物件でクリニックを開業する3つのデメリット

次に、居抜き物件でクリニックを開業するデメリットは次の通りです。
承継開業のデメリットにも似たところがありますが、以下の点は十分注意してください。
レイアウトの制約により動線が悪くなることがある
居抜き物件の場合、すでに内装やレイアウト、医療機器が決まっているため、設計の自由度が低くなります。
既存のレイアウトが、先生の診療科目や治療方針に最適化されているとは限りません。
患者さんやスタッフの動線が悪く、作業効率や患者満足度に影響する可能性があります。 レイアウトを大幅に変更するなら、結局修繕費用が発生することになり、開業資金削減という居抜きのメリットが失われるかもしれません。
設備・医療機器の老朽化と隠れたコスト
居抜き開業や承継開業で引き継いだ医療機器や設備は、すでに老朽化が進んでいる可能性があります。
特に耐用期間を過ぎた機器は、故障リスクが高くなっており、何らかの不具合が生じる可能性があるので、修理・点検が欠かせません。
そうなると、高額な修理費や買い替え費用が発生し、結局新規開業した場合の開業資金とあまり変わらなかったというケースもあります。
また、不要になった古い医療機器の廃棄にもコストがかかることを忘れてはなりません。
やはり、開業資金削減という居抜きのメリットが失われる可能性があります。
前院の悪評の影響を受ける可能性がある
居抜き開業は、認知されやすいといった立地の優位性がある一方で、前院の評判が悪い場合は逆効果になる可能性があります。
例えば、何かしら医療トラブルがあったり、前の院長やスタッフ対応が悪かったりした場合、地域住民にネガティブなイメージが付いています。
もちろん、新規開業するクリニックには関係のない話ですが、前院の悪評を引きずり、集患に苦労する可能性があります。
居抜き開業で失敗しないための5つの重要ポイント

これまでのことを踏まえて、居抜き物件でクリニックを開業する際、失敗しないための重要ポイントについてお伝えします。
居抜き物件を探す際は、次の点は確認するようにしましょう。
造作譲渡料がかかるかどうかを確認する
居抜き物件では、造作譲渡料がかかる場合とかからない場合があります。
造作譲渡料とは、前の借主(前院の院長)が店舗内に設置した内装、医療機器、備品など物理的資産(造作)の対価について支払う金額のことです。
造作譲渡料は、物件のオーナーではなく、あくまで前の借主に対して支払います。
造作譲渡料がかかる場合とかからない場合の特徴、メリット・デメリット、向き不向きをまとめると次のようになります。
| 造作譲渡料がかかる場合 | 造作譲渡料がかからない場合 | |
| 残置物の権利関係 | 所有権 | 使用権 |
| メリット | ・状態の良い医療機器を使える可能性が高い ・開業準備がスムーズに進む ・退去時に内装や医療機器を売却できる可能性がある | ・開業資金を抑えられる |
| デメリット | ・開業資金がかさむ ・市場価格と造作譲渡料が乖離している可能性がある ・退去時に売却できなければ廃棄費用が発生する可能性がある | ・内装や医療機器の老朽化が激しい可能性がある ・内装や医療機器を廃棄する際に費用がかかる ・退去時に原状回復義務が生じる可能性がある |
| 向いている先生 | 診療科目や治療方針が前院と一致して、引き継ぐ内装、レイアウト、医療機器をそのまま使いたい先生 | 建物の修繕、医療機器の買い替えを前提として、場所だけは確保したい先生 |
このように、造作譲渡料がかからないからといって、魅力的とは限らない点に注意が必要です。
造作譲渡料がかかっても、その金額を上回る価値のある内装や医療機器が手に入るなら、結果的に費用対効果は高くなります。
逆に造作譲渡料がかからなくても、高額な廃棄費用がかかればコストが大きくなります。
残置物の資産価値を客観的に査定してもらいながら、慎重に検討するようにしましょう。
診療科目や治療方針がマッチするか慎重に見極める
居抜き開業では、承継開業と違って引き継ぐのは内装や医療機器だけですが、それでも診療科目や治療方針がマッチしているかどうかは重要です。
診療科目や治療方針に合わない場合は、修繕、医療機器の買い替えが必要になるので、結局廃棄コストがかかるだけで居抜きのメリットを享受できません。
同じ診療科目であっても、居抜き物件が適切とは限りません。
内科であれば、一般的な保険診療を中心に行うのか、内視鏡検査などの専門的な検査に力を入れるのかで、内装、レイアウト、医療機器は変わります。
また、前院とまったく違うコンセプトのクリニックになる場合は、立地の優位性による集患効果も低くなります。
例えば、前院が内科だった場所に歯科医院を開業しても、当然前院とは患者さんの属性が違います。
認知に時間がかかりますし、前院の患者さんが戻ってくることも期待できないでしょう。 居抜き開業のメリットを享受できるかどうかは、診療科目や治療方針がマッチングしているかどうかで変わってきます。
内装・設備の状況を専門家と一緒に確認する
居抜き開業では、内装や医療設備が老朽化が進んでいる可能性があるので、専門家と一緒に確認するようにしましょう。
例えば内装であれば、壁や天井などの見た目だけでなく、給排水設備、空調設備、電気設備の状態の確認が必要です。
また、老朽化が進んでいるかどうかだけでなく、これらの設備の容量が、ご自身のクリニックに適しているかどうかも検討することが大切です。
医療機器については、動作確認だけでなく、耐用期間や寿命、メンテナンスの履歴、メーカーの保守サポートの可否などを慎重に確認します。
もし、修繕や医療機器の買い替えが必要な場合は、概算費用の見積もりをしてください。
先生にとって、その居抜き物件が妥当かどうかを判断する材料にもなりますし、前院との造作譲渡料の交渉の根拠にもなります。
居抜き物件の立地条件や周辺環境は問題ないか確認する
居抜き物件であっても、立地条件や周辺環境は問題ないかを、診療圏調査などでしっかり確認しましょう。
「以前にクリニックがあった場所なら、立地は問題ないだろう」と判断するのは早計です。
特に、前院が経営悪化を理由に閉院した場合は注意が必要です。
経営悪化の原因が、立地的に不利だったり、周辺環境の変化によるものだったりしている可能性があるからです。
現時点の立地条件や周辺環境を判断するためにも、診療圏調査は行った方が良いでしょう。
この点は、承継開業でも同じことが言えます。
前院の評判を確認しておく
居抜き物件の場合、前院の評判が開業時の集患や患者満足度に影響することがあるので、なるべく確認しておきましょう。
前院の評判が悪かった場合は、どんなに質の高い医療を提供して、接遇態度が良かったとしても、マイナスイメージを払拭するには時間がかかります。
また、前院の評判が良かった場合も、「前の先生と違うなあ」「以前はこうだった」と比較されやすくなります。
この場合は、前院長の功績に敬意を払いつつも、ご自身の診療方針を丁寧に伝えて、新たな信頼関係を築いていく必要があるでしょう。
前院の評判については、Googleの口コミやポータルサイトのレビューを見ておくのも良いですが、閉院していれば確認できない場合があります。
その場合は、地域の医師会や医療関係者など、地域のクリニック情報に精通している人に聞いてみるのも良いでしょう。
【まとめ】居抜き開業の重要ポイントを押さえておく
以上、居抜き開業の特徴やメリット・デメリットや失敗しないための重要ポイントをお伝えしました。
居抜き開業では、内装や医療機器を確認しておくことと同時に、前院の評判や周辺環境の変化も確かめておく必要があります。
そして、立地条件は本当に適切か、内装や医療機器はそのまま使用できるかを慎重に検討しましょう。
税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。
医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。
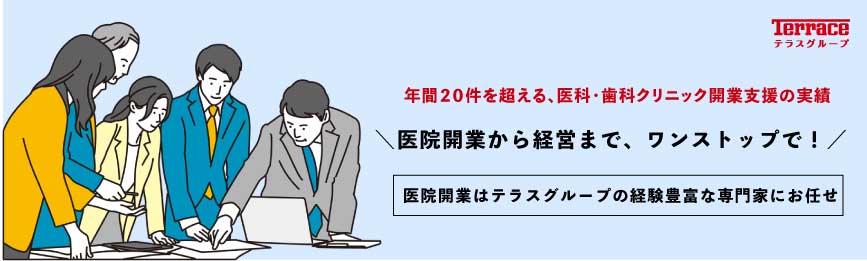
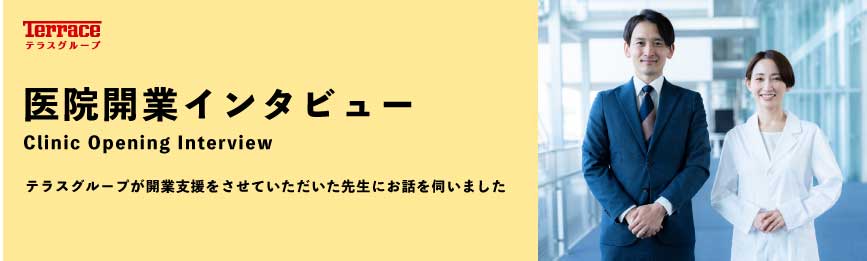


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。