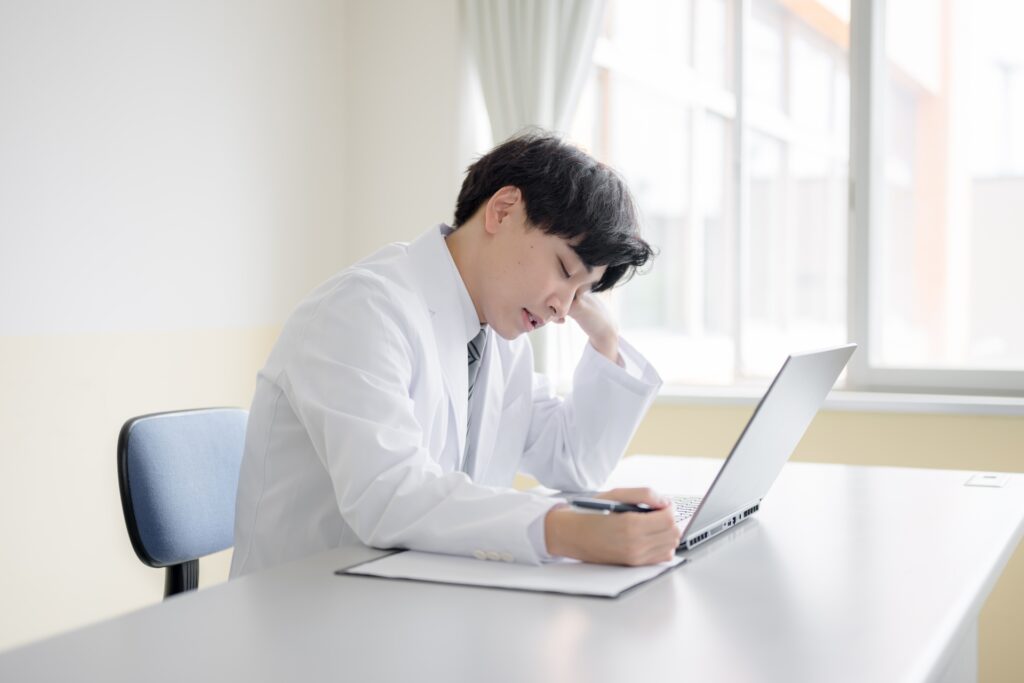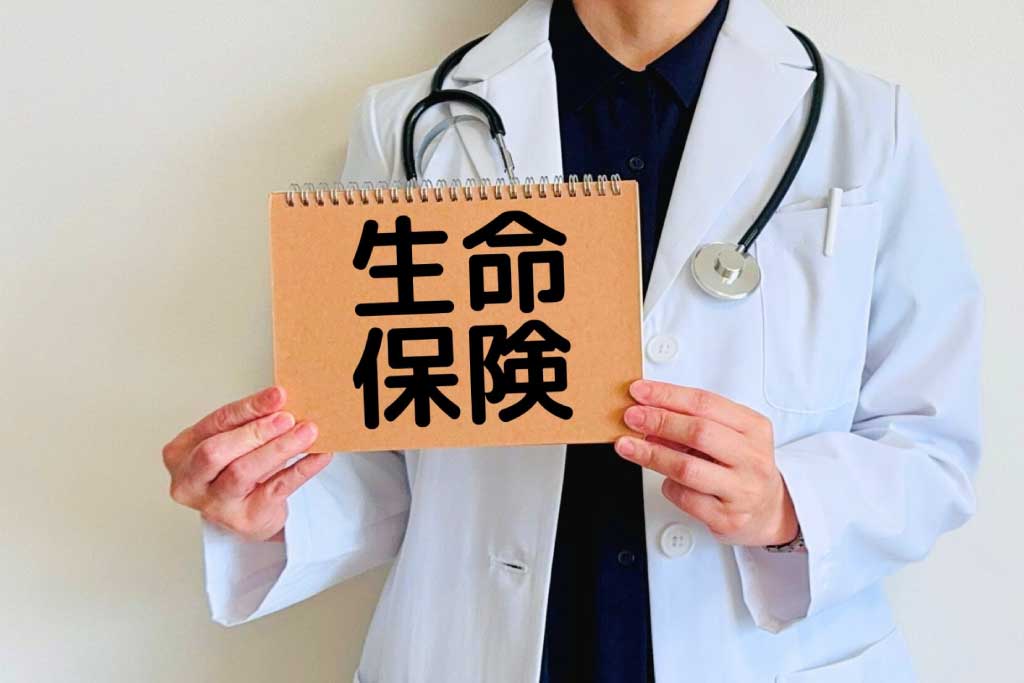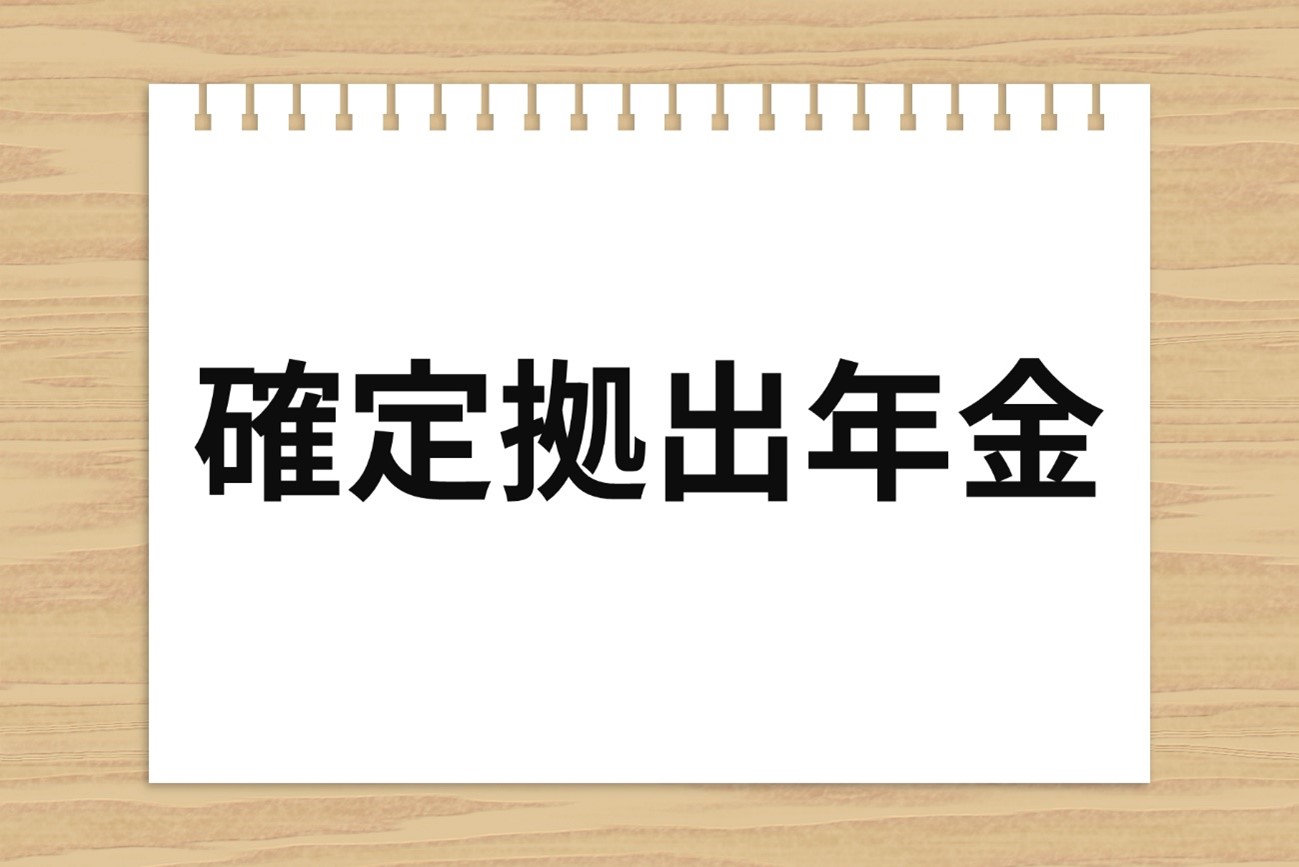クリニックで退職金制度は必要?制度の種類や計算方法を詳細解説


「スタッフが辞めた際の退職金制度は必要か?」
「スタッフの退職金はどれくらい支給すれば良いか?」
とお悩みの開業医の先生は少なくありません。
実際、退職金制度にはメリット・デメリットがあるので、特にこれから開業する先生は、導入すべきかどうか迷うのも無理はないでしょう。
そこで、今回は、医院・クリニックに特化した社会保険労務士が、医院・クリニックの退職金についてお伝えします。
退職金制度は必須ではないが導入している医院・クリニックは多い

医院・クリニックの退職金については、労働基準法などで規定があるわけではなく、必ず用意しなければいけないわけではありません。
退職金制度の導入の有無については、あくまで医院・クリニックの判断に委ねられています。
ただ、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 」によると、医療・福祉業界の退職金制度を導入している割合は75.5%にのぼります。
これは、全産業の平均(74.9%)と、ほぼ同程度です。
小規模の医院・クリニックだけでなく、大病院も含まれているデータということを差し引いても、決して低い数字ではありません。
これは、後述するように退職金制度はデメリットだけでなく、メリットも大きいためです。
なお、退職金制度を導入した場合は、就業規則や労働条件通知書で必ず記載が必要となり、定めに従って支払う義務が生じます。
退職金制度については、スタッフとのトラブルを避けるためにも、必ず書面で明確にルール化しておかないといけません。
医院・クリニックが退職金制度を導入する4つのメリット

先ほどもお伝えした通り、退職金制度を導入している医院・クリニックは決して少なくありません。
特に、スタッフを積極的に採用したり、定着率を上げたりしたい場合は、退職金制度を導入するメリットは大きくなります。
人材募集時のアピールポイントになる
退職金制度を設けている医院・クリニックは、長期的に安心して働ける職場と認識されるため、人材募集時のアピールポイントになります。
逆に退職金制度を設けていない場合は、医療スタッフの採用難が続いている今の時代にはかなり不利に働くことが考えられます。
給与や福利厚生のみを目的とするスタッフの採用は避けるべきですが、ここ数年は水準が上がっていることは事実です。
退職金制度だけでなく、給与や福利厚生については、最寄りの社会保険労務士と相談して十分検討した方が良いでしょう。
スタッフの定着率が上がる
退職金制度を導入することで、人材募集で有利になるだけでなく、スタッフの定着率の増加にも繋がります。
退職金の計算方法には様々ありますが、多くの場合は勤続年数が長くなるほど支給額が多くなる計算式になっています。
そのため、スタッフには末永く働こうという気持ちが芽生えやすくなります。
ただ、スタッフの定着率を上げるには、退職金制度だけでなく、人間関係やマネジメントも大きく関係してくることは忘れてはいけません。
退職金には社会保険がかからない
給与や賞与と違って、退職金には社会保険がかかりません。
給与や賞与として支払う額を、一部退職金として積み立てることで人件費の負担が軽減されます。
円満に早期退職を促すことができる
退職金制度では、スタッフの定着率を図ることができる一方で、早期退職を円満に促せる場合もあります。
例えば、問題スタッフの退職勧奨をする際、退職金を用意しておくことで円満な退職へと導き、将来的なトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
経営状況が厳しく、どうしても早期退職を促さないといけなくなった場合でも同様です。
これまで献身的に働いてくれたスタッフを労う意味でも、退職金制度は有効です。
医院・クリニックが退職金制度を導入する3つのデメリット

医院・クリニックが退職金制度を導入するデメリットについてお伝えします。
退職金制度を導入する際は、次の点は注意しましょう。
コストが発生する
言うまでもなく、退職金制度がなければ支払う必要のないお金を支給することになるので、+αのコストになります。
スタッフを採用した時点で、将来的に大きなコストがかかる可能性が発生することになります。
経営状況に関わらず支払い義務が発生する
退職金制度を導入した場合、例え経営状況が厳しいときであっても、退職金を支払う義務が発生します。
賞与と違って、退職金は業績が良くても悪くても関係なく、決まった支給をしなければいけません。
経営が悪化しているタイミングで、ベテランスタッフの退職が重なると資金繰りを圧迫することになりかねません。
このようなリスクを避けるために、退職金制度の種類や積み立て方を知っておくことが大切です。
一度退職金制度を作ると廃止や減額が困難になる
一度導入した退職金制度を廃止したり、支給額を減らしたりすることは労働条件の不利益変更と見なされます。
退職金制度の廃止や減額を強行すると、スタッフのモチベーションが低下するどころか、大量離職やスタッフ間トラブルの元になります。
また、退職金制度に限らず、スタッフにとって就業規則の不利益な変更をする場合は、必ずスタッフの合意が必要となります。
【労働契約法第9条】
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。【労働契約法第10条】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
スタッフの合意がなく、勝手な判断で不利益変更することは絶対に避けてください。
退職金制度は、後から不利益な変更が必要にならないように、無理のない範囲で導入すると良いでしょう。
退職金制度の主な3つの種類
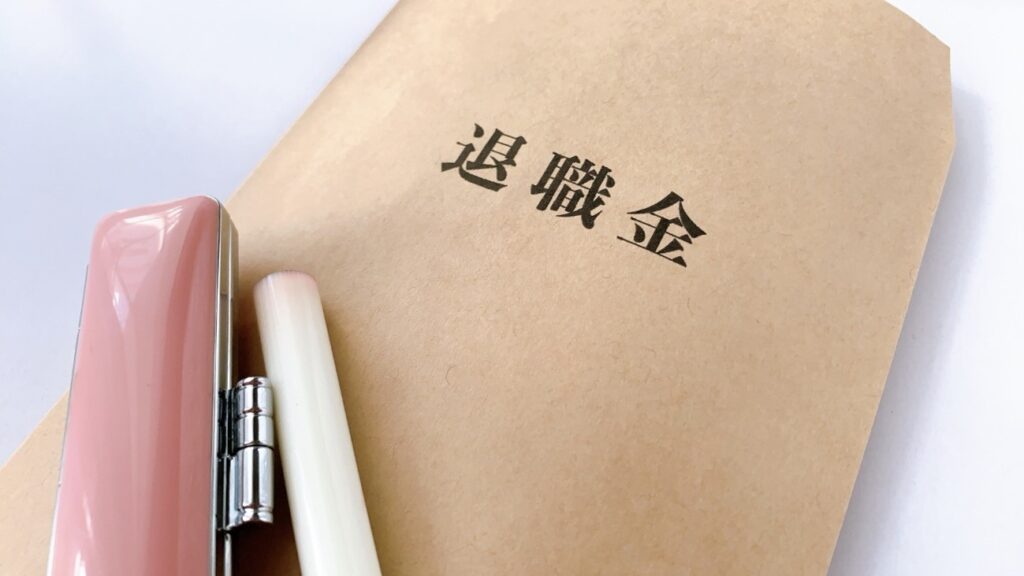
退職金制度については、大きく分けると、退職一時金制度、企業年金制度、前払い制度の3種類に分けることができます。
| 特徴 | 退職一時金制度 | 企業年金制度 | 前払い制度 | |
| 企業型DB | 企業型DC | |||
| 負担者 | クリニック | クリニック | スタッフ | なし |
| 医院側の税務処理 | 支払時もしくは掛金拠出時に損金算入 | 掛金拠出時に損金算入 | 給与として支払時に損金算入 | |
| スタッフの税務処理 | 退職所得控除 | 退職所得控除か公的年金等控除 | 給与所得控除 | |
| 資金繰り | 退職時に大きな支出 | 毎月一定の掛金支出(追加拠出リスクあり) | 毎月一定の掛金支出 | 毎月の給与支払いが増加 |
| 管理の手間 | 低~中 | 中~高 | 低 | |
| スタッフの定着効果 | 高 | 中~高 | 低 | |
上の表のように、それぞれ特徴が異なるので、最寄りの社会保険労務士と相談して、自院に合う方法を選ぶようにしてください。
退職一時金制度
退職金制度で最も多く採用されているのが、退職一時金制度です。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 」によると、医療・福祉業界で退職金制度を導入している職場の86.9%は退職一時金制度を採用しています。
退職一時金制度は、具体的な決まりはありません。
一般的には勤続年数や職場の功績、退職時点での役職や階級、クリニックの貢献度などによって退職金額が決定しますが、計算方法は後述するように様々です。
下記の企業年金制度や前払い制度と違って、退職時に大きな支出が発生するので、キャッシュフローには注意する必要があります。
そのため、内部留保だけでなく、中小企業退職金共済や生命保険などによる積み立ても検討の余地があります。
| 中小企業退職金共済 | 国が用意している退職金制度で、加入すると国からの助成金を受けられる。個人医院・クリニックであれば全額経費、医療法人の場合は全額損金が可能。スタッフが1年未満で退職した場合は掛金が戻ってこない点は注意が必要。 |
| 生命保険 | 契約によっては、保険料の一部を損金できるメリットがあるが、返戻率が高い保険商品は掛金が高額になる傾向がある。 |
中小企業退職金共済(中退共)については、以下のサイトで最新情報を確認するようにしてください。
生命保険に関しては、院長先生や役員クラス向きの保険には、長期平準定期保険、スタッフ向きの保険には養老保険タイプなどがあります。
2019年の税制改正以降、解約返戻率が50%を超える法人保険に対しては、損金算入割合が大幅に減っている点に注意してください。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
企業年金制度
企業型確定給付年金(以降、企業型DB)や企業型確定拠出年金(以降、企業型DC)を利用した、企業年金制度を導入する方法もあります。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 」によれば、医療・福祉業界では、まだ1.7%しか導入されておらず、まだ浸透しているとは言えません。
しかし、金融業・保険業では27.5%、情報通信業では17.7%が導入している方法で、今後医療・福祉業界でも導入例が増えることは考えられます。
実際、退職時に大きな支出になることはなく、毎月一定額を拠出することになり、キャッシュフローが安定しやすいメリットがあります。
企業型DBは、資産運用の成績によって受給額が変動することはなく、加入期間や在職中の給与などに応じて受給額が決まります。
スタッフにとっては退職時の給付額は保証されますが、運用結果が悪ければ、医院・クリニック側が不足分の追加拠出をしないといけません。
一方、企業型DCは、資産運用の成績によって受給額が変動するので、どの金融商品を選ぶかで退職金額は変わってきます。
企業年金制度を活用することで、スタッフは退職金を一括で受け取ることもできれば、定期的に給付を受け取ることもできます。
一方で、iDeCoと同様に60歳になるまで引き出しができない点にデメリットを感じるスタッフも少なくありません。
ただ、今はiDeCoや新NISAなど、資産運用に興味を示すスタッフが増えている傾向にあるので、十分検討の余地はあります。
特に、選択制企業型DCは、スタッフが自分で加入するかどうか決められるので、理解は得やすいでしょう。
企業型DCについては、以下の記事を参考にしてください。
前払い制度
退職金に相当する額を、退職時ではなく毎月の給与や賞与に分散して上乗せするのが前払い制度です。
医院・クリニックにとっては、退職時の多額の現金流出を抑えることができて、キャッシュフローが安定しやすいメリットがあります。
実質的に退職金はなくなりますが、その分給与・賞与がプラスされることで、求職者の印象も悪くなりません。
しかし、上乗せ分も給与と見なされることで、社会保険料の負担が大きくなってしまいます。
また、退職金という、将来のまとまった給付がなくなるので、スタッフの離職率が高まる可能性も無視できません。
つまり、前払い制度は退職金制度のデメリットはなくすことはできますが、メリットを享受することもできなくなります。
スタッフにとっても、退職所得控除のような税制上の優遇を受けることができなくなります。
他の退職金制度とメリット・デメリットが違う点に注意して、慎重に検討しましょう。
退職一時金制度の退職金4つの計算方法
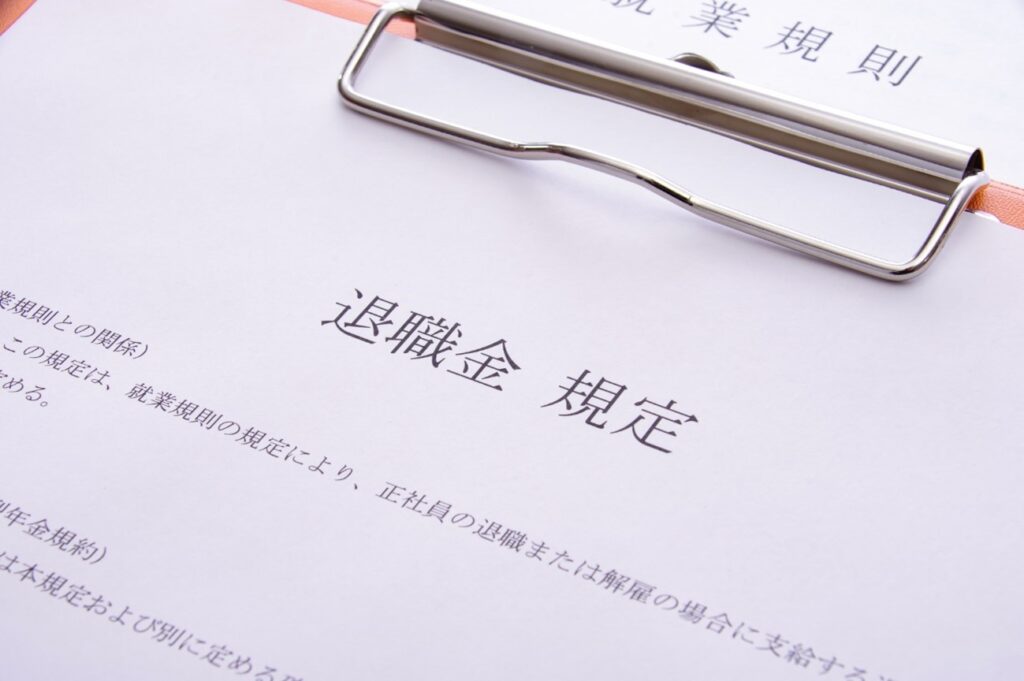
上記の退職金制度のうち、最も利用される退職一時金制度については、次のように4つの退職金の計算方法があります。
法的な計算方法のルールはなく、あくまで医院・クリニックの方針に委ねられますが、就業規則では計算方法を明記しなければいけません。
【労働基準法第89条】
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(中略)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
退職前に休職するスタッフも少なくないですが、休職期間を勤続年数に含めるかどうかも忘れずに明記しましょう。
定額制
計算式:固定額×勤続年数×退職事由係数
※退職事由は自己都合、医院都合のいずれか(以下同様)
定額制は、あらかじめ定められた固定額に勤続年数を乗じて退職金を計算する方法で、退職時の基本給や役職、貢献度は反映されません。
勤続年数だけが変数となる最もシンプルな計算方法で、支給額の予測が容易になり、医院・クリニック側の資金計画が立てやすくなります。
しかし、スタッフの基本給や役職が反映されないので、医院・クリニックへの貢献度が高いスタッフは不満を抱く可能性があります。
基本給連動制
計算式:退職時の基本給×勤続年数に応じた支給率×退職事由係数
基本給連動制は、退職時の基本給をベースにして、勤続年数に応じた支給率を乗じて退職金を計算する方法です。
支給率については、例えば5年未満は1.0、5~10年は3.0、11~15年未満は5.0といったものです。
勤続年数だけでなく、昇給も反映されるので、定額制よりスタッフ間で不公平感は生まれにくくなるでしょう。
一方で、退職時の給与水準によって支給額が大きく変動するため、医院・クリニック側の将来的な負担額の予測が難しい場合があります。
別テーブル制
計算式:役職・等級に応じた基礎金額×勤続年数係数に応じた支給率×退職事由別係数
別テーブル制は、上記の基本給連動制と計算式が似ていますが、基本給ではなく、役職や等級に応じた基礎金額で退職金を計算します。
役職・等級をベースとすることで、より医院・クリニックへの貢献度を重視した計算方法と言えます。
一方で、役職に就いていないスタッフから不満が生まれやすい計算方法でもあります。
基本給連動制にするか、別テーブル制にするかは、クリニックの人員体制によっても適性が変わってきます。
ポイント制
計算式:累計ポイント×ポイント単価×退職事由係数
ポイント制は、勤続年数、基本給、役職、貢献度などをポイント化し、その累計に基づいて退職金を計算する方法です。
どの項目に、どれだけのポイントがつくかは、医院・クリニックによって異なります。
勤続年数(勤続ポイント)、役職(役職ポイント)、個人の業績(貢献度ポイント)など、クリニックが重視する要素を柔軟に評価に組み込むことが可能です。
最も公平性が高い退職金制度で、近年採用例が多いですが、管理や将来の負担額の予測が複雑になる点は注意が必要です。
パート・アルバイトにも退職金を支給する必要はあるか?
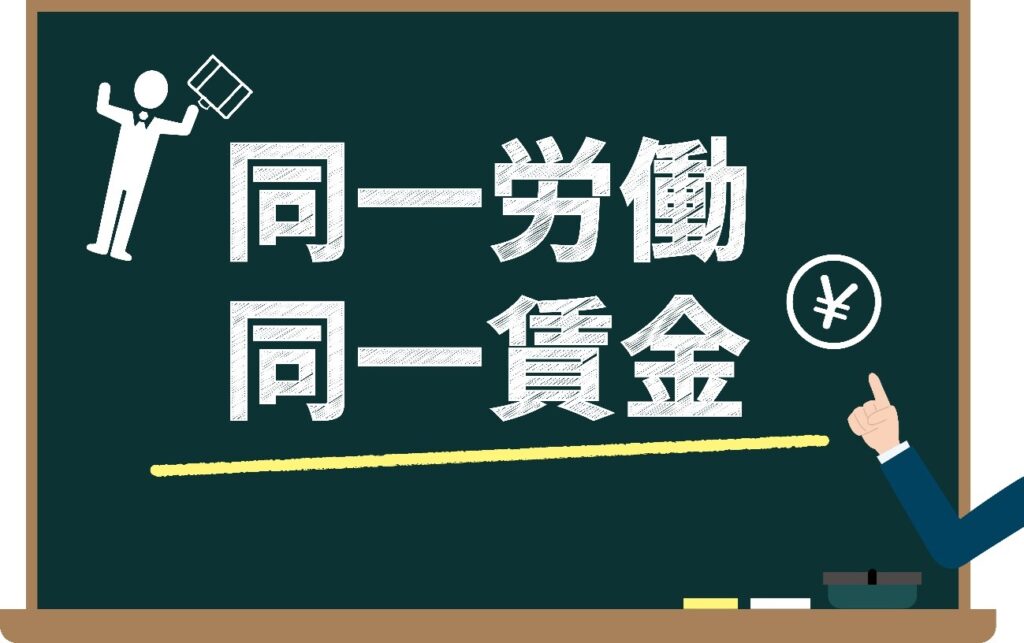
よく「非常勤のスタッフ(パート・アルバイト)に退職金を支払うべきか?」と聞かれます。
常勤スタッフと同様、パート・アルバイトにも退職金を支払う法的な義務はありません。
しかし、退職金制度を導入している場合は、「同一労働同一賃金」の考え方に基づき、パート・アルバイトにも退職金を支払う必要があると考えられます。
パートタイム・有期雇用労働法により、常勤と非常勤で、不合理な待遇差をなくすことが禁止されているためです。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
【まとめ】自院に合った退職金制度を導入する
クリニックの退職金制度について、メリット・デメリットや主な種類、計算方法をお伝えしました。
退職金については、法的な支払い義務はありませんが、医療・福祉業界の75.5%は退職金制度を導入しているのが実態です。
人材採用やスタッフの定着率という点では有利になりますし、社会保険料の削減というメリットもあります。
退職金制度を一度導入すると、不利益変更が困難になるので、無理のないように制度設計することが大切です。
最寄りの社会保険労務士や税理士に相談して、自院に合った退職金制度を導入するようにしてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
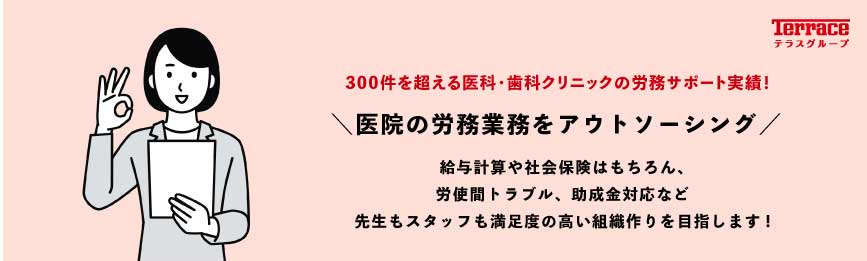
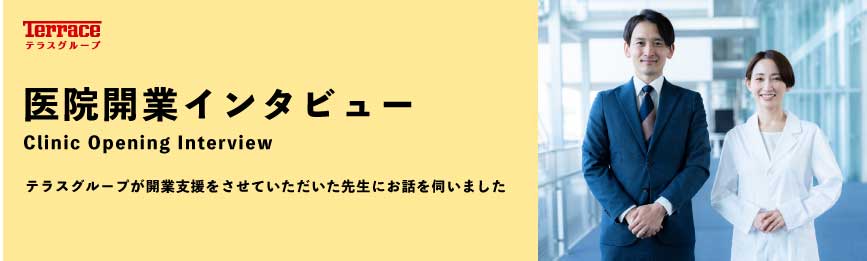
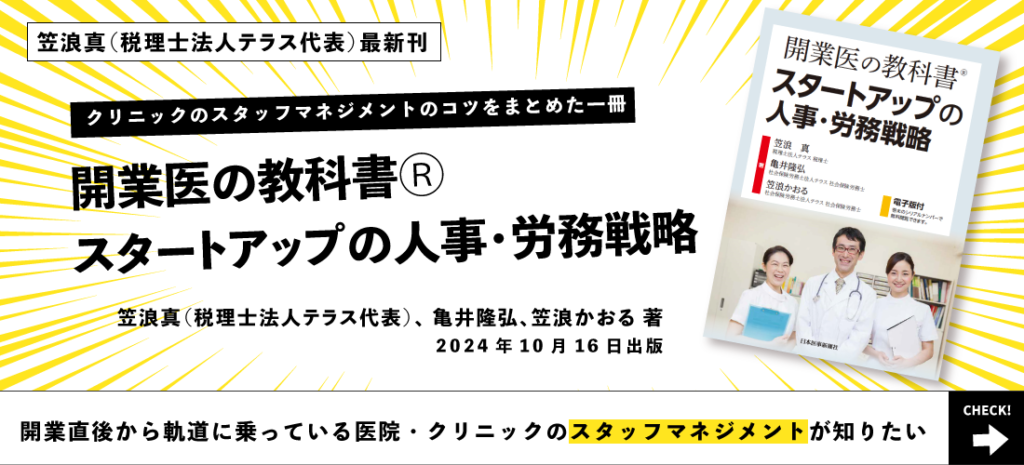


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。