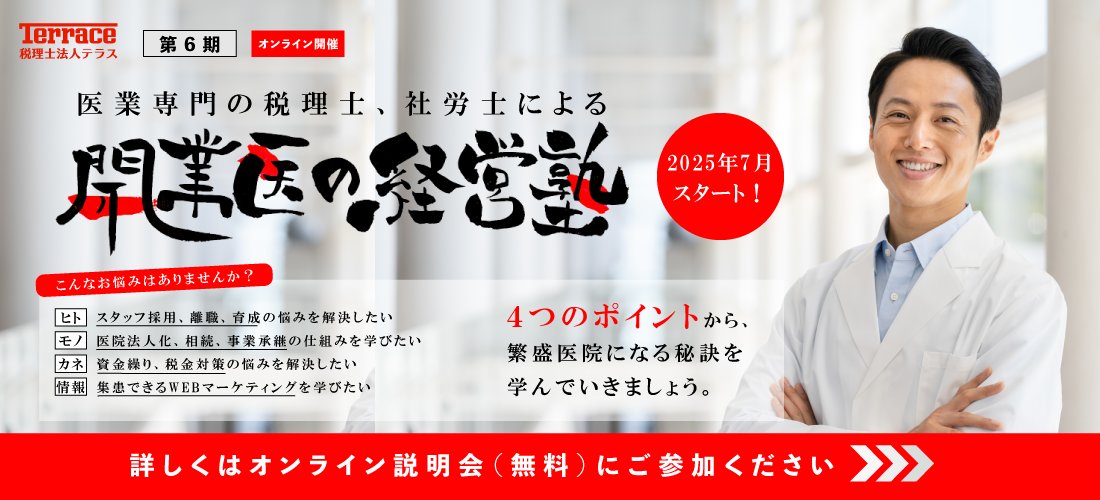医療法人ができない事業とは?業務範囲の注意点などを詳細解説


医療法人は、病院やクリニック、介護老人保健施設、介護医療院を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される非営利性の高い法人です。
そのため、医療法人の業務範囲には制限があり、医療法上できない事業があります。
違反した場合は、収益事業を中止するように行政指導を受けることがあり、場合によっては、本来業務の停止や役員の解任に至ることもあります(医療法第63条、第64条)。
そこで、本記事では、医療法人の業務範囲、一般の社団医療法人が禁止されている事業例(収益業務)、MS法人の活用についてお伝えします。
医療法人が行うことが出来る業務の4つの分類

医療法人が行う業務は、医療法によって大きく4つに分類されています。
・本来業務
・附帯業務
・付随業務
・収益業務
このうち、収益業務については、原則として社会医療法人のみが行える業務です。
一般の社団医療法人が行うことが出来る業務は、本来業務、附帯業務、付随業務のみになります。
本来業務
本来業務とは、医療法人の設立目的そのものである、中核となる事業を指します。
医療法第39条で定められており、定款への記載が必須で、都道府県知事の認可が必要です。
【医療法第39条】
1.病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2.前項の規定による法人は、医療法人と称する。
具体的には、以下の施設の開設・運営が該当します。
・病院
・医師・歯科医師が常時勤務する診療所
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的として設立される法人です。(医療法第39条)
※厚生労働省「医療法人の業務範囲」より抜粋
他の附帯業務と付随業務は、すべてこの本来業務を支えるために存在するというのが基本的な考え方になります。
附帯業務
附帯業務は、本来業務に支障のない範囲で行うことができる、医療・福祉に関連した事業です。
本来業務だけでは対応できない地域のニーズに応える重要な役割も担い、医療法第42条で定められています。
【医療法第42条】
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。一 医療関係者の養成又は再教育
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
附帯業務を行うには、本来業務と同様に定款に事業内容を記載したうえで、都道府県知事の認可を受けなければいけません。
代表的な附帯業務には以下のようなものがあります。
・看護師やPT、ST、OTなど医療関係者の養成・再教育(専門学校の運営など)
・医学・歯学に関する研究所の設置
・疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設
・疾病予防のために温泉を利用させる施設
・保健衛生業務(薬局、訪問看護ステーション、介護福祉士養成施設、助産所、歯科技工所など)
・海外における医療施設の運営に関する業務
・有料老人ホームの経営
※厚生労働省「医療法人の業務範囲」を元に作成
高齢者人口の増加に伴い、国が地域包括ケアシステムを推進している流れで、医療法人に求められる役割も、単に日々の診療だけに留まりません。
今後は、患者さんの生活を地域で支えるための在宅医療や介護サービス、予防医学といった分野が重要になってくると考えられています。
こういった分野の多くが、医療法人の附帯業務として展開可能になります。
例えば、訪問看護ステーションや有料老人ホームの運営、疾病予防のための運動施設の設置などは附帯業務の範囲内になります。
なお、医療法人が附帯業務を委託することや、本来業務を行わずに附帯業務のみを行うことはできません。
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること
※厚生労働省「医療法人の業務範囲」より抜粋
付随業務
付随業務は、本来業務に付随して行われる、患者さんへの利便性向上などを目的とした事業です。
附帯業務とは異なり、定款の変更や行政の認可は必要ありません。
具体的に、付随業務には次のようなものがあります。
・院内売店の運営
・敷地内駐車場の運営
・患者搬送サービス
・医療用器具の販売
※厚生労働省「医療法人の業務範囲」を元に作成
あくまで本来業務の一環と見なされる、比較的小規模なものに限られます。
収益業務(社会医療法人の認定を受けた場合のみ)
収益業務とは、医療とは直接関係のない、営利を目的とした事業全般を指します。
医療法人の非営利性の原則に基づき、社会医療法人の認定を受けた場合を除き、行うことは認められていません。
これは、医療法人が利益追求に走り、医療の質や公共性が損なわれることを防ぐためです。
代表的な収益業務には、次のようなものがあります。
・不動産賃貸業(医療法人の遊休資産については例外的に認められる場合がある)
・敷地外の飲食店の経営
・貸金業
・他の医療機関へスタッフを派遣
・医療施設内での玩具や文房具など療養の向上を目的としない物販
・他の病院やクリニックへのコンサルタント業務 etc…
講演や書籍の出版も収益業務になりますが、医療法人の理事長先生や役員が個人で行う場合は該当しません。
また、医療施設内での玩具や文房具など療養の向上を目的としない物販はNGとなりますが、逆に療養の向上を目的とした物販は可能です。
例えば、歯科医院の歯ブラシの販売、眼科クリニックのコンタクトレンズの販売などです。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
一般の社団医療法人の収益業務は、「勘定科目内訳書」の記載などで発覚するケースが多く、行政指導の対象となる点は注意してください。
なお、社会医療法人に認定された場合でも、収益業務を行うには、次の要件があります。
①一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上業務と認められる程度のものであること。
② 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの(注)でないこと。
③ 経営が投機的に行われるものでないこと。
④ 当該業務を行うことにより、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
⑤ 当該医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでないこと。
(注) 「社会的信用を傷つけるおそれがあるもの」とは、風俗営業、武器製造業、遊戯場などをいいます。
※厚生労働省「医療法人の業務範囲」より抜粋
医療法人でできない事業をMS法人で行う選択肢もある

一般の社団医療法人ができない収益業務の受け皿として、MS法人(メディカル・サービス法人)を設立する手もあります。
MS法人とは、医療法人ではできない営利事業を行うために設立される法人です。
事業範囲に制限のある非営利の医療法人に対し、MS法人は不動産管理や物品販売など、比較的自由な事業展開が可能です。
例えば、医療法人に代わって医療機器のリースを行ったり、クリニックの土地・建物を所有して賃貸したりすることができます。
しかし、MS法人を活用する上で注意すべきなのは、税務上のリスクです。
医療法人とMS法人との取引価格が不適切であると、税務調査で否認され、追徴課税の対象となる可能性があります。
その他、MS法人の株価の贈与税や相続税が高額になってしまう可能性もあります。
MS法人の設立は、医療法人の経営を効率化し、事業の幅を広げる有効な手段ですが、多くの注意点も無視できません。
MS法人の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
【まとめ】医療法人の運営の業務範囲の制限について理解する

医療法人の業務は、大きく分けると、「本来業務」「附帯業務」「付随業務」「収益業務」の4つに分類されます。
医療法人の事業範囲には制限がありますが、高齢化社会の中で、附帯業務として訪問看護や介護、疾病予防といった分野に進出することは可能です。
なお、社会医療法人に認定されていなければ収益業務ができないので、場合によってはMS法人の設立も検討の余地があるでしょう。
ただし、MS法人にはメリットだけでなく、デメリットもある点には注意してください。
本記事を最後までご覧いただきありがとうございました。
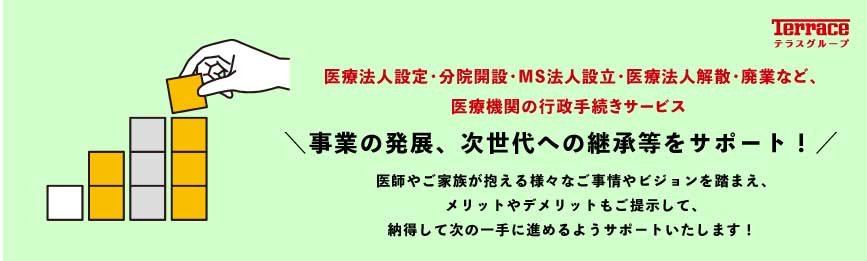



監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。