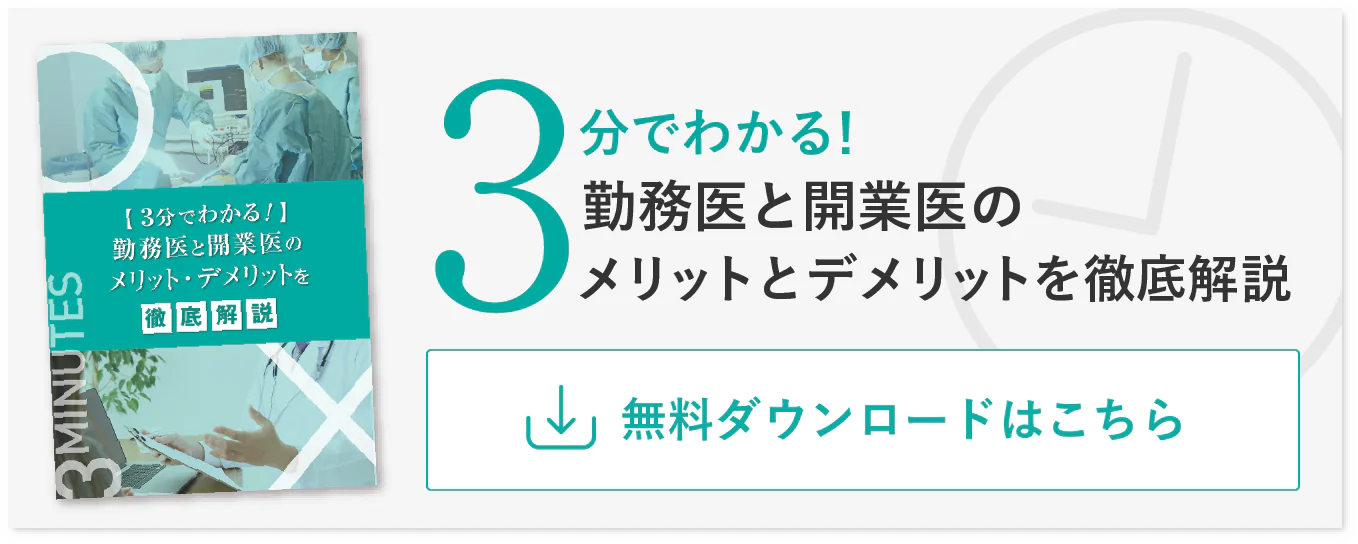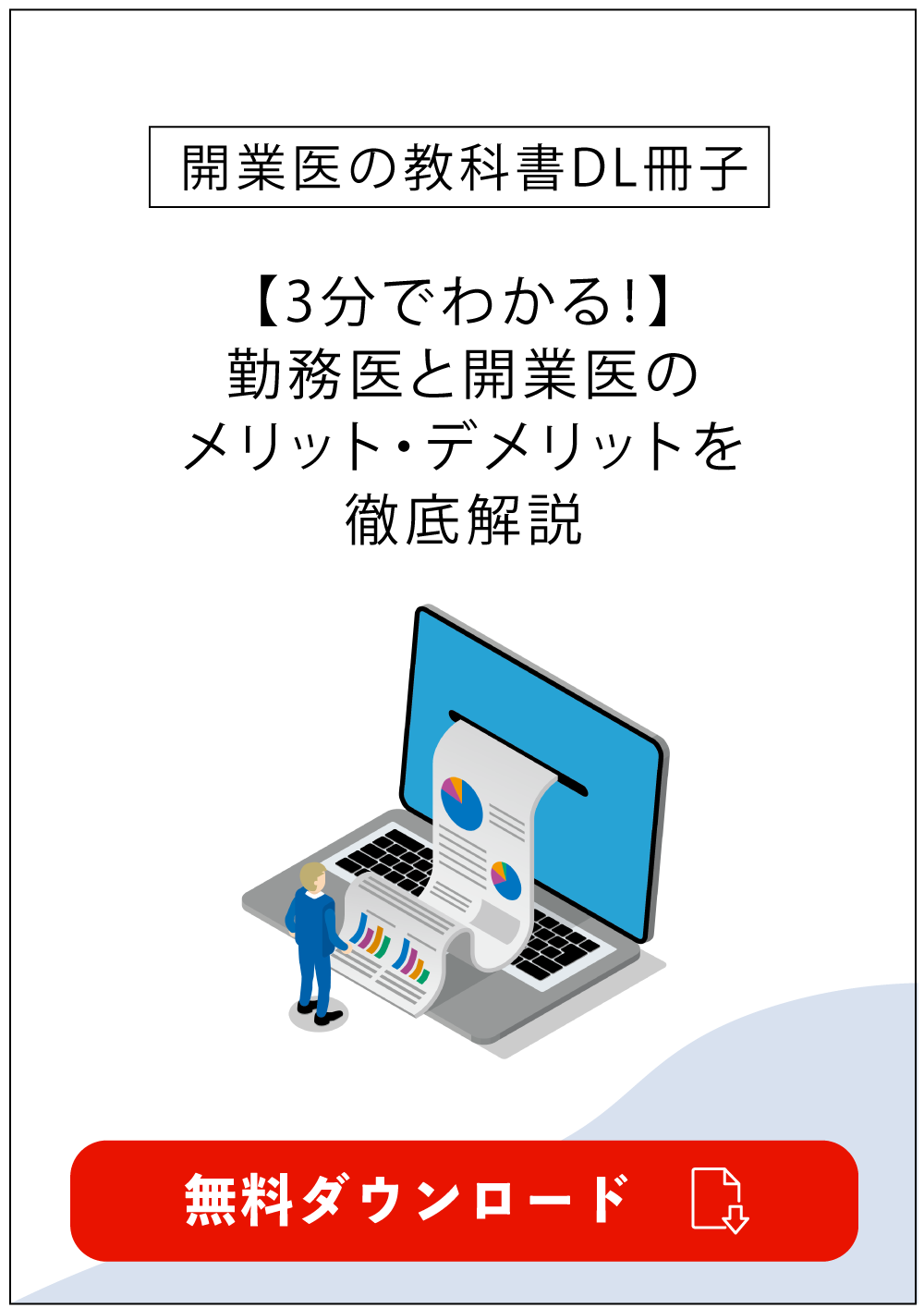新規開業するクリニックの内覧会の流れと集患に成功する7つのポイント


医院・クリニックの内覧会は、地域住民や医療関係者を招いて、院内を見学できるように開放するイベントです。
院長先生やスタッフが診療方針や設備を直接説明したり、楽しそうな院内イベントを企画したりします。
ホームページやチラシ、パンフレットだけで認知拡大を図っても、クリニックの雰囲気や人柄まで体験してもらうことはできません。
そこで、内覧会では直接クリニックに来てもらい、安心して来院できる関係を築くようにしていきます。
内覧会は、主に次のタイミングで行われます。
・クリニックの開業時
・クリニックの移転やリニューアル時
・医療法人化のタイミング
・院長交代のタイミング
・周年記念などの節目
特に、医院開業時の内覧会で成功すると、良いスタートダッシュを切ることができます。
そこで、今回はクリニック開業時の内覧会の流れや集患に成功するポイントについてお伝えします。
特に医院開業前の先生は最後までご覧ください。
クリニックの内覧会の4つの事前準備

クリニックの内覧会の最初のステップは、次のことを事前準備していくことです。
・内覧会の日時設定
・内覧会のスタッフ確保と当日の役割分担
・内覧会当日に配布するパンフレットやノベルティの用意
・内覧会の宣伝
準備期間は、他の開業準備と重なって多忙とは思いますが、余裕を持って1~2ヶ月を見ておくと無難です。
内覧会の日時設定
まずは内覧会をいつ開催するかを決めましょう。
医院開業時の内覧会であれば、開業日直前の土日祝日に行われることが多いです。
開業直前の土日であれば、多くの人が集まりやすいですし、クリニックとしても開業の準備がほぼ終わり、スタッフ採用や研修を終えている状態です。
来場者には、実際の診療環境に近い状態で見学してもらうことができ、開業まで記憶に残りやすいので来院を促しやすくなります。
あまり開業日まで間隔を空けないことがポイントです。
ちょうど祝日で3連休以上になっている場合は、在宅率の高い連休後半に開催することが多いです。
また、必ずしも休日に開催しないといけないわけではありません。
あまり多いケースではないですが、高齢者中心など、患者さんの属性が平日に適しているのであれば、平日開催も検討の余地があります。
なお、開催時間は10~16時に行われることが一般的ですが、患者さんの属性などを考慮して、あくまで目安としてください。
医師会や病院関係者にクリニックを見学してもらう場合は、住民の内覧会とは別の時間帯を設定すると良いでしょう。
内覧会のスタッフ確保と当日の役割分担

内覧会の日時が決まったら、スタッフの確保と役割分担を決めます。
内覧会は、基本的に休日に開催するため、スタッフには早めに説明して人員を確保するようにしてください。
後述するように、内覧会当日は院内見学の対応だけでなく、呼び込みやノベルティの配布、イベント対応なども発生します。
屋外で開催するイベントがある場合は、雨天時の役割分担も考えておく必要があります。
特に院長先生は、なるべく多くの来場者に挨拶できるようにしておく必要があるので、役割分担は明確にしておきましょう。
なるべく通常の診療体制と同じようにしておくと、ストレスがありません。
内覧会は、クリニックの初めての接遇機会になるので不安を感じるスタッフは多いです。
また、医院開業を経験したことのないスタッフであれば、内覧会の段取りのイメージが湧かない場合があります。 業者にスタッフ研修や接遇練習を依頼するなど、なるべくスタッフの不安は解消しておくようにしましょう。
内覧会当日に配布するパンフレットやノベルティの用意

内覧会の目的は、認知拡大を図り、住民に安心して来院してもらうことなので、来場者用のパンフレットやノベルティを当日までに用意しましょう。
ノベルティについては、ボールペンやタオル、カレンダーなど実際に使ってもらえるものを用意することが多いです。
宣伝用のチラシもそうですが、当日の配布物も完成まで時間がかかるので、なるべく早めに準備・対応してください。
内覧会の宣伝

医院開業の宣伝と並行して、主にチラシやハガキ、ポケットティッシュ、ホームページ、SNSなどで内覧会の宣伝も行いましょう。
チラシについてはポスティングだけでなく、立地によっては開業場所近くで住民に配布するのもありです。
当日、内覧会に行けない人に対しても、「この場所に新しいクリニックができるのか」と認知拡大を促すことができるからです。
チラシやポケットティッシュなどの販促物に関しては、早めに用意しておきましょう。
また、公道で販促物を配布するような場合は、道路使用許可が必要になることもあります。
なお、内覧会の宣伝も医療広告ガイドラインの対象になります。詳細は以下の記事をご覧ください。
クリニックの内覧会当日の流れ

内覧会当日は、次のような流れで進めていきます。
前もって段取りや役割分担を明確にして、スムーズに開催できるようにしましょう。
【STEP1】内覧会開始前の事前確認を行う
内覧会開始前は、事前に決めた院長先生やスタッフの役割分担を再確認していきます。
具体的には、来場への呼び込み、設備の説明など見学者対応、ノベルティの配布などです。
スムーズな運営ができるように、不安な点は解消しておきましょう。
【STEP2】内覧会のセッティングを行う
次に、内覧会のセッティングを行います。
ポスターの貼り付け、のぼりや看板の設置、パンフレットやノベルティの準備、雨の日であればマットや傘立て、傘袋の用意もしておくと良いでしょう。
準備物の抜け漏れがあれば、早急に対応する必要があります。
クリニックは清潔感の印象がかなり重要になるので、当日清掃もしておくと良いでしょう。
事前確認と内覧会のセッティングの時間を考慮して、内覧会開始1時間前にはスタッフが集合している必要があります。
【STEP3】クリニックの近くで呼び込みをする
内覧会の準備が済んだら、一部のスタッフはクリニックの近くや駅前、商店街などで住民の呼び込みを行います。
なかには、内覧会に行くかどうか迷っている人もいるので、当日スタッフがいるだけで後押しになることがあります。
また、内覧会に行かなくても来院する患者さんは多いので、クリニックの開業を知らせるチラシも配布するようにしましょう。
【STEP4】来場者対応をする
内覧会の開始時間になれば、来場者が続々と来場するので、受付とクリニックの案内をスタートします。
なるべく歓迎ムードを意識した方が良いので、余裕を持って開始時間を迎えましょう。
設備などの案内をする際は、来場者から質問されるようなことがあります。
ただ、スタッフが回答できない質問も多いので、その場合は院長先生に確認するように事前に周知しておきましょう。
患者さんは、何となく直感的にスタッフの接遇態度の良し悪しを感じ取ります。
事前にスタッフ研修などで教育しておくと良いでしょう。
【STEP5】パンフレットやノベルティを手渡しする
院内の見学が終わって帰る人に対しては、パンフレットやノベルティを手渡しします。
基本的なところですが、来場に対する感謝を告げるようにすると、スタッフの印象が良くなります。最後まで接遇を意識することを忘れないようにしましょう。
クリニックの内覧会で集患に成功する7つのポイント

最後に、クリニックの内覧会で集患に成功するポイントについてお伝えします。
内覧会を開催したからといって、集患に繋がるとは限らず、かえって印象を悪くして逆効果になることもあります。
ぜひ、内覧会を成功させて、開業後に好スタートダッシュを切りましょう。
関係者に協力してもらう場合は「スーツNG」を伝える
クリニックの内覧会を開催する際、スタッフだけでは人員不足になることもあります。
人員不足の場合は、内覧会業者などに協力してもらう場合もあるでしょう。
その際は、基本的には「スーツではなくやわらかい服装で来てください」と伝えておく必要があります。
スーツを着ている人が対応していると、緊張感が漂って、来場者が心地よく医院見学をできなくなるかもしれません。
クリニックの内覧会では、基本的には親しみやすい雰囲気を出すように努めましょう。
参加すると楽しそうな内覧会にする
医院・クリニックの人達にとって、内覧会の目的の多くは認知拡大や来院のハードルを下げることでしょう。
内覧会は、だいたい開業1週間前に行われることが多いので、内覧会で予約を獲得することもあります。
一方、内覧会の来場者は治療を目的としておらず、なかにはクリニックにそこまで興味を持っていない人も多いです。
多くの場合、医院・クリニックは症状が出てから来院するものなので、最初から興味を持ってもらえるとは限りません。
院内の設備の説明だけでは退屈してしまいますし、そもそも来場しようとは思わないでしょう。
そのため、「なんか楽しそう」「行ってみたら楽しかった」というような内覧会の方が、来場者の記憶に残ります。
・のぼりや看板を立ててお祭りのような雰囲気を出す
・楽しそうなBGMを流す
・お祭りのような院内イベントを開催する
・ビニールシートなどで土足OKにして入りやすい雰囲気にする
など、来場者が楽しめるような雰囲気にして、開業後の来院を促す方がスムーズです。
特に小児科など、子どもが多く来院するクリニックでは有効です。
また、楽しそうな雰囲気を作るのはもちろん、スタッフも楽しそうに対応するように心がけましょう。
一生懸命治療の説明をするほど逆効果になることがある
内覧会では、集患を目的にしていることがほとんどなので、来場者に一生懸命治療や医療設備の説明をしがちです。
もちろん必要なことなのですが、あまり集患に意識が向きすぎて一生懸命治療の説明をしても逆効果になることがあります。
先ほどもお伝えしたように、来場者はクリニックのことを知ろうというより、楽しもうとして来場している傾向があるからです。
そのため、あまり治療に関係のない世間話をしたり、イベントに参加してもらったりすることも大切です。
「世間話の方が難しい」
と思う先生もいると思いますが、基本的にはクリニック関連やご自身のことで構いません。
来場者は、院長先生やスタッフの雰囲気もよく見ています。
一生懸命自院を知ってもらうより、楽しんでもらうことを優先すると良いでしょう。
お祝いの品は院長先生に直接渡すようにする
知り合いの方や医療関係者など、内覧会にはお祝いの品を用意している来場者もいます。
この場合はスタッフに、必ず院長先生に直接手渡しするように伝えておきましょう。
内覧会当日はバタバタするので、ついスタッフが代わりに受け取りがちですが、相手は直接院長先生に渡したいはずです。
場合によっては「せっかく持ってきたのに軽く扱われた」と心証を悪くするかもしれません。
よほど何か大きなトラブルが起きていれば話は別ですが、基本は院長先生が直接受け取るようにしましょう。
内覧会を開催しない方がいいクリニックもある
基本的には、内覧会を開催した方が良いケースの方が多いですが、診療科目やコンセプトによっては、開催しない方が良い場合もあります。
例えば、来院していることを、あまり人に知られたくないような診療科目です。
この場合、あまり大々的に内覧会を開催しても多くの来場は見込めませんし、開業後の来院も期待できません。
自院のコンセプトや治療方針から内覧会の要否を検討して、迷うようなら専門家に相談するようにしてください。
SNSで内覧会の宣伝をする

内覧会の宣伝というと、多くの場合はチラシやホームページが思いつくところです。
しかし、患者さんの属性によっては、InstagramやFacebookなどで告知してみるのも良いでしょう。
高齢者が中心の場合はあまり効果が見込めませんが、SNSで情報収集する人は多いです。
少なくとも、コストがかからない方法なので、試してみる価値は十分あります。
来場者の記憶に残っているうちにSNSなどで接点を増やす

内覧会終了後は、あまり接点を減らさないように、SNSやホームページを更新して情報発信するようにしましょう。
例えば、内覧会の様子を写真に撮って、SNSに投稿することで、来場できなかった人にも雰囲気が伝わります。
特に開業日まで時間がある場合は、なるべくSNSやホームページで接点を減らさないようにしましょう。
【まとめ】安心して来院したいと思える内覧会を開催する
以上、内覧会開催の流れと集患に成功するポイントについてお伝えしました。
内覧会は、たしかに集患を大きく左右することがあります。
しかし、だからといって、一生懸命治療方針や医療設備について説明するだけでは逆効果になることがあります。
自院の魅力や他院との違いを説明するのも重要ですが、来場者は安心して来院したいという気持ちで内覧会に来場します。
あまり治療内容を一生懸命説明するよりは、クリニック内の雰囲気を伝えるつもりで内覧会を開催した方が集患を促せます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。
医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。
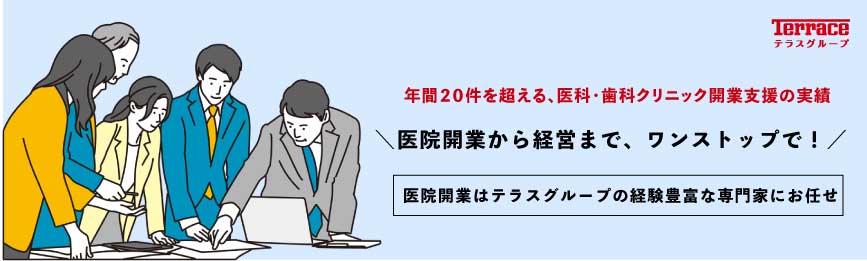
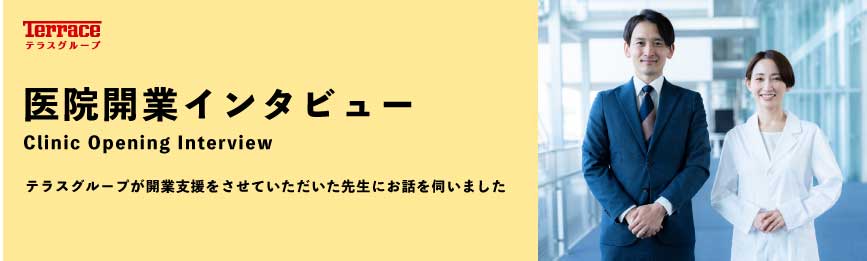


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。