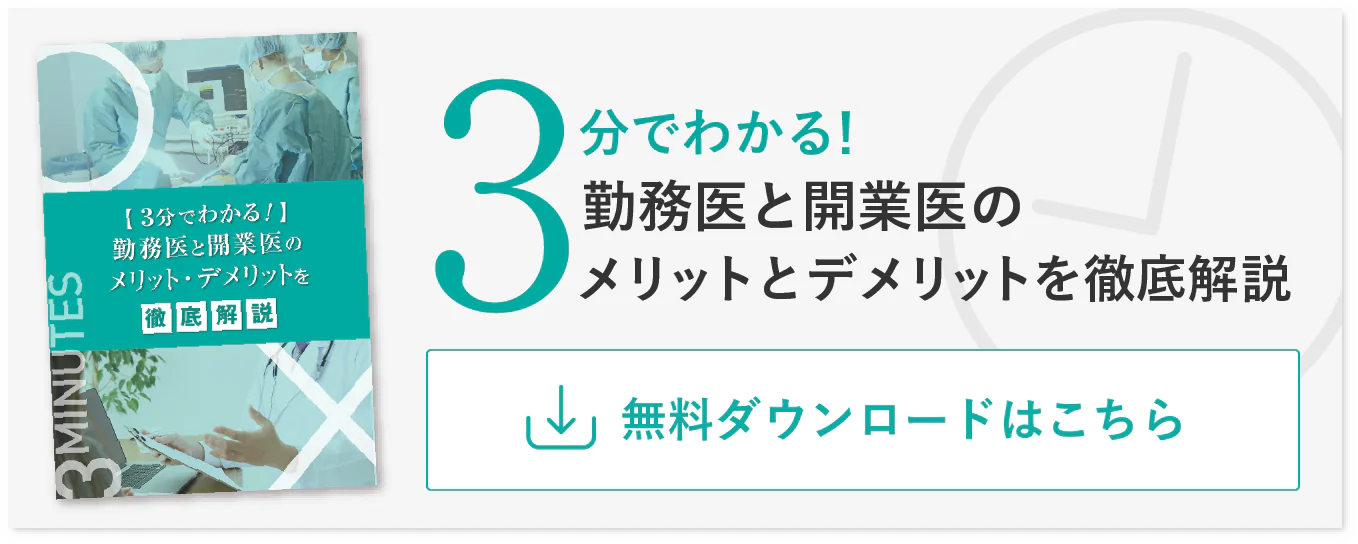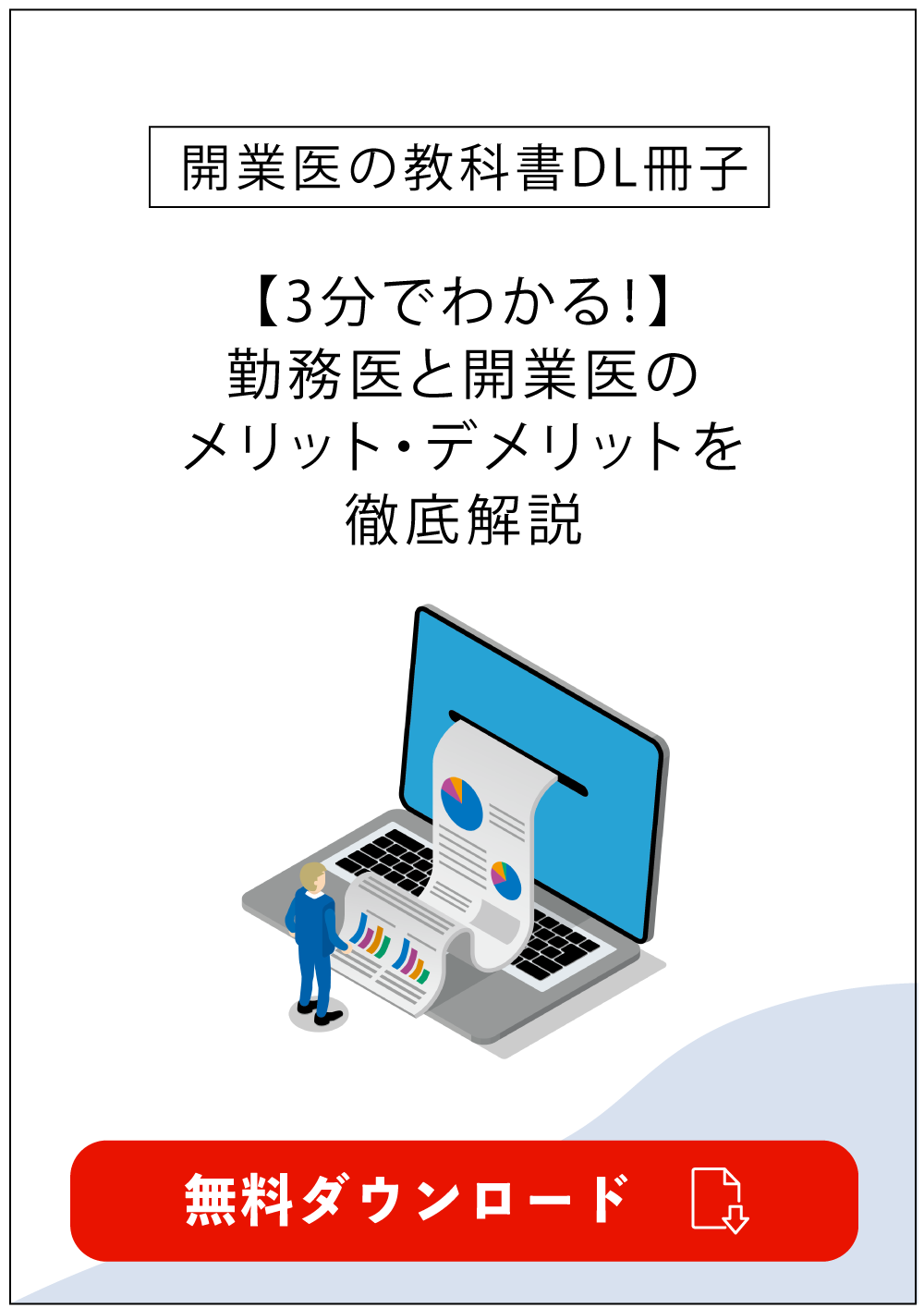外科開業で失敗しない10個のポイント|開業支援実績が多い税理士が詳細解説
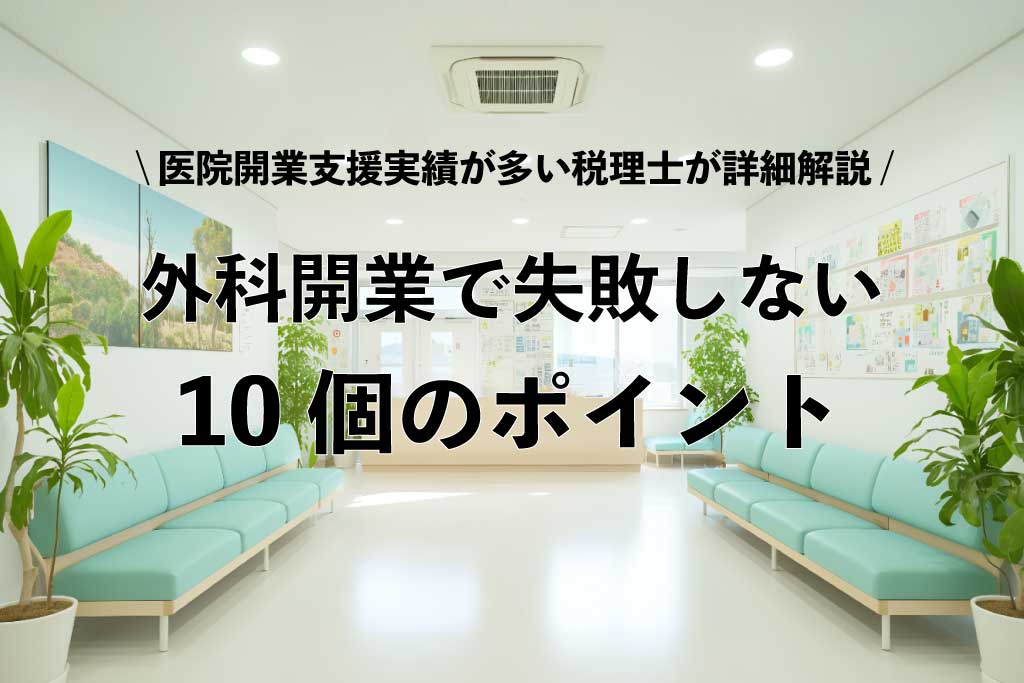
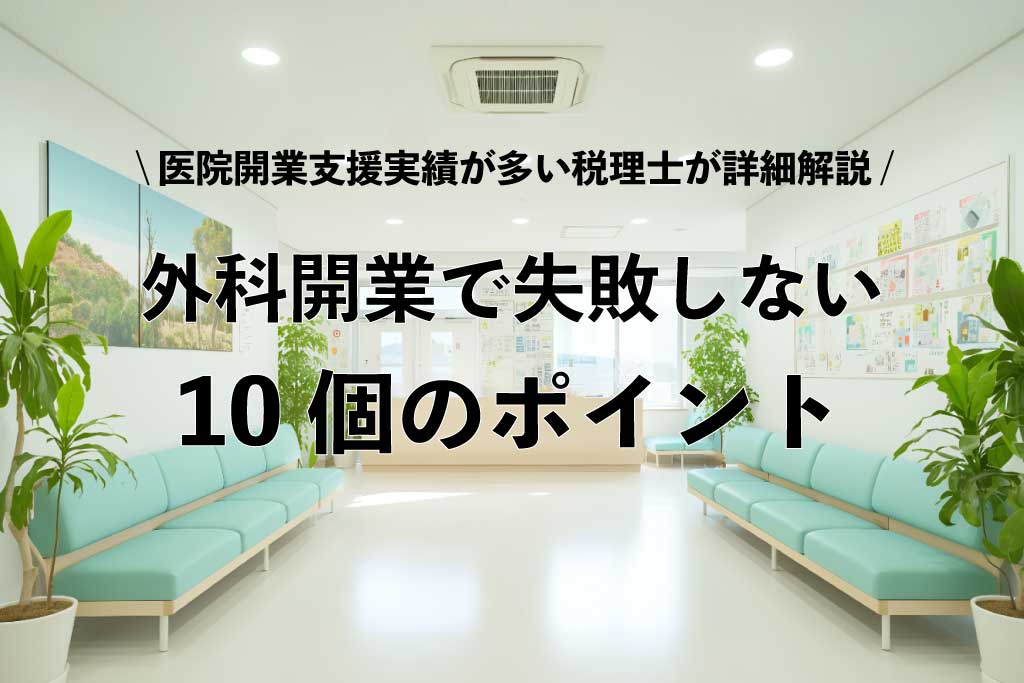
内科や眼科、整形外科に比べると、外科で開業する先生はそこまで多くありません。
「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 」によると、全国の診療所で働く外科医の人数は2,433人で、全体の2.3%程度です。
これは循環器内科(2.2%)、泌尿器科(1.9%)とほぼ同程度で、地域の需要はあるかどうかはともかく、比較的競合は少ないと考えられます。
外科医院を開業する際に注意したいことは、患者さんが継続的に来院することは期待できず、新患の来院が重要視される点です。
この点を踏まえて、外科医院の開業で失敗しない10個ポイントを解説します。
【外科医院開業のポイント①】Webマーケティングなどで新患に力を入れる

外科の開業で失敗しないためには、新患を呼ぶことに力を入れることが大切です。
冒頭でお伝えしたように、外科は手術したら継続的な来院はしないことが多く、常に新患に来院してもらわないといけません。
特に開業時は、看板、チラシ、ホームページなど、予算の許す範囲で外科医院の存在を知ってもらうことが重要です。
外科はそこまで競合医院は多くないので、特にホームページで集患を図ることで、比較的広範囲の患者さんの来院が期待できます。
MEO対策やリスティング広告で露出を上げつつ、医院のコンセプト(日帰り手術など)、専門とする疾患などを知らせるようにしましょう。
| MEO対策 | Googleマップで上位表示するための対策 |
| リスティング広告 | 特定の検索キーワードで検索画面の上位に表示される広告 |
地域によっては、競合が激しくなく、リスティング広告を出稿している外科医院が少ないなら、最初は広告費をかけない手もあります。
また、開業後しばらく経過して、クリニックの集患力が付いてきたタイミングで広告費を減らすことも有効です。
ホームページによる集患については、以下の記事をご覧ください。
【外科医院開業のポイント②】アナログな方法でも新患を呼ぶ

Webマーケティングに力を入れる一方で、地域のイベントに顔を出したり、地域の雑誌やフリーペーパーに寄稿したりするアナログな手法も有効です。
ここ数年、どの診療科目でもWebマーケティングに目が行きがちになっています。
そのため、アナログな方法で集患しているクリニックは少なくなっており、新患を獲得するチャンスと言えます。
特に近隣に競合医院が少ないのであれば、アナログな方法による集患も行っていくと良いでしょう。
【外科医院開業のポイント③】地域の大病院と連携を図る

常に新患の来院を見込めるようにするのであれば、地域間連携も意識していきます。
診療圏調査で競合医院の数を分析するのも重要ですが、他の医療機関と連携ができるかどうかも重要です。
そういう意味では、勤務していた病院の近所で開業して、密な連携を取るという選択肢もあります。
大病院との連携を十分取っているという点は、患者さんの大きな安心感にも繋がり、集患に繋がります。
【外科医院開業のポイント④】他の診療科目も標榜する

開業コンセプト次第ですが、内科や小児科といった他の診療科目を標榜するのも1つの手です。
特に内科は競合が多いものの、継続的な来院が見込めるという、外科と逆の特性を持っています。
そのため、集患対策上で、外科と内科のデメリットを補い合うことができます。
また、呼吸器外科の先生が呼吸器内科も標榜したり、消化器外科の先生が消化器内科も標榜したりするケースもあります。
小児の日帰り手術も需要があるので、小児科と小児外科を標榜することもあります。
高い専門性は求められますが、「この疾患については内科も外科もできる先生なので安心だ」と患者満足度の向上にも繋がります。
【外科医院開業のポイント⑤】継続して来院しないとはいえ患者満足度は上げるようにする

外科は継続的な来院が見込めない診療科目ではありますが、患者満足度を上げる努力は必要です。
というのも、患者満足度が高ければ、かつて来院していた患者さんが、他の患者さんを紹介することもあるためです。
開業後、患者さんや他の医療機関からの紹介による来院が増えてくるようになったら、広告費を下げることができます。
また、Googleなどの口コミ評価が高ければWebマーケティング上も大きくプラスに働きます。
【外科医院開業のポイント⑥】自分の専門性と患者さんのニーズを見極める

患者さんのニーズがなければ、どんなに競合が少ないエリアで開業しても患者さんの来院は見込めません。
大きな手術となると、多くの患者さんは大病院を探します。
また、開業時から大きな外科手術に対応する医療設備を揃えることは、開業資金の観点からも現実的とは言えません。
ただ、例えば下肢静脈瘤、鼠径ヘルニア、透析シャントなど日帰り手術を専門とした外科クリニックを開業するケースならあります。
胆嚢炎や虫垂炎などの日帰り腹腔鏡手術も比較的需要があります。
日帰りであれば、日々忙しく、数日~数週間程度の入院が厳しい人でも手術を受けることができます。
日帰り手術をコンセプトにして、開業するのも検討の余地があります。
ただ、先ほどもお伝えしたように、他の診療科目も標榜することも検討しましょう。
「腹腔鏡手術に特化」「日帰り手術専門」など、他の病院やクリニックと差別化できるように、開業コンセプトをじっくり考える必要があります。
【外科医院開業のポイント⑦】導入する医療設備は慎重に検討する

外科は、手術スペースが必要であることや、手術用の医療設備が必要であることから、比較的開業資金がかかる傾向にあります。
少なくとも、内科や皮膚科、精神科・心療内科よりは開業資金はかかります。
もちろん、無理に開業資金をかけて、大がかりな医療設備を導入するようなことをすると、開業後の資金繰りが苦しくなります。
開業時は必要最低限の設備だけにして、経営が軌道に乗ってきたら追加していく方が現実的です。
開業資金の考え方については、以下の記事をご覧ください。
【外科医院開業のポイント⑧】集患しやすく他の病院と連携できる立地を選ぶ

新規の患者さんの集患が重要になる外科では、開業の立地・物件選びは重要になります。
外科は、内科や歯科医院に比べると、そこまで競合医院は多くはなく、比較的駅近の物件などでも探しやすいことが多いです。
開業コンセプトや患者さんの属性に合った物件選びをするようにしましょう。
また、先ほどお伝えしたように、他の病院との連携ができるかどうかも重要です。
集患が見込めて、かつ他病院と連携しやすい立地を選ぶことができると理想です。
立地・物件選びについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
【外科医院開業のポイント⑨】経営が軌道に乗ってきたら常勤の麻酔科医を採用する

外科医院のスタッフ採用で、他の診療科目と違う点は、麻酔科医が必要となる点です。
ただ、開業直後は常勤ではなく、非常勤の麻酔科医で対応することも要検討です。
まだ集患が十分でない段階では、非常勤の麻酔科医で対応できるケースが多いです。
麻酔科医については、経営が軌道に乗ってきたら採用するくらいで良いでしょう。
なお、常勤の麻酔科医を採用すると、麻酔管理料が算定できるようになります。
【外科開業のポイント⑩】下肢創傷処置を行う外科医院は下肢創傷処置管理料が算定できる

下肢創傷処置を行っているク医院・リニックは、下肢創傷処置管理料を算定できるようになります。
下肢創傷処置管理料は、2022年度の診療報酬改定で新設され、月1回500点を算定できます。
該当する場合は、届出を行うようにしましょう。
【まとめ】外科医院は新患の来院を意識する
外科医院開業の失敗しないポイントについてお伝えしました。
外科は、手術が終われば継続的に来院することはないので、いかに新患の来院を意識して集患できるかどうかがポイントです。
・新規の患者さんが来院しやすい立地にする
・Webマーケティングに力を入れる
・地域のイベントに顔を出すなどアナログな方法でも集患する
・他病院と連携する
・患者さんから紹介されるように患者満足度を上げる
以上のことを意識して、外科医院を経営していくことが必要になります。
また、開業コンセプトによっては、内科、小児科など他の診療科目と標榜することも検討の余地があります。
税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。
医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。
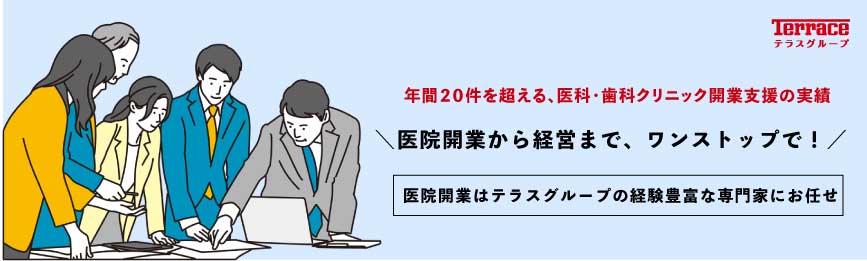
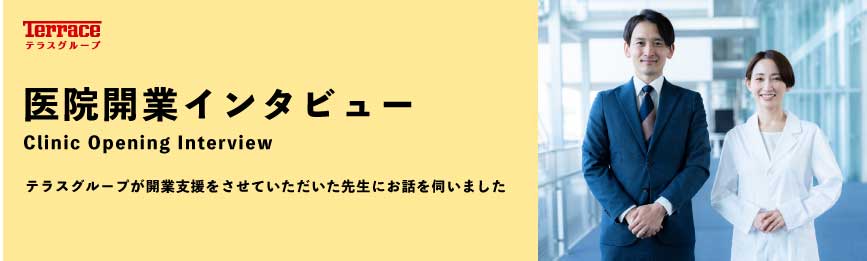
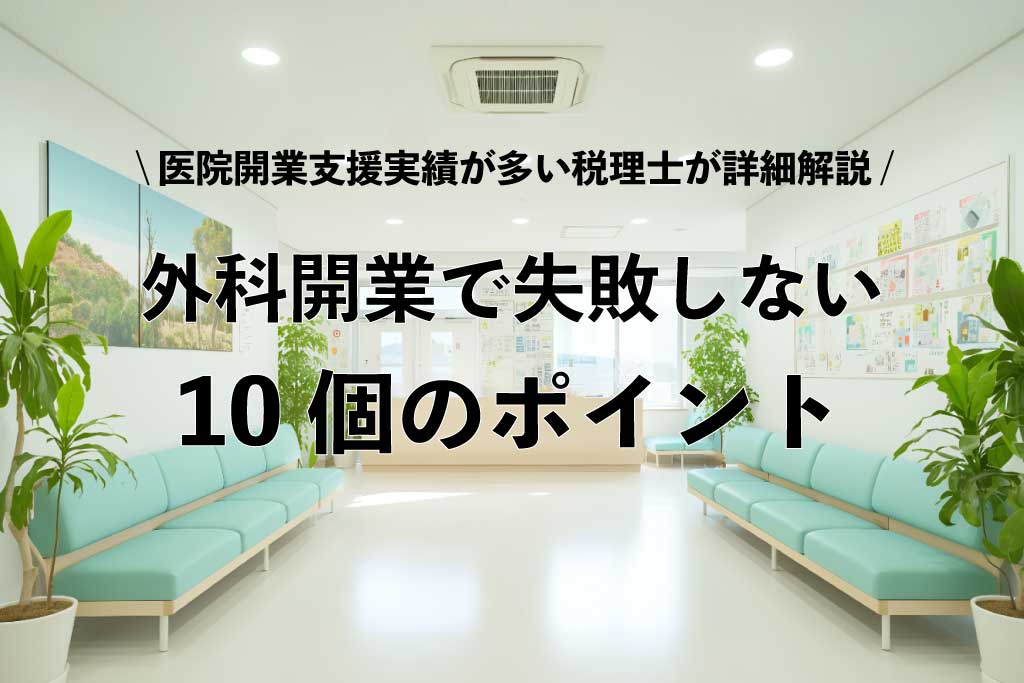

監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。