成長に繋がるクリニックのスタッフ教育10個のポイント


医院・クリニックのスタッフ教育というと、何も治療の知識や技術、スキルのことだけではありません。
例えば看護師の場合は、治療技術の向上だけでなく、患者さんへの接遇力向上や、クリニック全体のチームワークやコミュニケーションも重要な教育内容です。
また、スタッフが業務上のミスをしたときなど、どうしても厳しく指摘し、教育しなければならない場面が出てくることがあります。
しかし、叱責を繰り返してしまうと、スタッフは嫌々働くことになり自主性が失われ、成長を阻んでしまうことになります。
場合によっては、一生懸命スタッフ教育をしているつもりが、パワハラと言われてしまったり、退職を招いたりしてしまいかねません。
そこで今回は、医院・クリニックのスタッフ教育で重要なポイントについてお伝えしていきます。
【ポイント①】スタッフ教育中に「指摘」が「叱責」と受け取られないようにする

院長先生やベテランスタッフであれば、「これはだめだよ。こうするんだよ」とスタッフに「指摘」する場面が出てきます。
しかし、「指摘」したつもりが、「叱責」と受け取られたりすることは少なくありません。
もちろん、「叱責」と受け取られれば、スタッフのモチベーションに関わってきますし、積み重なればパワハラと認識されるかもしれません。
なぜ、「叱責」と受け取られてしまうのでしょうか?
「これはだめだよ。こうするんだよ」という教え方ばかりでは、スタッフに「やらされ感」を与えてしまうからです。
細かいことを指摘して、改善や修正を促すほど、自主的に動くモチベーションを下げてしまい、やがてスタッフは嫌々働いてしまうのです。
でも、改善した方が良いことを指摘しなければ、今度はスタッフの成長に繋がりません。では、どうすれば良いでしょうか?
この場合、「スタッフに考えさせる」ことを意識するのです。
スポーツの話を例に挙げると、箱根駅伝で2連覇を達成した青山学院大学陸上部の原晋監督の選手への指導方針がそうでした。
選手が「右足が痛いが、どうしたら良いですか?」と聞かれたら「なぜ痛いのか、自分で考えてみなさい」と問い返すそうです。
選手は自分で考え、答えを導き、それに対して原監督は意見を伝えるようにしていたそうです。
これはクリニックのスタッフ教育でも大きなヒントです。
敢えて答えを最初に言わず、考えさせることで「やらされている感」を排除するのです。
「こうすればもっとうまくいくよ」と伝えることも大事ですが、「どうすれば良かったと思う?」とスタッフに考えさせて、気付かせるような問いかけをしましょう。
自己分析の習慣を身に付けさせることで、スタッフは自発的にモチベーションを掘り起こすことができるのです。
また、考える力を養うことで、早い段階でスキルが熟成し、臨機応変な対応力が身につくようになるでしょう。
【ポイント②】改善点だけでなく良かった点も具体的に指摘して褒める

改善点を指摘しつつも、良かった点をほめる習慣を付けると、やや厳しいことを指摘する際に角が立たなくなります。
どんな点が良かったか、悪かったかを明確に伝えて、アメとムチ両方使うようにするといいでしょう。
しかし、効果的なほめ方と、そうでないほめ方がある点は注意してください。
例えば、仕事で「ありがとう」「助かったよ」とスタッフに声がけするのも大切です。
しかし、機械的に感謝したりほめたりしても、スタッフは社交辞令としか思えず、それほど嬉しい気持ちにはなりません。
つまり、「今日の◯◯な対応は、とても良かったよ」などと、具体的に指摘してほめるようにするのです。
ほめられた理由を明確に言われれば、スタッフは自分の仕事が役に立ったと感じて、嬉しい気持ちになります。
そのうえで「○○をすると、もっと良いと思うよ」と指摘すると、少なくともスタッフは叱責されたとは捉えません。
気分のいい状態で指摘されたことは、素直に活かしたくなるものです。
スタッフとしては、やる気を持って「もっと良くなりたい!」と考えるので、今まで以上にますます能力を発揮してくれるでしょう。
【ポイント③】第三者を介して間接的にほめる

ほめ方の点でもう1点お伝えすると、院長先生が直接良かった点をほめるだけでなく、第三者を介して間接的にほめることも効果的です。
心理学で「ウィンザー効果」と呼ばれるもので、例えば「よくがんばっていると、○○さんが言っていたよ」というものです。
むしろ、本人の口からではなく、第三者を介したほめ方のほうが、説得力があって嬉しさを感じる人も少なくありません。
「○○さんのおかげで今日の診察は本当に助かりました」という話を聞いたら、積極的に本人に教えてあげましょう。
院長先生の方から「看護師の○○さんがほめていたよ」と言うのも、他のスタッフに「院長先生がほめていたよ」と言ってもらうのも効果的です。
口裏合わせて間接的にほめる必要はないですが、日々のスタッフとの対話のなかで意識していくといいでしょう。
第三者は、院長先生の他、配偶者、事務長、看護師長などの幹部クラスだと効果的です。
目上の人が意外と評価してくれることがわかると、間接的にほめられたスタッフは驚きと喜びを感じることができるでしょう。
【ポイント④】陰口を言うのではなく本人に直接指摘する
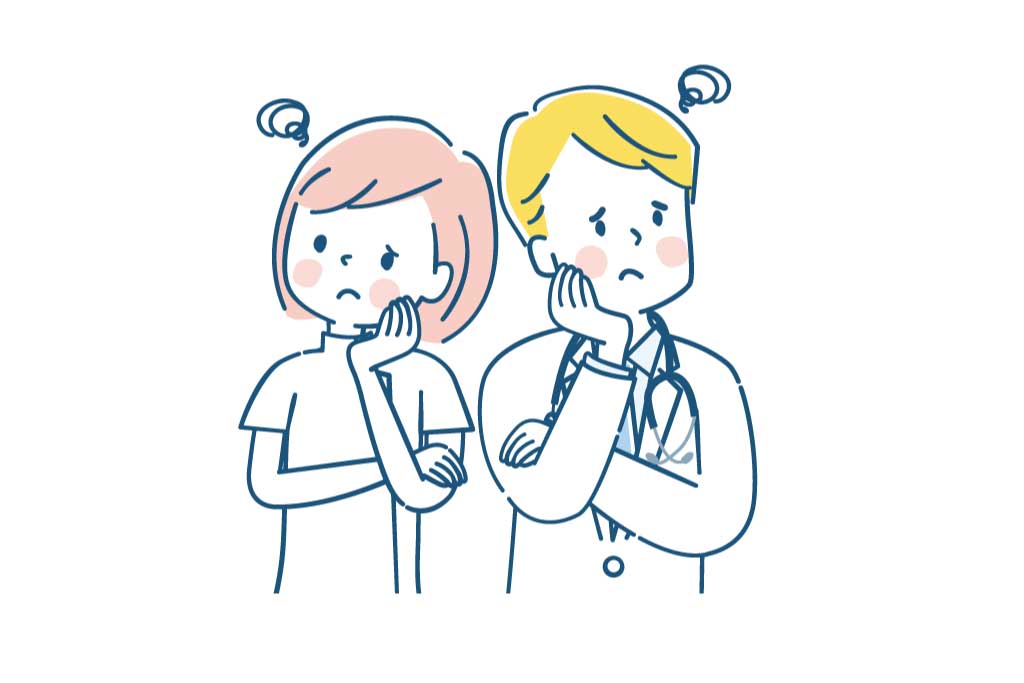
良かった点を第三者に伝えることは効果的ですが、逆に悪かった点、改善してほしい点を第三者に言ってしまうのは逆効果です。
つまり、「あいつがまた同じ失敗をした」「あいつをどうにかしてほしい」という陰口や愚痴です。
「陰口や愚痴は良くない」というのはよく聞く話だと思いますが、スタッフマネジメントの観点では本当にマイナスです。
まず、陰口を言われたスタッフが良い気分がしません。
「自分ももしかしたら陰口を言われているのではないか」と不信感を募らせることになります。少なくとも共感は得られないでしょう。
改善してほしい点、やめてほしい点があれば、上記のことを参考に角が立たないように本人に直接指摘しましょう。
もし、他のスタッフにも注意してほしいという意図があれば、その旨を第三者にはっきり伝えるようにしてください。
また、第三者を介して注意する場合は、ほめる場合と同様に配偶者、事務長、看護師長などの幹部クラスにしましょう。
そうでないスタッフに間接的に指摘することは、逆効果になる可能性が高いです。
【ポイント⑤】スタッフに対して余計な先入観を持たない
先に「価値観は人それぞれ違う」ということを書きましたが、もう少し詳しく延べます。

スタッフを教育する際は、余計な先入観を持たないように注意しましょう。
具体的には、スタッフの言動や行動を見て、頭ごなしに「あいつはだめな奴だ」「やばい奴を採用してしまった」とレッテルを貼らないことです。
スタッフの自信や成長機会を奪ってしまうことになりかねません。
例えば、スタッフが調べればわかるようなことを質問してきたとします。
そのとき、多くの院長先生や先輩スタッフは「自分で調べない奴だ」と思うでしょう。
たしかに、「自分で調べてから聞きに来て」と言わないといけないこともあるでしょう。
しかし、スタッフが本当に何も調べていないかどうかは、実は誰もわかりません。
もしかしたら、時間かけて間違った調べ方をしているかもしれませんし、調べたことに疑問を持って聞いている可能性があります。
調べ方が間違っているのであれば、「○○で調べると良いよ」と言えば済む話です。
また、調べても疑問を感じているなら「あなたはどう思うのか?」「なぜそう思ったか?」と問いかけて自発的に考えさせることもできます。
特に入職したばかりのスタッフに対しては、院長先生や他の先輩スタッフが先入観を持ってしまいがちです。
しかし、必要以上にレッテルを貼ってしまうと、スタッフはやる気をなくし、本当に仕事ができないスタッフになってしまうので注意しましょう。
【ポイント⑥】「言わなくてもわかるだろう」は厳禁

これも、ある意味先入観の話に近いのですが、「これくらいはできるだろう」「言わなくてもわかるだろう」という過度な期待感は厳禁です。
特に新卒や入職したばかりのスタッフに対して、特に言わなくても察してくれるとは考えないようにしましょう。
院長先生や先輩スタッフにとっては当たり前のことでも、他の経験の浅いスタッフには当たり前ではありません。
マニュアル化して指導しないと身に付かないことも多いです。
それなのに、「それくらい察して仕事してくれよ!」と叱責してしまうと、「きちんと教えてくれないとわからない」と反発されることになります。
当然、スタッフとしては理不尽に叱られた気持ちになるので、やる気は大幅に削がれてしまいます。
また、医療業界で「言わなくてもわかるだろう」という気持ちでスタッフに治療に関わらせると、インシデントや医療過誤に繋がりかねません。
特に入職したばかりのスタッフについては、後述するように「この場合はどうしたらいいと思う?」と考えさせながら丁寧に教えていきましょう。
【ポイント⑦】院長先生とスタッフの価値観が決定的に違うことを理解する

院長先生とスタッフは、そもそも価値観が違うということを認識しておく必要があります。
とある経営者が、このようなことを言っていました。
「社長は自社の利益主義、スタッフは自分の幸せ主義」
これは医院・スタッフでも同じことで、各々の立場上変えることはできません。
ですから、価値観が決定的に違うスタッフの言動や行動について、否定的な感情になっても、次のように考えるようにする習慣は欠かせません。
「なぜ、あのスタッフはこのような発言をしたのか? 行動したのか?」
感情はコントロールすることはできませんが、思考や行動はコントロールできます。
否定的な感情が生まれても、否定的な思考や行動は抑えることができます。
とはいえ、否定的な感情を抑えて、態度に出さないのは、習慣づけないとなかなか難しいかもしれません。
しかし、相手の価値観を理解して、否定することなく自分の伝えたいことを伝えていくことができれば、スタッフとの人間関係や成長速度は劇的に変わるでしょう。
【ポイント⑧】院長先生やベテランスタッフが経験したことを伝える

スタッフに自主的に考えさせるようにすることは大切ですが、あまり「自分で考えろ」と突き放してばかりでは、かえってスタッフは困ってしまいます。
おそらく、「この人は全然教えてくれない、何もしてくれない」と思われて、不信感を抱かれてしまうでしょう。
敢えて「自分で考えろ」と突き放すのは、指導側に明確な答えや方向性を準備できる状況で、初めて功を奏するためです。
スタッフが考えてみたことに対して、経験に裏打ちされた明確な答えがなければ、スタッフは到底納得できません。
ポイントは、その答えが理論や机上の知識だけでなく、経験に裏打ちされているということです。
経験がもとになっていないと、明確で柔軟な回答ができなくなります。
ただ、院長先生が看護師や医療事務の仕事を経験するわけにはいきません。
その際は、ベテランのスタッフの力を借りるようにしましょう。ベテランのスタッフに教育担当になってもらうのも一つの手です。
【ポイント⑨】上から目線で一方的に押さえつけずに自分の気持ちを伝える

院長先生やベテランスタッフの経験はもちろん、場合によっては、院長先生自身の気持ちを伝えることも大切です。
最近は少なくなってきましたが、「自分は雇っている立場」「上司は自分」と言わんばかりに上から目線で接してしまうケースがあります。
当然、「ちゃんとやってよ!」と上から目線で押さえつけられたスタッフは大きくやる気が削がれます。
しかし、スタッフの改善点を指摘しないままではいけません。放置すれば問題は大きくなります。
この場合は、一方的に押さえつけるのではなく、自分の気持ちを伝えるといいでしょう。
例えば、患者さんに無愛想な対応をする受付スタッフがいるとします。
挨拶もまともにせず、会計時などは患者さんの目で見て話そうとしません。院長先生から見て最低レベルの接遇態度です。
だからといって「挨拶もまともにできないのか!」「患者からクレームが来るだろ!」と押さえつけるような言い方は逆効果です。
もしかしたら、自分では精一杯の対応をしていたつもりで、気付かなかっただけかもしれません。
実際、接遇態度が今一つに見えても、自分では精一杯な受付スタッフは少なくありません。
それで、いきなり一方的に叱られては、かえって萎縮してしまって自然な接遇ができなくなるでしょう。
しかし、「あの患者さんは今日の治療に少し緊張していたよ。だから、もっと笑顔で挨拶して、緊張をやわらげてほしかった」と自分の気持ちを話したらどうでしょうか?
スタッフとしては、どう対応しなければいけなかったかが理解でき、受け入れることができるでしょう。
そのうえで、「もっとこうするといいよ」など具体的な方法をアドバイスすると、改善に繋がりやすくなります。
院長先生や先輩スタッフの伝え方を少し変えるだけで、スタッフのやる気は大きく変わります。
【ポイント⑩】1つでも新しいことに挑戦してみる

スタッフの成長を促すには、教育的な意味も込めて、1つでも新しいことに挑戦してみるのもいいでしょう。
クリニックによっては、若手のスタッフの割合が多い場合と、ベテランスタッフの割合が多い場合があります。
一長一短があり、どちらが良い、悪いはないのですが、ベテランスタッフの割合が多いと、技術的に熟練している反面、新しいことに挑戦しなくなりがちです。
それでは、マンネリが生じてしまい、スタッフ全体の士気が低下しますし、治療技術や患者満足度の向上、業務効率化に繋がりません。
1つでも良いので、新しいことに挑戦していくことで、スキルを上げてスタッフの成長を促すようにしましょう。
スタッフのマンネリ化を防いで、個々の能力とモチベーションを上げていく秘訣は、以下の記事をご覧ください。
【まとめ】自主性を引き出す教育が、スタッフの成長に繋がる
成長に繋がるスタッフ教育のポイントを10個お伝えしました。
10個のポイントで共通しているのは、スタッフの自主性を引き出すことができることです。
各々のスタッフが積極的に、自ら進んで動き出すことが、各々の成長に繋がります。
おそらく、どれか1つでも取り入れれば、スタッフのモチベーションは格段と高まり、治療技術や患者満足度の向上に繋がるでしょう。
ぜひ、スタッフがイキイキと働くことができて、患者満足度の高いクリニックを目指してください。
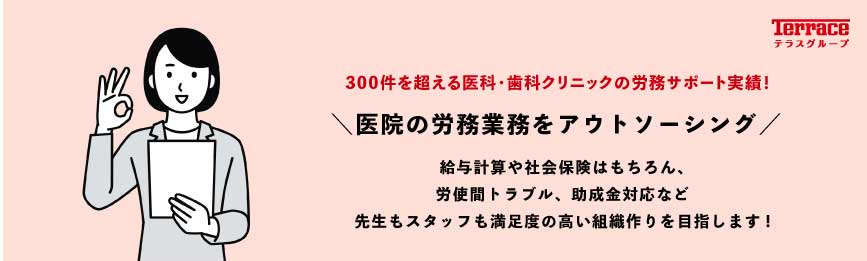
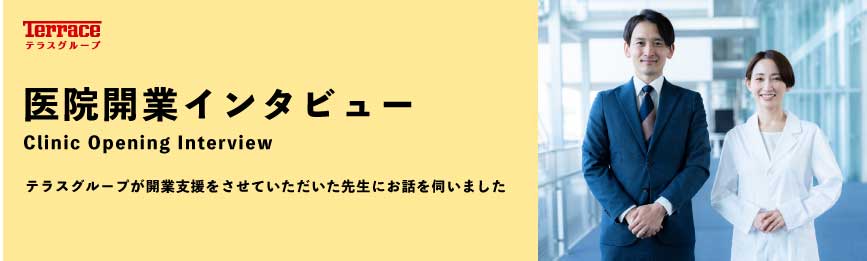
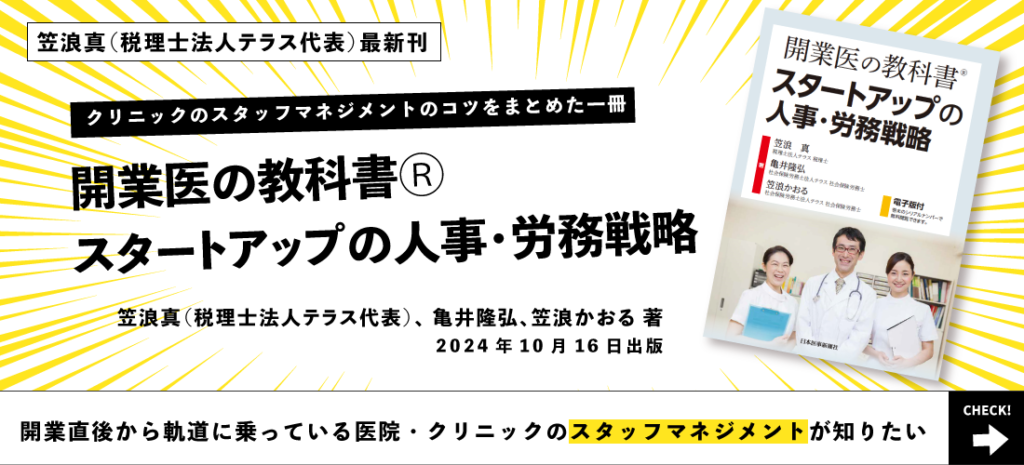


監修者
亀井 隆弘
社労士法人テラス代表 社会保険労務士
広島大学法学部卒業。大手旅行代理店で16年勤務した後、社労士事務所に勤務しながら2013年紛争解決手続代理業務が可能な特定社会保険労務士となる。
笠浪代表と出会い、医療業界の今後の将来性を感じて入社。2017年より参画。関連会社である社会保険労務士法人テラス東京所長を務める。
以後、医科歯科クリニックに特化してスタッフ採用、就業規則の作成、労使間の問題対応、雇用関係の助成金申請などに従事。直接クリニックに訪問し、多くの院長が悩む労務問題の解決に努め、スタッフの満足度の向上を図っている。
「スタッフとのトラブル解決にはなくてはならない存在」として、クライアントから絶大な信頼を得る。
今後は働き方改革も踏まえ、クリニックが理想の医療を実現するために、より働きやすい職場となる仕組みを作っていくことを使命としている。









