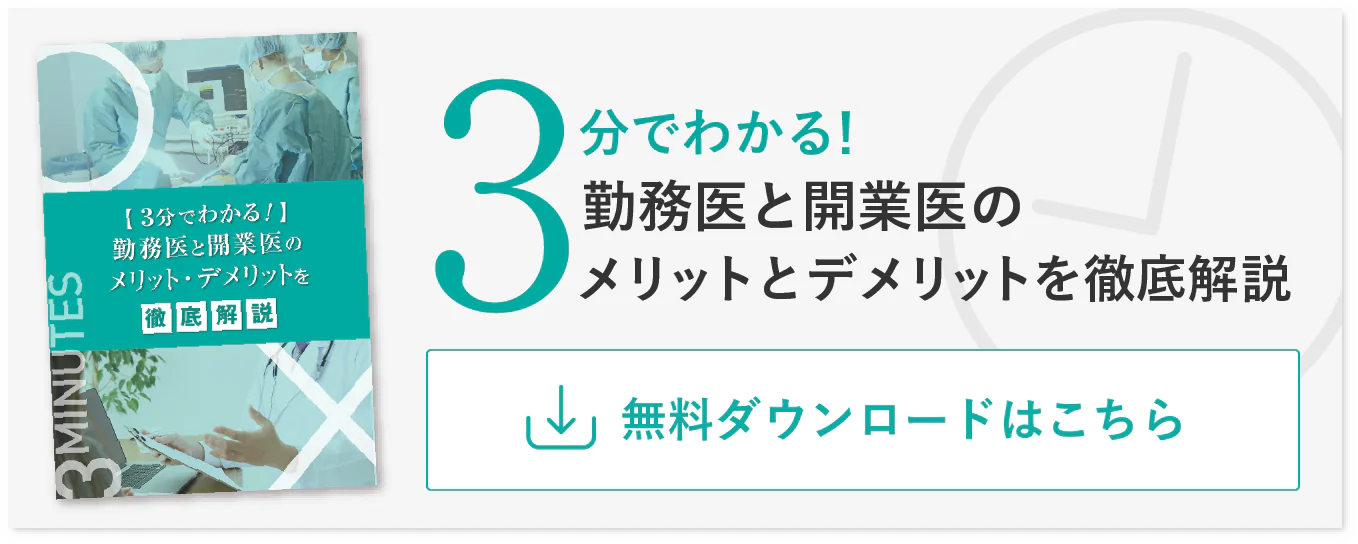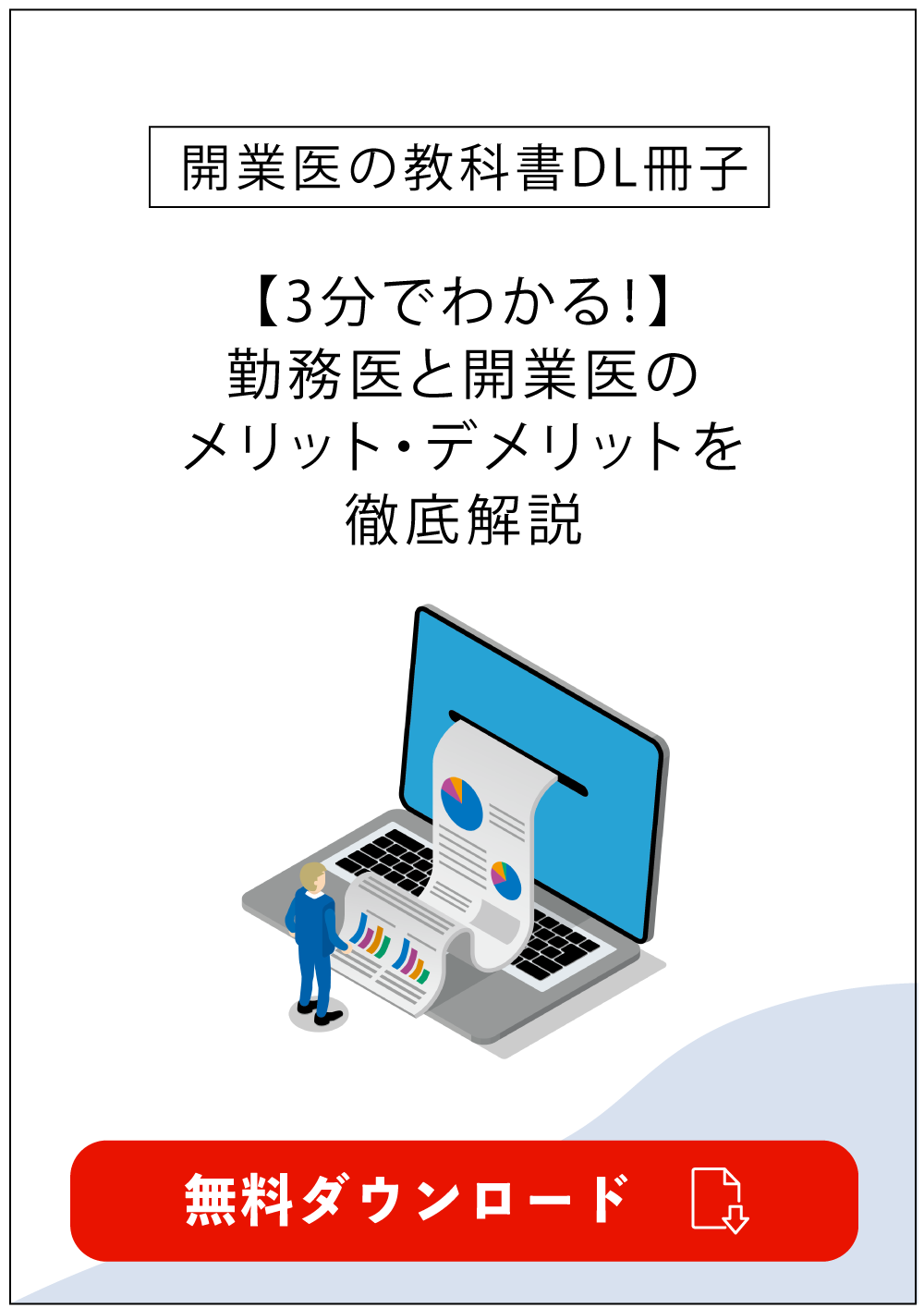患者さんファーストでの自費診療のおすすめの仕方!自費診療率が高まる!デンタルローンの選び方


はじめに
「あそこのお医者さんは高いから」と噂されるのが嫌。自費診療の説明をいくらしても「保険範囲内でお願いします。」と言われてしまう。そもそも、どのように自費診療の説明をしたらよいかわからない。そんな風にお悩みではありませんか?
歯科医院の収益を伸ばすためには、“患者さんの数を増やす”ことと、“自費診療率を上げること”が必要です。
しかし、患者さんが増えたとしても、自費診療率が上がらなかったら、クリニックの収益アップには繋がりにくいのが現状です。
そこで今回は、自費診療率を高めるデンタルローンについてお話いたします。
なるほど!自費診療率が上がらない理由

まず、なぜ自費診療率があがらないのでしょうか?
多くの先生は、「自費診療の説明はしているはずなのに、患者さんに話を聞いてもらえない」だとか、「自費診療の説明はしたけれど、保険適用内でやってほしいといわれてしまう」とお悩みです。
なぜ患者さんに自費診療が受け入れてもらえないのでしょうか?そこには、意外な理由が隠れています。
ここでは、自費診療率が上がらない理由をお伝えいたします。
先生自身が保険適用内で良いと考えている
まず、先生自身が、心の中で「保険適用内でも十分治療できるな」と考えてしまっている点が挙げられます。
もちろん、保険適用内で治療することはとても良いことです。しかし、それは本当に患者さんの求めていることでしょうか?
おそらく先生は、「患者さんはきっと安い方が良いだろう」とか、「患者さんは保険適用内で治療してほしいだろう」と思われているのではないでしょうか。
しかし、患者さんの中には、保険適用外の「自費診療の治療を受けたい」と思っている患者さんが少なからず存在するのです。
その患者さんたちに、自費診療のことを勧めずに保険適用内で治療をしてしまった場合、患者さんはどう思うでしょうか?
本来患者さんの望んでいた治療が自由診療であったという潜在的なニーズ、機会をきちんと掘り起こすというためにも、先生自身の基準ではなく、(自由診療を求められている)患者さん基準で、患者さんが求めている治療が何なのか見極めて、自費診療をお勧めしてみてください。
自費診療メニューを患者さんの目に見えるところに置いていない
自費診療のメニューはありますか?ある場合、どこに置いていらっしゃるでしょうか。
歯科医師自身は自費診療メニューは概ね推測できますが、患者さんは歯科医療に関しては素人なので、相当な下調べをされている方を除き、自費診療メニューに何があるのかはわからない方ばかりです。
そこで、待合室などに自費診療メニューを設置することをお勧めします。
ちょうど患者さんの目線が向くところにメニューパンフレットを置いたり、人は動くものに注意が向く性質を活かしてテレビに自費診療メニューを流したりするのも良いかと思います。
肝心の自費診療メニューについてですが、先生のクリニックに来院する患者さんが今、何に困っている人が多いのかを考えて作成することが大切です。
人は、悩み事や、困っていることを解決したくてお金を払いますので、そのお悩みを解決してあげられるようなメニューを設定すれば良いのです。
患者さんに自費診療の必要性を感じてもらえていない
自費診療メニューを患者さんにお勧めする方法は、初対面の人をデートに誘うのと同じだと考えるとわかりやすくなります。
先生は、初めて会ってほんの10分くらいの人に対し、いきなりデートに誘うでしょうか?
おそらく、もう少し会話をしたり、何回か顔を合わせる機会を設けて、相手のことを理解してから誘うと思います。
自費診療メニューをお勧めするときも、これと全く一緒です。
初めて来院したクリニックで、まだ先生との関係も出来ていないのに、いきなり120万円の治療を勧められたら、患者さんは戸惑い、断ってしまうでしょう。
断るだけなら良いのですが、「あそこの歯医者は、高い診療を勧めてきた!絶対行かない方が良いよ!」などと噂を立てられてしまうかもしれません。
このようにならないために、通常の診察の中で患者さんのお悩みニーズをくみ取り、何度か患者さんに自費診療との接点を持ってもらい、その末に「自由診療をご提案する」必要があります。
潜在的なニーズやその状態から医師自身が自費診療の必要性を見極め、患者さんファーストで自費診療の必要性をご提案、ご説明するのです。
院内ポスターや、自費診療のメニュー表、メルマガでクリニックについて広報するのも有効な手段です。
患者さんの目に触れるところに自費診療メニューを置き、診療の中で患者さんに合った自費診療メニューを医師自身が見極め、患者さんファーストでご提案することで、自費診療率のアップにつながります。
デンタルローンで患者さんが得られるメリット

デンタルローンをすることで、患者さんは今までよりも幅広い治療を受けることができるようになりました。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
矯正、インプラントなど保険外診療全般の高額治療を受けられるようになる
今までは経済的な理由から保険範囲内の診療でしか入歯やブリッジを入れられなかった患者さんも、デンタルローンを使えば、保険範囲外の素材を使った入歯やブリッジを使用することが出来るようになります。
治療をすぐにはじめることが出来る
急ぎで早く治療を開始したいというニーズにも対応することができます。
返済回数の多さ
デンタルローンは通常のローンよりも借り入れ金額が高く設定されています。そのため、高額な保険外診療に対応することができるのです。
返済回数も多めに設定されているため、患者さんの月々の負担額を抑えることができます。
医療費控除対象内
1年の内に10万円以上医療費を使った場合、確定申告をするといくらか戻ってきます。この医療費控除の中には、デンタルローンでの支払いの金額も含まれます。
他にも、デンタルローンには、歯科医院の窓口で手続きができたり、借入金額を自分で決められる等のメリットがたくさんあります。
しかし、
・クレジットカードのように審査がある
・連帯保証人が必要な場合(主婦や年金受給者)もある
・手数料が発生することがある
という点は患者さんに説明しておかないといけません。
また、このようなメリットがあるということを、クリニックのスタッフ全員と共有し、患者さんに説明できるようにしておく必要もあります。
患者さんが自費診療に興味を持ったときや、疑問を感じたときにきちんと答えることが出来れば、自費診療に繋がります。
失敗しないデンタルローンの選び方

デンタルローンを導入しようにも、たくさん種類がありすぎて、どのデンタルローンにすればいいのか迷ってしますよね。
ここでは、どのデンタルローンにすればいいのか、その選ぶ基準をお伝えいたします。
分割回数はどれくらいか
患者さんによっては、月々の出費は抑えたいと思う方もいるはずです。分割回数が多ければ、高額な自費診療を受けたとしても、月々の支払が安くすみます。分割回数はなるべく60回以上のものを選ぶようにしましょう。
分割手数料が低いか
手数料を“患者さん負担”か、“クリニック負担”にするのかは、デンタルローンによって異なりますが、クリニック負担にすると、高額治療の場合、高額な手数料を負担しなくてはいけなくなるので、“患者さん負担“をお勧めします。出来れば6%未満のものがお勧めです。
クリニックの審査は通りやすいのか
どの歯科医でもデンタルローンが導入できるわけではないとご存知でしょうか。
実は、年商5千万円以下では導入不可の会社もあります。事前に確認しておくことが必要です。
患者さんの審査は通りやすいのか
患者さんの審査が通りやすいかどうかは、会社によってばらつきがあります。
いくら先生が自費診療のメリットや、お勧めをしても、審査で落ちてしまったら、患者さんの自費診療に対するやる気が一気になくなってしまいます。そうならないためにも、審査が通りやすいデンタルローン会社を選ぶ必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。自費診察率が上がらない理由には、
・先生自身が保険適用内で良いと考えてしまっている
・自費診療メニューを患者さんの目に見えるところに置いていない
・患者さんのニーズを診察の中でくみ取り、適切なタイミングで適切なメニューのご提案が出来ていない
という、潜在的なニーズを拾う機会がうまく作れていないことが挙げられます。
デンタルローンで得られる患者さんのメリットは、
- 矯正、インプラントなど保険外診療全般の高額治療を受けられるようになる
- 治療をすぐに開始することが出来る
- 返済回数が多い
- 医療費控除が受けられる
などがあります。
デンタルローンは、
- 分割回数
- 分割手数料
- 審査の通りやすさ
を比較して決めることをお勧めします。
しっかりとニーズを拾い、適切な自費診療メニューと併せてデンタルローンを患者さんにご紹介することで、患者さんの診察範囲も増え、クリニックの自費診療率も高まります。
ぜひ、今回お話したことをクリニックの経営にお役立てください。
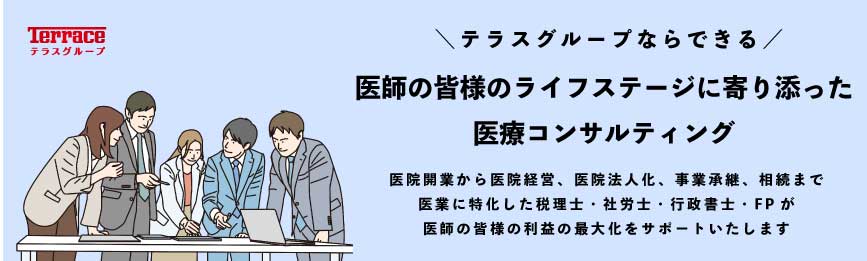
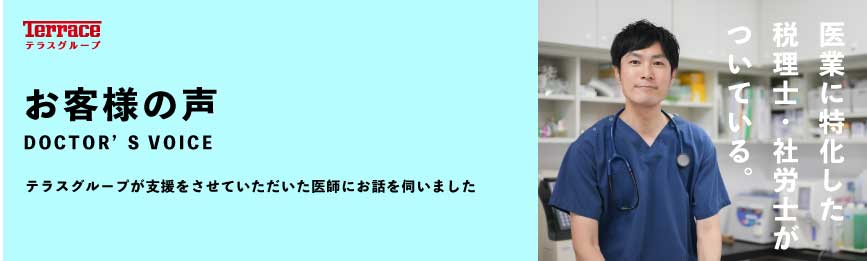


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。