医師以外でも医療法人の理事長に就くことはできるのか?


「医師や歯科医師でなくても医療法人の理事長に就くことはできるのか?」
医療法では、原則は医師の先生が医療法人の理事長に就かないといけません。
しかし、例外もあり、都道府県知事の認可を受けた場合は、非医師でも理事長に就くことが可能です。
あまり知られていませんが、何か理由があって、院長先生でなくても医療法人の理事長に就くケースはあります。
そこで、今回は医師、歯科医師以外の方が医療法人の理事長になるための要件や、注意点についてお伝えします。
医師、歯科医師以外が医療法人の理事長になるための要件

医療法第46条の6第1項では、医療法人の理事長は原則、医師もしくは歯科医師である必要があると定められています。
一方で、例外的に都道府県知事の認可を受けた場合は、非医師であっても理事長になることができるとも定められています。
【医療法第46条の6第1項】
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
では、どんな場合に非医師の方が医療法人の理事長になれるかというと、医療法人運営管理指導要綱で、次のように要件が記載されています。
医師、歯科医師でない理事のうちから選任することができる場合は以下のとおりである。
①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
②次に掲げるいずれかに該当する医療法人
イ 特定医療法人又は社会医療法人
ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人
つまり、理事長である院長先生が死亡、職務不能となった場合に、一時的に配偶者などが理事長職を代わることは認められているということです。
ただ、上記③にあるように、万が一の際に都道府県知事が必ずしも認可するとは限らず、具体的には、次の4つを満たす必要があります。
| 過去5年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人 | 次の場合は条件を満たさない ・立入検査や保健指導監査で指導を受けて改善が見られない ・脱税などの法令違反がある ・債務超過になっており経営改善の兆候が見られないこと |
| 理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人 | ― |
医師又は歯科医師の理事が理事全体の2/3以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の1/3以下である医療法人であって、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人 | 親族関係を有する者とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族関係を有する者を指す |
昭和61年6月27日以前に設立された医療法人については、右記のいずれかに該当する場合 | ア同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合 イ同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合 |
簡単にまとめると、都道府県知事の認可を受けるには、次の条件を満たすことが目安になります。
・直近5年間で立入検査や保健指導監査で指導内容に改善が見られること
・直近5年間で医療法人に違法行為がないこと
・直近5年間の医療法人の経営で債務超過に陥っていないこと
・直近5年間で赤字決算であったとしても経営改善の兆しが見られること
・理事長候補が、理事に3年以上在籍していること
・医療法人の理事の2/3以上が医師であること
・理事のうち、親族関係者が1/3以下であること
医療法人によっては、理事の2/3が医師で、親族関係者が1/3というのは、少しハードルが高い要件かもしれません。
後述するように、都道府県知事の認可を得るには厳格な審査を通す必要があります。
詳細は、医療法人の承継に詳しい専門家に相談して進めるようにしてください。
医師、歯科医師以外が医療法人の理事長に就く2つのケース

上記のことを踏まえると、医師、歯科医師以外が医療法人の理事長に就くケースとしては、次の2つが考えられます。
理事長先生が万が一の際に後継者が不在だった場合
理事長である院長先生が急逝されたり、重い病気になったりした際に、後継者が不在である場合は、配偶者などが一時的に理事長になることがあります。
非医師の方が理事長に就く理由として、最も多いケースです。
あくまで一時的な役割であり、将来的に医師の先生が理事長の職を引き継ぐことが前提となっています。
一時的に配偶者などが理事長となり、医療法人を経営することで、後継者が見つかるまで時間を稼ぐことができます。
この措置により、医療法人の解散といった事態を避け、地域医療が継続できなくなることがありません。
個人開業の医院・クリニックの場合、院長先生が万が一の際は廃院するしか選択肢がなくなります。
事業承継を考えるのであれば、医療法人化して承継をスムーズに進められるようにすることも検討しましょう。
特定医療法人、社会医療法人など公益性の高い医療法人の場合
公益性の高い医療法人である特定医療法人や社会医療法人などは、医師、歯科医師以外の人が理事長に就任できる可能性があります。
これらの医療法人は、通常の医療法人以上に経営の透明性や客観性が強く求められます。
そのため、敢えて医師ではない第三者的な視点を持つ方を理事長に据えることで、より公正で安定した法人運営を目指す場合があります。
ただ、特定医療法人や社会医療法人は、認定要件は厳格なので、これから設立する場合は注意してください。
医師、歯科医師以外が医療法人の理事長に就く際の2つの注意点

医師、歯科医師以外でも医療法人の理事長に就くことは可能です。
ただし、次の点は必ず注意するようにしてください。
都道府県知事の認可の難易度が高い
1つは、都道府県知事の認可の難易度が高い点です。
構成要件としては、理事の医師が2/3以上いなければいけませんし、親族の理事の割合は1/3以下でなければいけません。
また、先に示した「医師、歯科医師以外が理事長になるための要件」はあくまで目安です。
非医師の方が理事長に就く要件を満たしたからといって、必ずしも都道府県の認可がすぐ通るとも限りません。
しかも、要件を満たしているかどうか厳格に審査されるため、認可がおりる場合でも、申請後1年程度要することもあります。
医療法人の最終的な経営責任を負うことを自覚する

一時的とはいえ、医師、歯科医師以外の人が理事長になった場合は、医療法人の運営に関する最終的な責任を負うことになります。
常勤医や看護師などの採用や労務管理、資金繰りといった財務管理、そして医療法をはじめとする様々な法令遵守の責任など広範囲に渡ります。
特に常勤医の採用は、コネクションのある医師の先生でないと、紹介が少なくなり難しくなる可能性があります。
税理士、社労士、弁護士といった士業や専門家と常に連携し、適切な助言を得ながら慎重に法人を運営していく姿勢が不可欠です。
なお、事業承継には、親族承継とM&Aの2つの手段があります。
非医師の方が理事長に就任することで時間的な余裕はできますが、引き続きどのように承継するかについて、詳細に動き出すようにしましょう。
事業承継については、以下の記事も参考にしてください。
【まとめ】万が一の際は医師の先生以外の方が理事長に就任するのもあり
医師や歯科医師以外でも、理事長に就任することは可能です。

もし、院長先生に万が一のことがあれば、非医師の配偶者の方などが一時的に理事長となり、後継者を探すのも1つの手です。
ただ、都道府県知事の認可がおりるハードルは高い点は注意して、医院承継に詳しい専門家に相談するようにしてください。
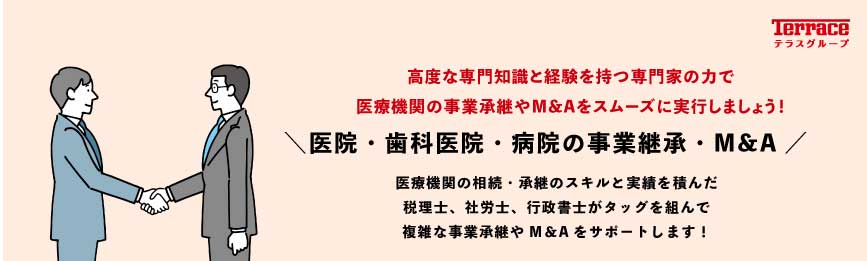
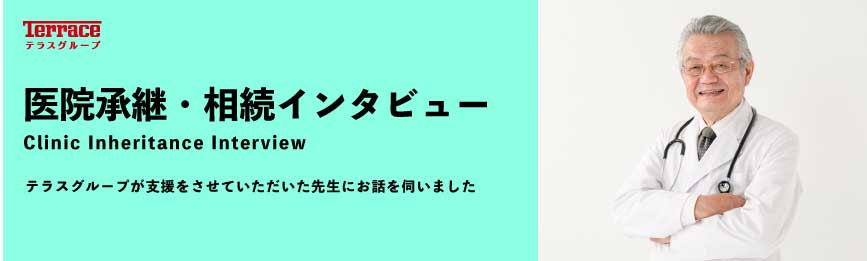


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。














