開業医が病気になったらどうする?従業員の給与や家賃・ローンは?
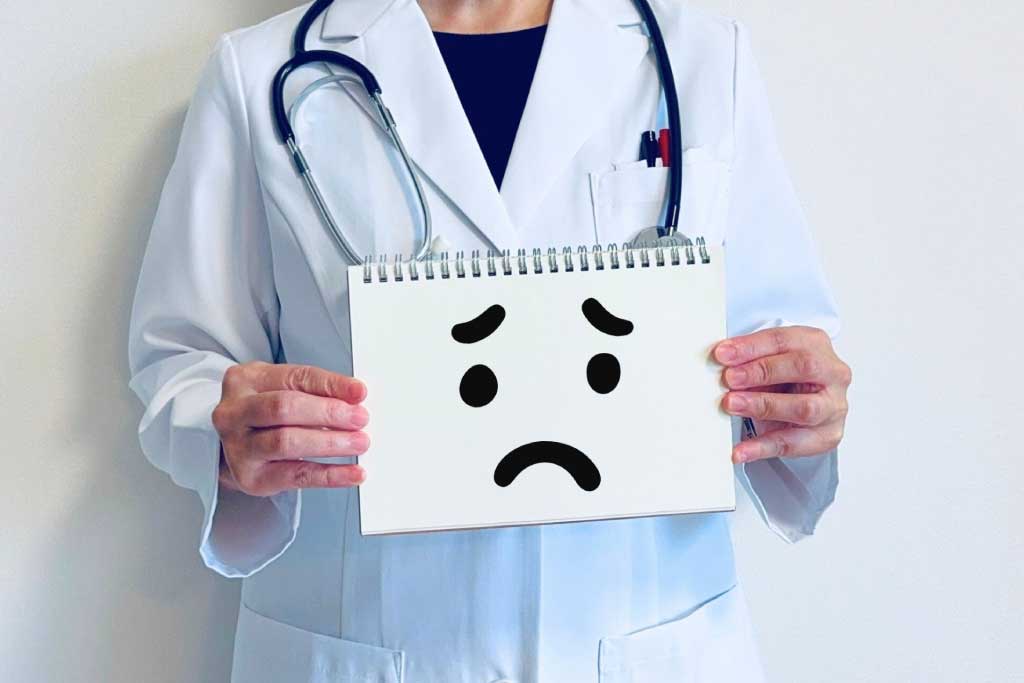
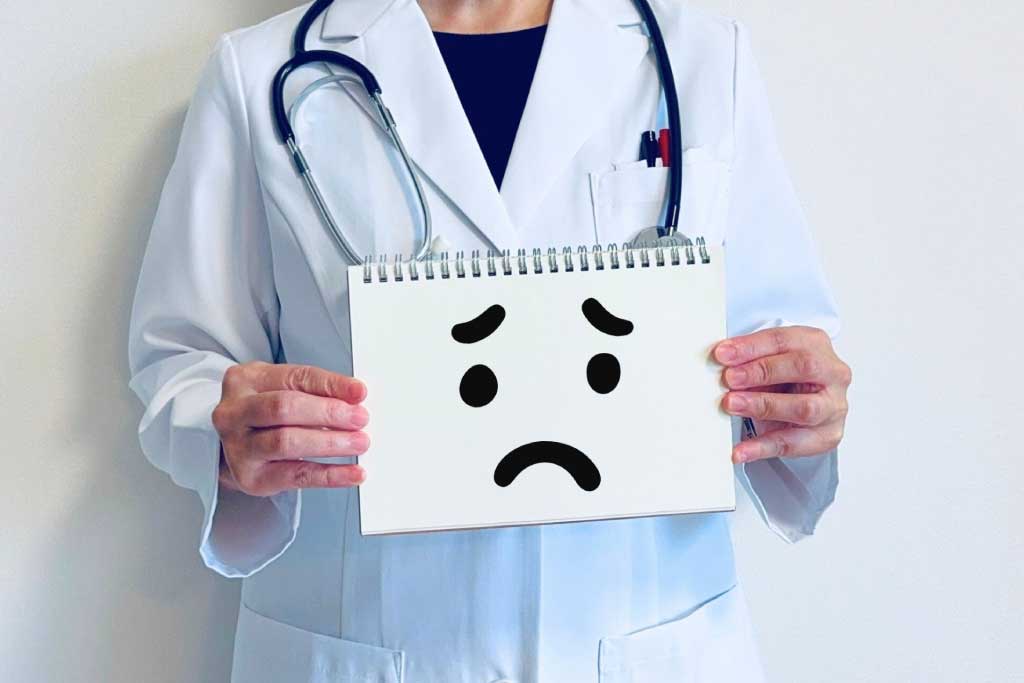
健康管理に人一倍気を付けていたとしても、病気や事故のリスクをゼロにすることはできません。
おそらく、これは日々患者さんを診療している開業医の先生なら普段から感じていることではないでしょうか?
医院開業した先生からも「自分が病気になったらどうなるのか?」「必要な保険は何か?」という相談をいただくことがあります。
開業医の先生が病気で長く働けなくなり、診療がストップすれば、クリニックの収入は途絶えてしまいます。
その一方で、従業員の給料や家賃は払い続けないといけませんし、借入金は返済しなければいけません。
また、休診中に残された従業員の対応も考える必要があります。
本記事では、開業医の先生が病気になった際に直面する具体的なリスクや従業員対応を整理し、今からできる備えをお伝えします。
開業医が病気になったら直面するリスクとは?

まずは、開業医の先生が病気になった場合に直面するリスクについて整理します。
・医業収入がゼロになる
・開業医の先生には傷病手当金が出ない
・従業員に給料を支払わないといけない
・家賃やローンなど固定費の支払いは常に発生する
大きく分けると、上記4つのリスクについて考えないといけません。
医業収入がゼロになる
開業医の先生が病気になると、長期間休診せざるを得なくなり、当然クリニックの収入が途絶えることになります。
開業医の先生は医院・クリニックの管理者になるので、長期間不在になると診療ができなくなります。
しかし、医療法上では、都道府県知事の許可を得たうえで、代診の先生を新たな管理者として診療を継続することは可能です。
【医療法第12条】
病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させることができる。
ただ、お住まいの都道府県に相談した方が良いですが、都道府県知事の許可は簡単に出るものではありません。
また、すぐに駆けつけてくれて長期間代診してくれる代診医が見つかるかどうかという問題もあります。
どちらにしても、開業医の先生が病気で不在になっているのに診療を継続することは困難です。 そのため、基本的には急病やケガで診療が長期間できなくなると、収入が途絶えてしまうことになります。
開業医には傷病手当金が出ない
医業収入がゼロになるということは、開業医の先生の収入もゼロということになります。
勤務医であれば、協会けんぽに加入しているため、傷病による休暇4日目から通算で1年6ヶ月までの期間、標準報酬月額の2/3にあたる傷病手当金が支払われます。
⇒⇒⇒【参考】全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金 」
しかし、個人の開業医の先生は、国民健康保険か医師国保に加入することになるため、傷病手当金が出ません。
先生は収入が完全に途絶えることになるため、ご自身の生活費や養育費、住宅ローンなどは、すべて貯蓄から直接切り崩すことになります。
後述するように、診療ができなくなるリスクに備えて、保険の見直しをしておくことも必要になってきます。
従業員に給料を支払わないといけない
クリニックの収入がゼロになったとしても、従業員に対する給与の支払い義務がなくなるわけではありません。これが人件費のリスクです。
労働基準法では、「使用者の都合」によって従業員を休業させる場合、休業手当として賃金の60%以上を支払うように定めています。
【労働基準法第26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
院長先生ご自身の病気による休診は、天災のような不可抗力とは見なされず、「使用者の都合」に該当すると判断されるのが一般的です。
そのため、先生は診療ができず収入がない中でも、従業員の生活を守るための人件費を支出し続けなければなりません。
家賃やローンなど固定費の支払いは常に発生する
医業収入がまったく入ってこない間も、医院・クリニックには次のような固定費が発生します。
・従業員の人件費
・テナントの家賃もしくは戸建て物件のローン
・開業資金の借入金
・水道光熱費
・医療機器のリース料 etc
そのため、手元の運転資金がまたたく間に減少することになります。
開業医の病気で休診中は従業員をどうする?

開業医の先生が病気で休診中となっている場合、資金繰りという「カネ」の問題もありますが、従業員という「ヒト」の問題もあります。
医院・クリニック休診中の従業員に対する対応についてお伝えします。
労働基準法に従い給与は払い続ける
先ほどお伝えしたように、休診中であっても、従業員に対しては平均賃金の60%以上の給与を支払わないといけません。
これは、常勤スタッフだけでなく、パートやアルバイトに対しても同様の支払い義務が生じます。
また、従業員が休診中に有給休暇を消化する場合は、休業手当を支払うのではなく、100%の給与を支払う必要があります。
なかには、従業員の生活不安を考慮して、就業規則で平均賃金の100%の休業手当を支給している医院・クリニックもあるようです。
その場合は、就業規則に従って、100%の給与を支払わないといけません。
長期間休診となると、後述するように将来に不安を感じる従業員が多くなる傾向があるので、100%支給も検討の余地があります。
ちなみに、似たようなものに休業補償(労働基準法第76条)がありますが、これは従業員の労災保険給付で、まったく別のものになります。
開業医の関係者を通じて状況を都度説明しておくこと
開業医の先生が病気で休診するようになったら、ご家族などを通じて状況を都度説明しておくようにしましょう。
いくら給与の60%以上の休業手当が支給されているからといって、残された従業員は「この状態がいつまで続くのか」「クリニックは再開できるのか」と不安を持っています。
生活への不安から転職を考える従業員も多いと考えられます。
特に働く意欲が高い従業員は、長期間の休診に不満を抱くことも十分あり得ます。
そのため、可能な限り、ご家族などを通じて現在の容態や退院・復帰時期といったことを説明するようにしましょう。
そのうえで、従業員の不安に配慮して、「今後も診療を続けたい」「皆で危機を乗り越えたい」という想いを伝えることが、信頼関係を維持するカギとなります。
休診中に、退職したい従業員まで引き止めることは無理と考えられます。
しかし、先生は診療を再開する予定で、従業員も本当は働きたいのに退職してしまうことになればもったいないことです。
上記のように適正に休業手当を支払い、従業員に配慮したコミュニケーションを取るのも1つの方法です。
医院を開業したら、万が一の可能性に備えて保険の見直しをする
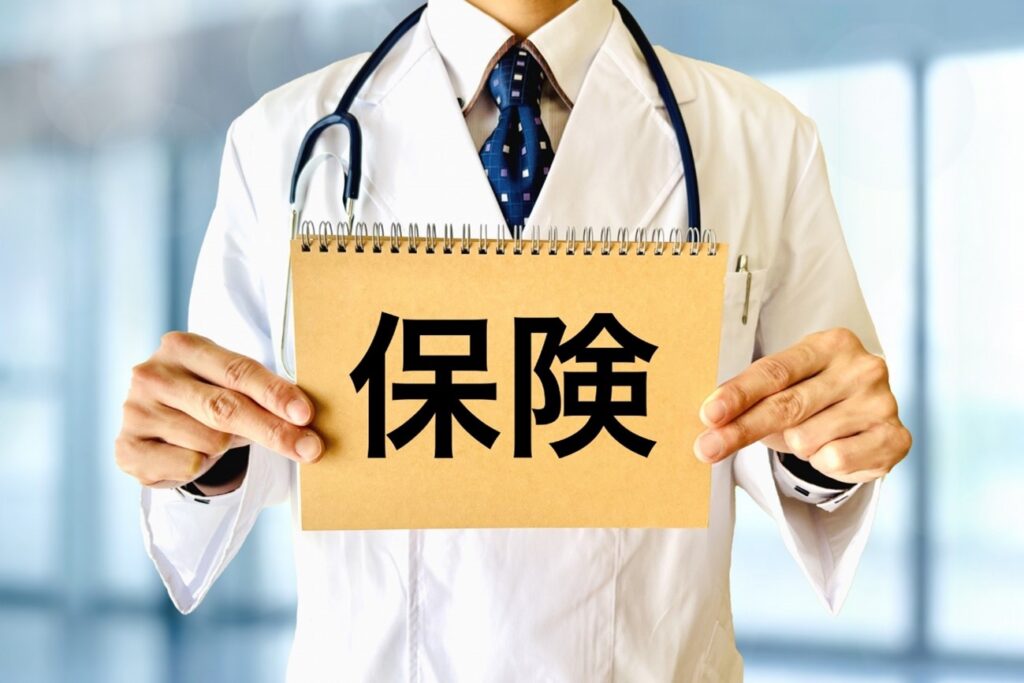
ここまでお伝えしたように、開業医になると、病気やケガで働けなくなった際に、傷病手当金などの公的補償が期待できません。
しかも、従業員の休業手当や家賃の支払い、借入金の返済などの対応もする必要があります。
そのため、勤務医から開業医になった場合は、所得補償保険などの重要性が増してきます。
所得補償保険とは、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少を補償する保険です。
所得補償保険といっても、様々なタイプがあり、開業医向けに1~2年ではなく長期間補償される保険もあります。
そこで、所得補償保険の加入・見直しのポイントについてお伝えします。
ただ、詳細については、開業医の先生のライフプランに詳しいFPなどに相談してください。
なお、医院開業したら見直したい保険は他にもあるので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
必要最低限の補償金額:医院経営の固定費+生活費で考える
所得補償保険で最も重要なのが、毎月いくら受け取るかという「保険金額」の設定です。
感覚で決めるのではなく、「万が一の際に最低限必要な支出」をシミュレーションしていくことが大切です。
具体的には、医院経営の固定費を算出します。
家賃や医療機器のリース料、従業員への休業手当など、休診中でも必ず発生する事業経費です。
従業員の休業手当は、多くは給与の60%で算定しますが、就業規則などで100%としている場合は、100%で算定します。
次に、先生ご自身とご家族の生活費を洗い出します。
住宅ローンや教育費など、プライベートで必要不可欠な支出などを洗い出しましょう。
この2つを合計した金額に、ご自身が切り崩してもいい貯蓄額を差し引いた分が、毎月カバーすべき最低限の金額です。
根拠のある補償金額を設定すれば、収入がゼロになっても貯蓄を切り崩すことなく、医業と従業員、ご自身の生活を守ることが可能になります。
免責期間:いつまで自己資金で耐えられるかを考える
免責期間は、病気や怪我で働けなくなってから、実際に保険金の支払いが開始されるまでの待機期間のことで、この期間は保険金が支払われません。
免責期間は、保険会社や保険商品によって様々で、特に長期の所得補償保険は60~365日と幅広いので、よく確認しておく必要があります。
免責期間については、先生ご自身の「自己資金(貯蓄)でどれくらいの期間、事業と生活を維持できるか」で検討します。
例えば、3ヶ月分の運転資金と生活費を貯蓄で確保できているなら、免責期間を90日間に設定することで、月々の保険料を安く抑えられます。
逆に、自己資金に不安があれば、保険料は高くなりますが短い期間を選ぶ必要があります。
ご自身の貯蓄額と保険料のバランスを考えて、最適な免責期間を選択することが肝心です。
補償期間:最長でいつまで保険金額を受け取るかを考える
補償期間は、保険金を受け取れる期間です。
補償期間は保険商品によって様々で、1年や5年といった短期的なプランから、65歳など引退年齢まで補償が続く長期的なプランまであります。
当然、保障される期間が長いほど、月々の保険料は高くなります。
選び方の基準は、開業医の先生の事業計画やライフプランと直結します。
例えば「クリニックの借入金の返済が終わるまで」「お子様が独立するまで」といった期間を目安にするのも手です。
万が一、長期間診療に復帰できないことに備えるならば、保険料は高いものの長期のプランが安心です。
ご自身が抱えるリスクの大きさと、支払える保険料のバランスを考えて選択しましょう。
補償範囲:どの疾患まで補償できるか確認する
補償範囲を確認して、どの疾患に対応しているかを確認しておきましょう。
例えば、所得補償保険の多くは、うつ病などの精神疾患を補償の対象外としています。
最近こそ精神疾患も保障する商品が増えてきましたが、その場合でも補償期間が短く、保険料が割高になることがほとんどです。
このように、どの疾患まで対象となっているかはよく確認しておく必要があります。
【まとめ】医院開業したら万が一の備えが必要になる
以上、開業医の先生が病気になって診療できなくなった場合のリスクと、具体的な備えについて解説しました。
医業収入が途絶える一方で、人件費や家賃、借入金などの支払いは続き、残された従業員の不安にも配慮する必要があります。
どんなに健康第一で考えても、病気で診療できなくなる可能性はゼロではありません。
医院を開業したら、所得補償保険の見直しなど、万が一の備えについて見直しておく必要があるでしょう。
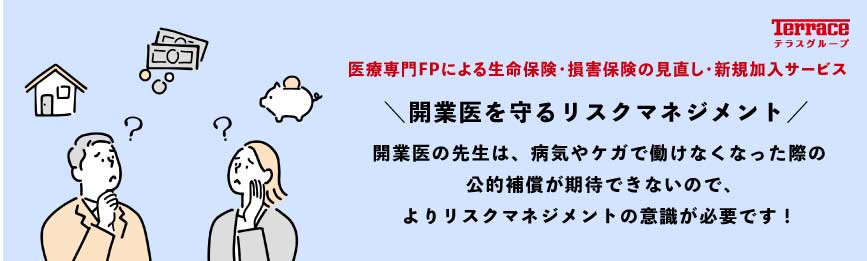
税理士法人テラスのグループ法人であるFPテラスでは、開業医の先生に合った生命保険のご提案ができる医療専門FPが在籍しています。最新の保険商品の知識も踏まえ、今後のライフプランや事業状況に応じて、医療専門FPは適切な保険戦略を提供します。保険税務に詳しい税理士も在籍しているので、ぜひご相談ください。
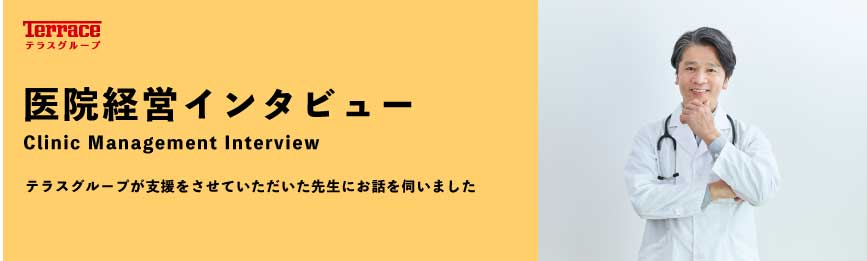
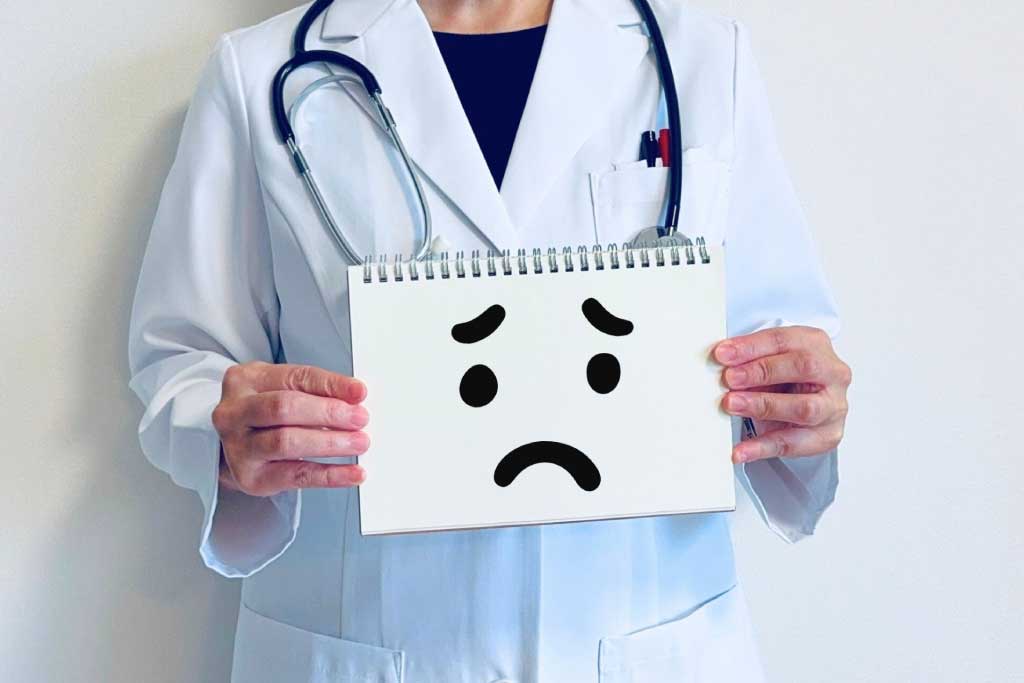

監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。














