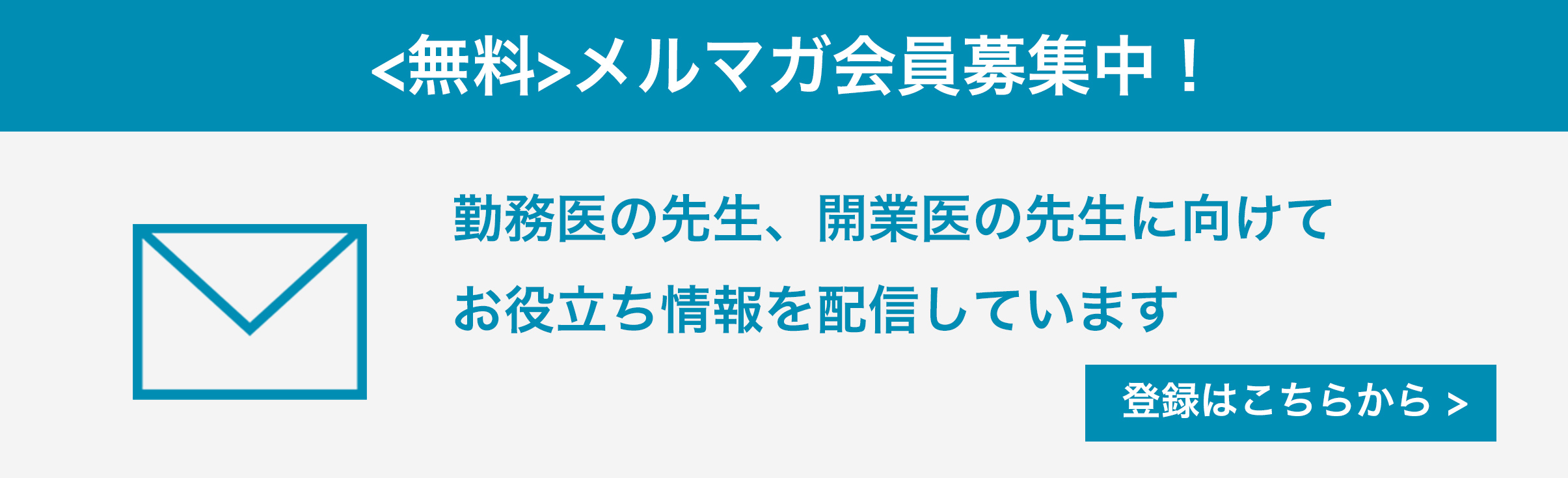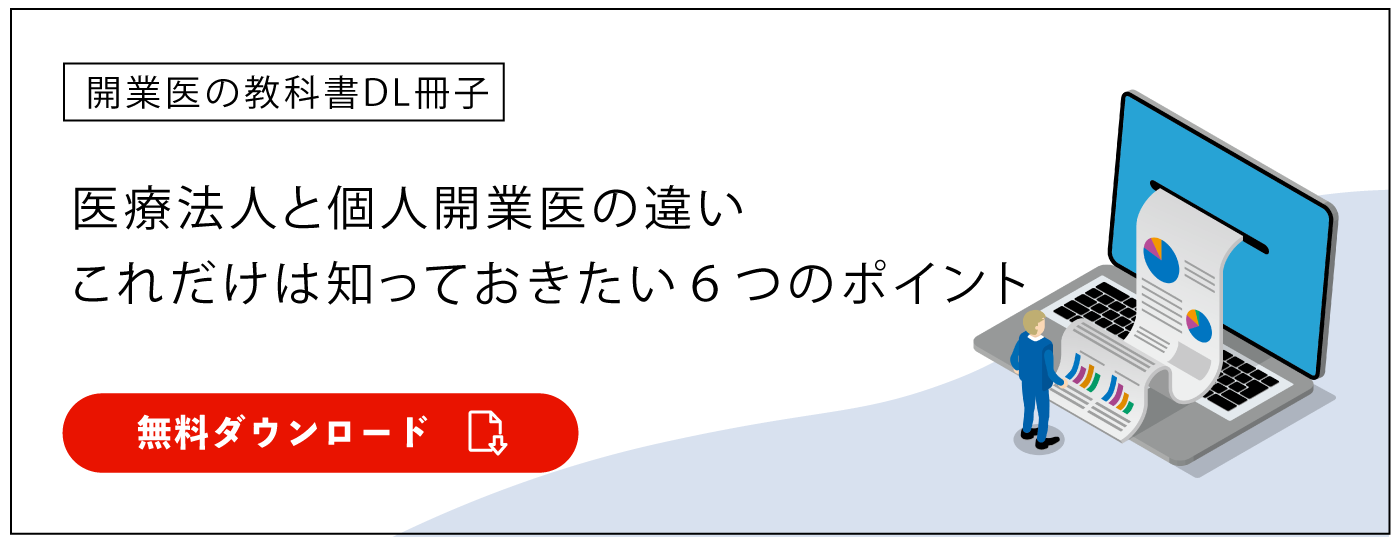【5分でわかる】相続問題でよく聞く「寄与分」「遺留分」とその関係は?


遺産相続の場面では、専門用語が多くて、わかりづらいことがあります。
今回は、遺産相続の場面で、比較的よく出てくる「寄与分」「遺留分」について解説します。
「寄与分」と「遺留分」の意味は次の通りです。
| 寄与分 | 相続財産の維持・増加に寄与した法定相続人の相続分を優遇する制度 |
|---|---|
| 遺留分 | 法定相続人に最低限認められる遺産取得分の権利 |
遺産相続では、最低限遺留分に相当する財産を相続人に分配することになります。
例えば、被相続人Xの長男Aに1/4の遺留分が認められれば、最低でも1/4以上の遺産を相続できる権利があるということです。
しかし、Xの次男Bが寄与分を主張する場合、Bの遺留分が侵害され、1/4の相続を受けられない問題が発生することがあります。
そこで、本記事では、寄与分と遺留分について詳しく解説し、寄与分と遺留分が衝突する事例についても紹介します。
寄与分|相続財産の維持・増加に寄与した分だけ相続を優遇できる制度

まずは「寄与分」について詳しく解説します。
例えば法定相続人が2人の兄弟だったような場合は「平等に1/2ずつ」という形になります。
これで相続人同士納得すれば良いのですが、次のような場合は兄弟のうち片方が納得しないこともあります。
・長男の方が被相続人である親と頻繁に会っていた
・長男の方が家業を積極的に手伝っていた
・長男の方が親を献身的に看病した
このような場合、長男の寄与分は認められるのでしょうか? 寄与分の定義を詳しくお伝えしながら解説します。
「寄与分」が認められる要件とは?
寄与分については、民法上に定義規定はないものの、冒頭でお伝えしたとおり、一般的には次のように考えられています。
『相続財産の維持・増加に貢献(寄与)した相続人の相続分について、他のそうでない相続人よりも優遇しようとする制度』
つまり被相続人に対して貢献度の高い相続人に対して寄与分を認め、法定相続分に上乗せするということです。
しかし、頻繁に被相続人を手伝っていたり、一緒に被相続人と住んでいたりすれば寄与分は認められるのか? と言われればそうでもないようです。
「寄与分」については民法904条の2に次のような規定がありますので抜粋します。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
引用元:民法904条の2
この規定の解釈では、寄与分が認められるためには、少なくとも次の3つの要件を満たす必要があると言えます。
- (1) 相続人の行為が特別の寄与といえること
- (2) 被相続人の財産が維持または増加されたこと
- (3) 寄与行為と財産の維持または増加に因果関係が認められること
(1)の「特別の寄与」とは、こちらも民法上の定義規定はないですが、一般的に次のように説明されています。
『被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献』
これはどういうことかというと、配偶者や親族間には相互扶助義務があります。
【民法752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
【民法第877条】
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
「通常期待されるような程度の貢献」とは民法752条、877条の範囲内の相互扶助義務になります。
この範囲内の相互扶助では通常の相続評価を超えることがなく、寄与分は認められないことになります。
寄与分が認められた場合の相続額の計算方法
法定相続人の寄与分が認められた場合の相続額の計算方法は、下記のようになります。
寄与分がある人の相続額=(遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
寄与分がない人の相続額=(遺産総額-寄与分)×法定相続分
この計算式によって得られた寄与分のない人の相続額が遺留分を下回る場合に、遺留分侵害額請求と衝突することが想定されます。
この点については後述します。
寄与分が認められる事例とは?

民法上の規定を超える特別な貢献があって寄与分が認められるということなのですが、具体的には次のようなものです。
被相続人の家業を無償で手伝っていた場合
被相続人の家業に対して、ほぼ無償に近い形で貢献して被相続人の財産増加に寄与していれば、寄与分が認められることがあります。
「被相続人の財産増加に寄与する」という条件がありますから、一緒に被相続人と住んで家事を手伝っている場合については、寄与分は認められないでしょう。
また、こういったものは農業や商工業が典型例となるので、被相続人が開業医の先生だった場合はほとんど当てはまらないと思われます。
金銭等を被相続人に出資していた場合
典型例としては、相続人である妻が婚姻後も共働きを続け、被相続人の夫名義で不動産を取得した場合が該当します。
その場合は自分が持っている資産を被相続人に対して提供したことになるので、寄与分が認められることがあります。ローンの返済のために金銭を提供していたような場合も寄与の対象になります。
老人ホームへの高額な入居金を被相続人において負担したなどの場合も該当します。
ただ、例えば開業医の妻がクリニック経営のために金銭を出資したような場合は原則として寄与分は認められません。
療養看護をしていた場合
相続人が被相続人の療養看護を行い、看護の費用の支出がなかったような場合は、寄与が認められることがあります。
大きく分けると療養看護は「病気の看護」と「老親の看護」に区別されます。
「老親の看護」は寄与が認められやすいと言われていますが、介護保険導入によって寄与分が認められにくくなっている現状があります。
なお原則寄与分は法定相続人にしか認められないのですが、相続法改正により例外的になったのが「長男の嫁の療養看護」です。
長男の嫁は基本的には法定相続人ではないのですが、療養看護による寄与が認められた場合、特別寄与料を請求することができます。
被相続人の財産を管理していた場合
・被相続人の財産管理を行い、「管理費用の支出を免れた場合」
・被相続人所有の土地の売却の際に売却代金を増加させた場合
が該当します。火災保険料、修繕費、公租公課などの実際の費用を負担した場合には実際の負担額が寄与分に該当します。
寄与分に関するケーススタディ

それでは、次のような事例で寄与分が発生するかどうかを見ていきましょう。
【事例】
被相続人である開業医の先生が亡くなり、長女、長男、次男で法定相続分を分配することになりました。
・長女は毎週実家に帰って非相続人の面倒を見ており、入院した際はお見舞いに行って看病していました。
・長男はほとんど実家に帰るようなことはなく、被相続人の面倒はほとんど見ていませんでした。
・次男は被相続人の買ったアパートの管理を任されていました。ただ不動産管理業者との事務連絡だけで、ほとんど業者に任せっきりでした。
そこで本来であれば1/3ずつ平等に分配されるところ、長女と次男が寄与分の主張を始めたのです。
しかし結論からいくと、このようなケースでは寄与分が認められないのではないかと考えられます。
まず長女の場合は療養看護に該当するかどうかが争点となるでしょう。しかし、被相続人は要介護認定というわけではなく、介護の必要性が高かったわけではありません。
療養介護の寄与は介護の必要性があるにも関わらず、業者に依頼せずに自分で介護していたような場合に認められます。
ですから、被相続人が入院して、長女が病院に行ってトイレに付き添った程度では認められないでしょう。
また実家に帰って被相続人と一緒に過ごした程度では、通常の扶助行為の範囲内とみなされるので、こちらも寄与分の対象とはならないと思われます。
次男については、財産管理に該当するかどうかが争点となりますが、こちらも寄与分は認められないでしょう。
不動産管理業者と契約して管理費用等を支払っているので、次男によって被相続人の財産が維持・増加したとはみなされないからです。
遺留分~法定相続人に認められる最低限の遺産取得分~

それでは、今度は遺留分についてお伝えします。
本来、相続財産をどのように処分するかは、被相続人の自由というのが大原則です。
しかしそれでは相続人の間で不公平が起きる可能性があります。そこで相続人の間での公平を図るのが「遺留分」制度です。
「遺留分」と「遺留分侵害額請求」
冒頭でもお伝えしたとおり、「遺留分」とは、被相続人と一定の関係にある法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分の権利のことを言います。
遺産相続が起こったとき、基本的には遺言書がなければ法定相続人が法廷相続分に応じて相続するのが原則です。
しかし、被相続人は遺言書によって特定の相続人や遺贈という形で第三者に多くの相続財産が与えることが可能です。
そうすると、他の相続人は遺産をほとんどもらえないという事態が発生します。
例えば、被相続人が土地と建物を所有して、妻と一緒に住んでいた状態で亡くなったとします。
その場合、被相続人は「土地と建物を愛人に遺贈する」と遺言に遺せば、遺言書通りに愛人のものになってしまいます。
その場合、妻は家から出ていくか、住み続けるにしても家賃などの対価を愛人に支払わないといけません。妻にとっては酷な状況です。
このような場合に、妻は本来相続されるべき「遺留分」を取り戻す権利が出てきます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
【民法第1046条】
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分を主張できる人とは?
遺留分侵害額請求、つまり遺留分を主張できる人は、「配偶者」「子」「直系尊属」に限られています。つまり、被相続人の兄弟姉妹は含まれないので注意が必要です。
遺留分の割合は?
民法第1042条を抜粋すると、次のように記載されています。
【民法第1042条】
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
つまり、直系尊属のみが相続人であれば、遺留分は法定相続分の1/3、それ以外の場合は法定相続分の1/2ということになります。
(1)被相続人の妻、長男、長女で遺産を相続する際の法定相続分と遺留分の関係
| 法定相続分の割合 | 遺留分の割合 | |
|---|---|---|
| 妻 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 長男 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
| 長女 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
(2)被相続人に子供がなく、配偶者と父母で遺産を相続する場合
| 法定相続分の割合 | 遺留分の割合 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2/3 | 2/3×1/2=1/3 |
| 父 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
| 母 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
(3)被相続人の子供がなく、配偶者がすでに死亡しており、父母のみに遺産を相続する場合
| 法定相続分の割合 | 遺留分の割合 | |
|---|---|---|
| 父 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
| 母 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
※この場合、被相続人に兄弟姉妹がいた場合でも、法定相続分、遺留分ともになし
遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害額請求の時効については、民法第1048条で次のように定められています。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。引用元:民法第1048条
「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。
これはあくまで「請求」なので、1年以内に履行されなくても時効消滅されないということです。
「寄与分」と「遺留分」の衝突する場合のケース

遺産相続では最低限遺留分に相当する財産を相続人に分配することになりますが、その遺留分を侵害するほどの寄与分を主張するケースもあります。
つまり、遺留分侵害額請求に対して寄与分を主張してきて衝突するようなケースです。
例えば2人の子がいる被相続人が、上記の療養看護や財産管理などを理由に遺産総額の全額を長男に与える遺言を遺して死亡したケースです(被相続人の配偶者はすでに死亡しているものとします)。
結論から述べると、次男が納得せずに遺留分侵害額請求をしてきたら、長男は寄与分を理由に拒否するのは難しいでしょう。
つまり、このケースでは、次男は1/2×1/2=1/4の遺留分相当の相続財産を受け取れるのではないかと推測されます。
というのも、遺留分の基礎となる相続財産については寄与分を控除するとは定義されていないためです。
しかし、長男の特別寄与がはっきりと認められていたような場合が別です。その場合は、次男の遺留分侵害額請求は認められないでしょう。
理由としては遺留分減殺請求の対象が、民法第1046条で明確に遺贈と贈与に限っているためです。
このように「寄与分」と「遺留分」の衝突に関しては判断が難しいケースになるので、詳しいことは弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
【まとめ】寄与分と遺留分の問題は相続トラブルの元に
以上、遺産相続のなかの「寄与分」と「遺留分」についてお伝えしました。
本記事のように、寄与分と遺留分が衝突すると、相続トラブルが起こりやすいので、早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
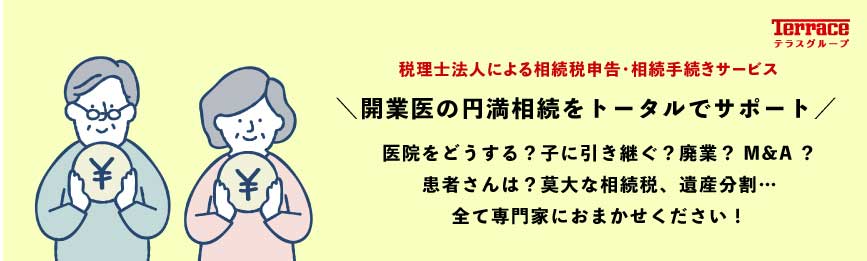



監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。