小児科クリニックの現状と財務・経営戦略


はじめに
近年は小児科の数も減っているようです。全国の小児科の数は22,000院ほどと、平成20年ごろの25,000院と比較しても10%以上減っています。この傾向は平成時代になってからずっと続いています。
小児科の減少の原因は子供の数の減少、小児科医の激務傾向などから、小児科医を目指す方が単純に減ってその結果病院の数も減っているのかなと思われます。
小児科医の年収は開業医で2,800万円から3,000万円程度、勤務医で1,600万円程度から1,800万円程度と言われています。世間一般のサラリーマンで働いている方と高め、内科医などよりも高めの傾向になっています。
単純に子供の数が減れば病院間の淘汰が始まりますので、どこかの病院や診療所は生き残れなくなります。ただ小児科という特性上、親もしくは祖父母の方がちょっとした風邪でも子供を病院に連れていきます。ある一定のニーズが小児科にはあるということに疑いの余地はありません。
小児科の病院や医院は今後も減っていくのではないかと思われますが、小児科医の年収はある程度高いところで保たれるのではないかと思われます。
小児科クリニックの患者数

小児科1診療所あたりの平均患者数は1日あたり55名から60名程度となっています。診療所によって、この値を大きく超えるところ、全く届かないところが出てきます。ただ地域的に見ていくと、だいたいこのあたりの数字に落ち着いているところがほとんどとなっています。
一般的に、小児科は寒い季節ほど患者数が増えて、暖かい季節ほど患者数は減ります。寒い季節になるとインフルエンザの予防接種なども含め、多くの患者さんが来ます。夏は風邪を引きにくくなることもあり、小児科の来院数は全体的に少なくなる傾向があります。
また夏休み・冬休みなどの時期に入ってくると、小児科の患者さんは減る傾向にあります。園児や小中学生などのお子さんが、学校に行かなくなることで風邪を移されなくなるからです。この点から、学校に行かない、集団生活を行わないということは風邪をひきにくくなる、すなわち小児科に行く患者数が減るという相関が分かってきました。
ちなみに内科の1診療所・1日あたりの来院数も平均するとだいたい60名前後と、小児科とあまり変わらないというデータが揃っています。大病院は別として、医師数名程度の診療所やクリニックだと1日の患者数が60名程度・月1,300名程度が経営をしていくための目安になってくるのかなと思われます。
病院は一般に日祝は休み・土曜午後休診・他に週の中間の木曜あたりを休診にしているところもあります。おおよそ週5日程度の診療を行っているということを考えていくと月に換算すると22日弱になりますので、だいたいこの程度の数字になってきます。
小児科は子供だけのものではない?
小児科は小中学生くらいまでのお子さんしかかかることができないのかなと思われがちですが、実際にはそうでもありません。小児科でも全体の数%程度は大人の患者が小児科にかかっています。これは小児科以外の他科も標榜している小児科医院があることや、引率の母親や祖父母などの保護者の方が一緒に受診をするケース、また地方などに行くと一般病院が近くになく小児科のみが近くにあるなどの理由で、年配の方が小児科にかかってしまうケースも中にはあるとのことです。
小児科だからといって乳幼児・小中学生のようなお子さんしかかかることができないというわけではありません。風邪などの場合、ご家族も一緒に罹患してしまう状態は普通の流れでしょう。子供だけではなく様々な年代のご家族の診療も一緒にできる事は、小児ではないご家族にとってもありがたく、病院側にも収益が入りますので双方にメリットが出てきます。
保険診療と自由診療

小児科にも、高熱が出た、お腹が痛いなどの病気に対しての処置をしていく保険診療と、予防接種や乳幼児健診などの自由診療の部分があります。一般に規模の大きい病院ほど自由診療の割合が高くなります。
地域の大病院になると、3割程度の収入が自由診療になっているところもあります。ただ個人医が行っているクリニックになってしまうと、自由診療の割合は5%から8%程度とだいぶ少なくなっています。
小児科の収入
収入=患者数×客単価に診療報酬の点数が比例してきます。患者数が1割増えても競合が年間数%程度増えていきます。さらにクリニックの場合は客単価が稼げません。さらに診療報酬が数%程度減少します。こうなってくると収入を維持するのは大変になります。
小児科の診療所の場合は月平均の患者数を1,300、客単価が5,000円程度になっています。そうなってくると診療所に入ってくる1年の収入は5,000円×1,300名×12か月=7,800万円程度になります。小規模なところほど保険診療の割合が高く大きな規模の医院ほど自由診療の割合が高くなります。
小児科の経費

今までは収益の面でみてきました。今度は医療スタッフや設備などのコストの面を考えていきます。
まず小児科クリニックなどを経営するには建物が必要です。建物を買うか、借りるか。またその費用を一発現金で払うか、ローンで払うかという問題が出てきます。そこで購入、一発現金以外の場合は毎月の建物のローンが発生します。このローンの額は地方/都市部。駅近く/郊外などによってかなりのばらつきが出ます。おそらく最低でも月10数万円・高いところは100万円近くになってもおかしくはありません。また小児科になってくると待合室や入口をお子さんやベビーカーが入りやすくするための工夫をする必要があります。部屋数も多くかかりますので、他の科よりも建物にかかるコストは高くなってきます。
また人員面でも、看護師などのスタッフを確保する必要があります。事務員さんなどは奥さんや身内の方に手伝ってもらうことも可能ですが、それでも多少の人件費はかかってしまいます。いずれにしても固定費もそう簡単には減らせません。この収入が減る・固定費が変わらないというところが病院・診療所経営の難しいところでもあります。
収益=収入ーコストで計算できます。前年度の収入が年間7,800万円・固定費などのコストが6,000万円であれば7,800‐6,000=1,800万円手元に残ります。
小児科の場合は安定している医院では収入はあまり変わりません。コストは人件費は看護師の求人でお金がかかるかもしれません。建物のローンが徐々に上がる可能性があります。備品のローンの返済が順調であればあまり問題はないのですが、ここを減らせないと難しくなります。
ただ競合する病院や診療所の数は減っています。この点からも、小児科の経営に関しては他の科に比較しても比較的順調なところが多いのではないかなという気がします。
小児科は他の医院との連携がしっかりと取れているかがご家族の信頼のカギになる
小さい規模の小児科の場合は、お子さんのすべての病気の診療をするということができなくなります。たしかにお子さんでもまれにかかってしまう、がん・心臓病などの大きな病気になってしまうと、小児科医院では対処ができません。
そこまでではなくても小児科・それぞれの医師にとっても得意分野・不得意分野があります。このようなケースで他の医院との連携がしっかりと取れているかも、ご家族の信頼につながってきます。お子さんの病気というと引率者のご家族もナーバスになることが予想されます。そのような時に信頼できる病院を紹介できるかなども、小児科医の腕となります。意外に重要なところかもしれません。
小児科は患者さんである子どもと同様に、保護者とのコミュニケーション、信頼関係が大切に
小児科はお子さん1人だけで来ることはあまりありません。母親・父親・祖父母・叔父叔母などの親族の方が一緒に来ることが多いです。お子さんの体調が悪くなると、親は心配になります。先生に不安をぶつけてくるご家族の方もいます。そのような患者さんへの対応をどうしていくか。
また小さいお子さんが病気になってしまうと、家族も移されてしまうことがよくあります。特に仕事をしている保護者の方々など、保育園や幼稚園、学校には行けるのか?休むべきなのか?いつまで休むべきなのか、これは休まなくてはいけない状況なのか等、患者さんであるお子さんとのコミュニケーションだけではなく、看護者とのコミュニケーションも大事になってきます。
小児科は個々のお子さんの診療時間は長めになる傾向があり、それが働く保護者からの課題にもなっています。また、看児の受診に際し、健康な兄弟を同伴させざるを得ない状況も生じますので、予約システムなどの積極的利用により待合室にいなくてはいけない時間を減らすことが出来ることや、感染症に罹患している看児と、ワクチン接種目的などの非感染症罹患の患者との導線をうまく分けるなどの工夫をクリニック構築に施すことは、保護者に支持され、集患にも大きく繋げられるはずですので、是非検討されてみてはいかがでしょうか。
小児科クリニックのデータ作成
| A医院(分業) | |
| 実患者数 | 1374 |
| 延患者数 | 3297 |
| 請求点数 | |
| 平均来院回数 | 2.399 |
| 診療単価 | |
| レセ単価 | |
| 初診料 | 276(20.0%) |
| 初診:機能強化加算 | 2 |
| 初診:乳幼児夜間加算 | 6 |
| 初診:夜間・早朝等加算 | 8 |
| 初診:乳幼児加算 | 120 |
| 初診:妊婦加算 | 8 |
| 再診料 | 823 |
| 同日再診料 | 2 |
| 電話等再診 | 8 |
| 再診:乳幼児夜間加算 | 2 |
| 再診:夜間・早朝加算 | 1 |
| 再診:休日加算 | 4 |
| 再診:乳幼児加算 | 432 |
| 再診:妊婦加算 | 2 |
| 時間外対応加算1 | |
| 時間外対応加算2 | 8 |
| 明細書発行体制加算 | 3 |
| 地域包括診療加算1 | |
| 地域包括診療加算2 | |
| 認知症地域包括診療加算1 | |
| 認知症地域包括診療加算2 | |
| 外来管理加算 | 854 |
| 調剤技術基本料 | |
| 血液学的検査判断料 | 48 |
| 免疫学的検査判断料 | 108 |
| 尿・糞便等検査判断料 | 25 |
| 微生物学的検査判断料 | 100 |
| 生化学的検査判断料 | 18 |
| 呼吸機能検査等判断料 | 182 |
| 外来迅速検査加算 | 7 |
| 単純撮影 | 18 |
| CT撮影 | |
| 超音波検査 | |
| 胃・十二指腸ファイバースコピー | |
| 骨塩定量検査 | |
| 心電図 | |
| 負荷心電図 |
税理士法人テラス、テラスグループでは、経験豊富な税理士、社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、事業用物件の専門家などが結集してワンストップで医院開業支援を行っています。
医院開業準備における税務・労務・法務業務のすべてをワンストップで進めることができますので、ぜひご相談ください。
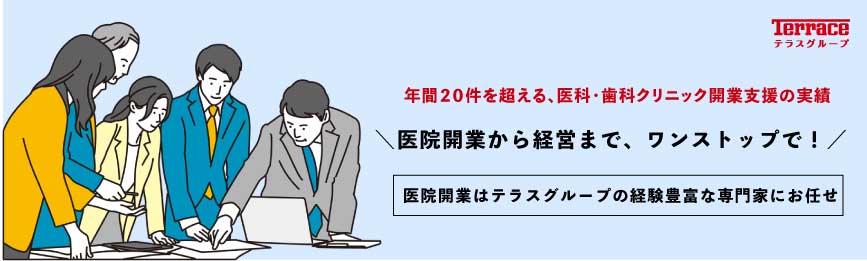
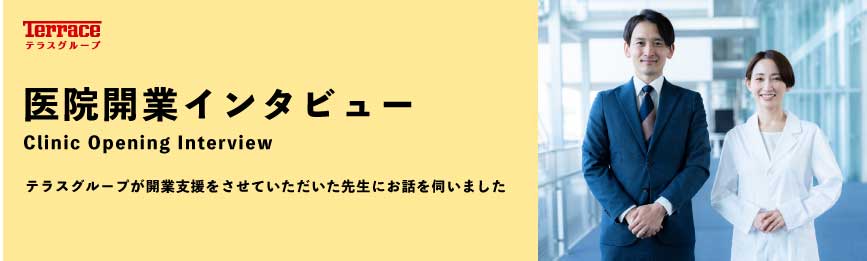


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。












