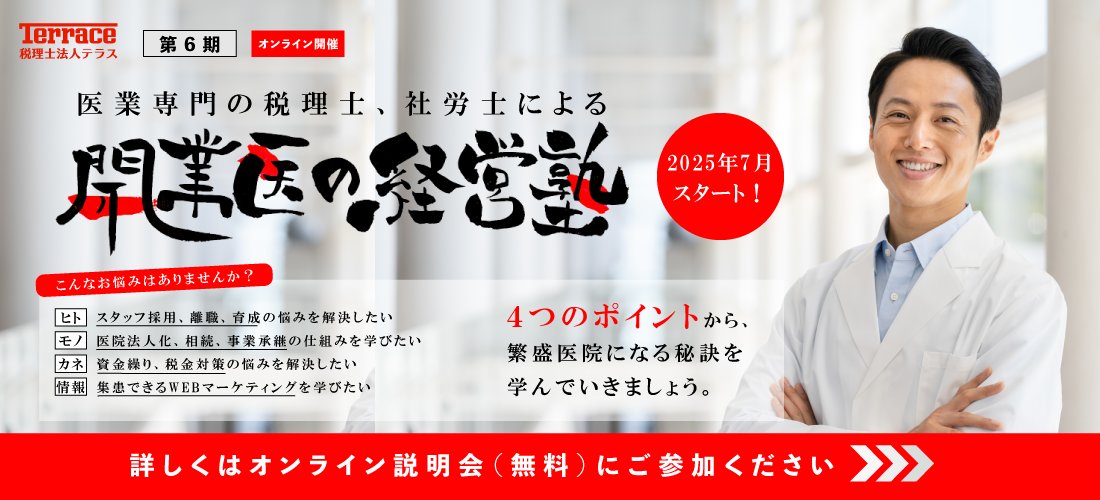クリニック・医院の現状と財務・経営戦略【総論】


はじめに
今後日本は超高齢化社会を向かえます。2050年ごろにはその割合が40%弱程度になるともいわれています。それだけでなく、子どもや若者などの若年人口はどんどん減っています。
実は平成初期の1990年ごろから若者の人口は減っていました。これからはその1990年前後の方が、結婚・出産などをしていく世代の中心になります。基となる親世代の人口が少なくなっているのですから、若者の人口がますます減っていくことは不可避です。
そこに高齢者がどんどん増えていきます。これからの日本を担う若者や中堅世代の人口と高齢者の人口比がどんどん縮まっていくわけですから、経済などを含めたいろんな面で厳しくなっていくことは容易に想像できます。
特に高齢者が多くなっていくと医療費は増えていきます。今までは負担の少なかった高齢者の方も、保険診療で2割・3割は当たり前の時代になります。国の負担していく医療費の額も増えていくことが予想されます。
クリニック・医院の経営戦略

クリニックの場合は、脳神経外科・内科・神経内科・整形外科・美容外科・眼科・耳鼻咽喉科・胃腸科・整形外科・産婦人科・歯科など様々な専門の科があります。またクリニックの場所・診療実績などによっても、経営面で視界良好なクリニックもあれば、そうではないクリニックも多くあるものと思われます。
クリニック経営において確実なところは2つ、1つは高齢化社会によって診療報酬の点数の減少があること、そしてもう1つは都市部のクリニック経営は苦戦する可能性が高いということです。
診療報酬の点数の減少は、病院にとっての直接の収入を失うことになります。多くのクリニックでは患者さん1人あたりの単価が下がります。患者さんの増加によってカバーできるところもありますが、経営の為には患者さんをたくさんさばく必要があり、仕事自体は忙しくなります。比例して医師や看護師の負担も増えていきますので、難しい問題になります。
クリニックの医師は開業医であって、院長を兼ねていることも多いので、経営面と診療を両方行っていくことにもなりますので、さらに難しい問題にもなってきます。
都市部のクリニック経営は苦戦する可能性が高いということについて、都市部には病院だけでなく多くのクリニックがあります。都市部に在住している方には選択肢が増えるのでとてもよいことなのですが、経営するクリニック側にとっては競合が次々に来るのでたまったものではありません。
都市部の新設クリニックの5院に1院程度は、3・4年で経営難によって閉院してしまう可能性が高いという想定があります。都市部のクリニック新設には土地や建物などの不動産、看護師や事務員などの医療スタッフ、診察や手術をするための器具などが必要になり、最低でも数千万円はかかってきます。その費用は借金で賄うことはできますが、いずれは病院経営を軌道に乗せて収入や収益を上げていくわけです。それができなければ閉院・廃業という形になります。
都市部の多くの地域はクリニックが乱立しており、競合が多い中で、経営の為には患者さんの取り合いが発生します。医療技術だけではなく、接遇やサービス、利便性などにより他院との差別化を行い、勝ち抜くことが求められます。
この点において、競合が少ない地方ではまだクリニック経営で勝ち抜ける可能性が都市部よりは多いとなります。潜在的な患者数は都市部ほどではなく、向かう敵は過疎化とはなりますが、患者さんからの選ばれやすさという点からの経営の難易度は競合は少ない地方の方が低くなります。
競合との差別化の強化や、患者さんに選ばれる医院にならなくては経営が成り立たないというプレッシャーが都市部よりは生まれにくいなど、地方での開院は都市部よりは有利な点が多くなっています。そのような状況下において、接遇の差や、他院との差別化、都市部に負けない高いサービスを付加することで、医院経営を成功させられる可能性はより高まります。
クリニック経営は、科によっても有利不利が出てきます。産婦人科・小児科などは今後クリニックが減少していく方向にあります。内科も志す医師の数が減っているようで、あまりクリニックを増やせない実情などもあるようです。また眼科などは小さい施設で行うことができ、手術が多くなりますので、比較的収益が高くなります。美容整形外科も自由診療で、クリニック自身で価格を決めることができますので、これらの科は比較的経営をしていく上では有利な科になっているのが現状です。
競合が多く参入がしやすい内科・整形外科・歯科などは、クリニックも供給過多傾向で、今後も大きな収益を伸ばしにくい状況があります。内科は診療報酬の点数の減少や入院ベッド数の問題、整形外科はリハビリ施設の問題、歯科はコンビニよりもはるかに多い数が存在していますので、患者さんの取り合い、すなわち経営の難しさが問題になっています。
歯科医の3分の1程度は新人・若手社員クラスの年収しかないという状況にもなっています。歯科はクリニック経営を行う以前の問題かもしれません。開設する医院数よりも閉院数の方が多いのではないかというくらいの危惧さえ出てきます。
とにかくクリニックの経営戦略は地域・科によって大きく異なりますので、一つの答えはが見出しにくい状況ともいえます。
クリニック・医院の収入

クリニックの収入は患者数×客単価に診療報酬の点数が比例してきます。後期高齢者の数が多いということは診療報酬・保険収入に頼る部分が大きくなります。この部分は今後も下げていくのではないかと思われますので安心はできません。
クリニック1軒あたりの平均患者数は50人・客単価は5500円程度になっています。従って、クリニックに入ってくる1年の収入は7260万円程度となります。この数字は診療しているクリニックの科や地域によっても異なりますが、一般的に地方の方が収入や収益は高くなる傾向があります。また自由診療の多い美容整形外科・眼科・競合の少ない産婦人科などは収入面では高めになってきます。
ただ参入障壁が低く競合の多い内科・整形外科・歯科などでは収入が取りにくくなっています。収入が取りにくいということは収益も取りにくく、経営面では苦戦をしてしまう傾向になります。
また都市部のクリニックは競合が多くなるので、新設医院などは収入が思ったほどいかないというケースも多く出てきます。
クリニック・医院の経費

今までは収益の面でみてきました。今度は医療スタッフや設備などのコストの面を考えていきます。
まずクリニックを経営するとなると建物が必要になります。建物を買うか、借りるか。またその費用を一発現金で払うか、ローンで払うかという問題が出てきます。そこで購入、一発現金以外の場合は毎月の建物のローンが発生します。このローンの額は地方・都市部。駅近く・郊外などによってかなりのばらつきが出ます。おそらく最低でも月20万円・都心部などの高いところでは80万円クラスの規模になってもおかしくはありません。
また人員面でも少なくても医師と看護師の確保などが必要になります。眼科や整形外科などは視能訓練士や理学療法士などの医療スタッフが必要になることもあります。このスタッフを常勤で雇用したら1人あたり年間で400万円から500万円はかかります。
事務員さんなどは奥さんや身内の方に手伝ってもらうことも可能ですが、それでも多少の人件費はかかってしまいます。いずれにしても固定費もそう簡単には減らせません。この収入が減る・固定費が変わらないというところが病院・診療所経営の難しいところでもあります。
建物・器具・人件費などででコストは初年度には数千万円程度かかると思われます。科目により設備コストが高いもの、低いものがあります。それら設備機器を購入にするか、リースにするかは考えていく必要があります。お金の少ない時点ではリースを選んで、リースの償還が終了して経営が順調に進んだ時点で買い替えという道を選ぶのも1つの道です。
収益=収入ーコストで試算すると、前年度の収入が年間7,500万円・固定費などのコストが5,500万円であれば、2000万円程度が手元に残ります。
これからのクリニック経営においては、診療報酬の点数の減少やスタッフの方の昇給や新たな求人費用などもかかっていき。器具代などのリース費などはどんどん減っていく方向にあるのですが、それでもコストもかかってきます。
数年後に収入が7,200万円、コストが5,600万円だとクリニックの収益は1,600万円程度になります。今後のクリニック経営は厳しくなっていくことも予想されます。
ただ科や開業する地域などによっても異なるところがあります。一般に都市部・内科・整形外科・歯科などで開業していきたいというのであれば厳しいかもしれません。ただ都市部でも美容整形外科であればチャンスはあるかなという気がします。逆に地方都市・産婦人科・小児科・眼科などで開業していけばチャンスは多くなるかなという気がします。
ただこれも一般論であって必ずしも多くの人に当てはまるかどうかまではいえません。開業・経営自体は自分の城・パターンを作らなければいけないので万人に当てはまるものはないのかもしれません。
これからのクリニック医院・経営に大事なこと

これからのクリニック経営にとって重要なことは、まずはしっかりとした開業戦略を立てることが重要になります。競合をしっかりと調査すること、さらに開業する科を選定していく必要があります。
さらに収入とコストといった数字を知ることも重要になります。1日何人を診療すれば、1か月・1年でどの程度の収入が見込めるか、建物代・施設設備費・人件費もかかりますので試算して把握しましょう。設備機器や備品などの購入は、ローンにするのか、キャッシュにするのか。購入にするのか、リースにしていくのかなども大事な判断ポイントとなります。
このあたりのことを開業時にしっかりとプランニングしておく必要があります。
あとは診療時の患者さんへの接遇は、医院経営において非常に重要なポイントです。医師を看護師の方がサポートをしているところもありますが、医師の言葉は重いですので、看護師に頼らず医師自身もしっかりと患者さんと対峙しましょう。
現在、口コミがネットで広がり、良い・悪いを広い範囲の方々に判断されてしまう時代になっています。些細なクチコミが、その後の医院経営に大きな影響を及ぼしてしまう可能性もゼロではありません。接遇、患者さんとのコミュニケーションをしっかりと行えるどうかで、クリニック経営がうまくいくかの分かれ目にもなります。
また、もちろん手術を含めた治療技術も重要です。経営ができても対応が良くても医師本来の治療技術がないと安定して患者さんはきません。脳血管手術・がんの除去手術・レーシック・白内障手術・美容整形手術などの技術的な手腕は大事なポイントです。
開業医になり、クリニック経営を軌道に乗せていくことは決して簡単なものではありません。ただ戦略をしっかりと立てて、適切な事業計画書を作成することで、クリニック経営において勝ち抜けられる可能性は格段に高まります。
クリニック設立・経営において、適切にサポートをいただくための専門家をどう選ぶかも重要になります。
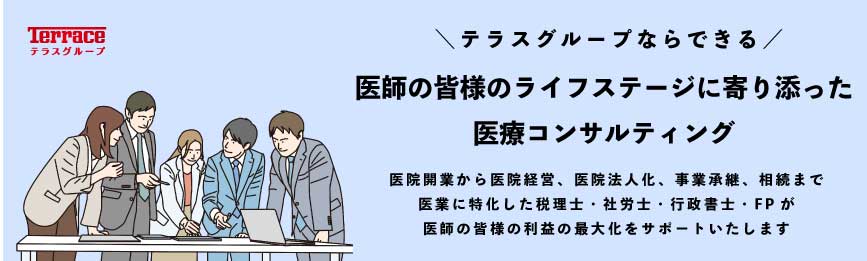
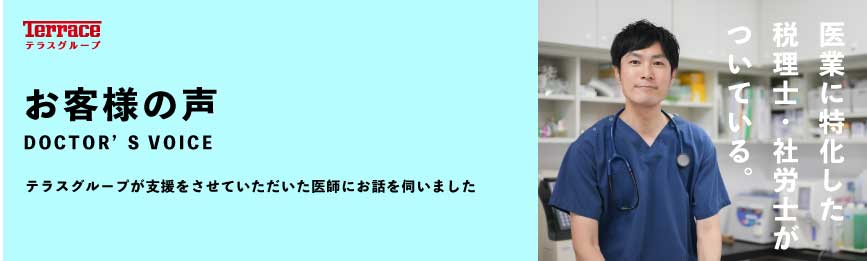


監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。